2001年に初回放送され「沖縄ブーム」を巻き起こしたNHK連続テレビ小説第64作「ちゅらさん」が4月1日から総合テレビで再放送(月~金曜午後0時半、全156回)されている。NHKの番組編成計画によると、多彩なジャンルのアーカイブス番組を活用し、映像資産を視聴者に還元する目的の下、好視聴率時間帯に放送する。ヒロイン古波蔵恵里(国仲涼子)が沖縄の家族や東京で一緒に暮らす「一風館」の住人らに見守られ、成長する姿を描く物語。Kiroroによる主題歌「Best Friend」や番組に登場するキャラクター「ゴーヤーマン」などもヒットし、続編もパート4まで制作された。一方、沖縄の描かれ方への賛否もあった「ちゅらさん」を24年の時点でどう見るか。沖縄戦後史研究者の古波藏契と漫画編集者の金城小百合が考察する。

■愛情も反発も 故郷への思い投影
金城小百合 漫画編集者

初回放送当時、沖縄生まれで本州育ちの転勤族、さらに大学進学で東京に上京したての18歳だった私は「ちゅらさん」を楽しめなかった。私自身のアイデンティティーのために、東京で生きていくために、己にとって決別すべき沖縄が描かれていたからだ。しかし、今回の依頼で、何度も号泣しながら、全156話を夢中で見通した。
私の両親は沖縄生まれだ。両親の望郷の思いは強く、父母が語る熱のこもった沖縄の戦後の記憶を、私は自分のものとして育った。ドル硬貨を握りしめてバッシュ(バスケットシューズ)を買いに行った高揚も、米軍基地への怒りも、安保闘争も、上京にパスポートが必要だった違和感も、東京で言葉をバカにされた悲しさも、私は沖縄のスタンダードな話としてビビッドに受け取っていた。加えて帰郷した際には、おじぃもおばぁも、誰だか分からない親族も一緒にビーチパーティーで飲んで歌う“ザ・沖縄”な親戚付き合いをしていた。
その半面、思春期にはそれらに嫌気が差していた。私は沖縄というアイデンティティーのせいで周囲と隔てられていると感じていた。例えば、学校で基地問題に少しでも言及すれば「でも、基地のおかげで金もうけしている人も多いんでしょ」と友人から軽くいなされる現実に、いちいち傷ついていた。私は私を守るために、沖縄から決別しないといけないように感じるようになっていた。
「ちゅらさん」には大好きな沖縄が描かれている。
兄弟の名前を呼ぶイントネーション、三味線の音色、元気なおばぁたちの宴会、命どぅ宝、キジムナー…。大好きで、いつも帰りたいと思う沖縄がそこにあった。特に平良とみさん演じるおばぁが素晴らしく、ひょうきんで悪戯(いたずら)めいたキャラクターながらも的を射た発言をクリティカルに繰り出す姿に、「そうそう、おばぁはこうでなくちゃ」と喜んだ。大好きだ。ゴリさんが演じる恵尚という、いわゆる「ダメな人」が当たり前に受け入れられている世界も居心地が良かった。
大好きなのに、反発をせざるを得ない。「ちゅらさん」への思いはまるで故郷への思いそのものだ。しかし、主人公・古波蔵恵里は沖縄の精神そのままに東京で生きていく。今更ながら恵里に学んだ気持ちにもなった。一方で令和を生きる一人としては、恵里の人生の描き方には、ヒヤリとするところがいくつもあった。悪い意味での懐古主義も描かれていたように思う。
しかし沖縄は進み続けている。再放送真っただ中の4月15日、沖縄のラッパーAwich(エーウィッチ)が世界的音楽の祭典コーチェラ・フェスティバルで沖縄をレペゼン(代表、象徴)していた。Awichの髪の毛の多さや沖縄の子そのものの顔つきを見るたび、故郷を誇らしく思う。沖縄が抱える複雑さや痛みは、これからの日本にとって大事な要素になるだろう。それを世界に発信するアーティストもいる。「ちゅらさん」をいつも胸に、これからの世界をアップデートしていきたい。
【きんじょう・さゆり】 1983年那覇市生まれ。漫画編集者。小学館勤務。ひめゆり学徒隊をモチーフにした「cocoon」などの漫画を担当する。夫は「最後の音楽〓 (〓=音楽の反復の終了を意味する記号) ヒップホップ対話篇」などの共著があるラッパーで音楽家の荘子it。
■作品イメージと現実の距離 注視
古波藏契 沖縄戦後史研究者
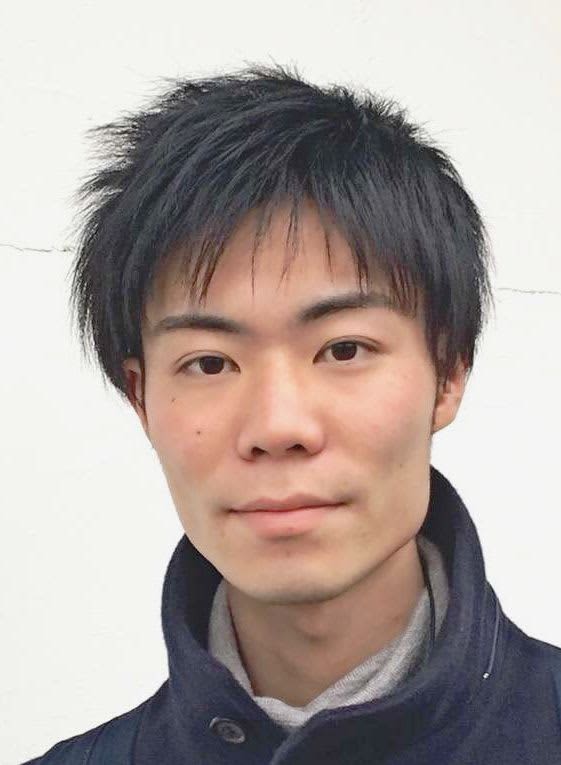
「ちゅらさん」は、主人公・古波蔵恵里の成長物語であり、同時に復帰後の沖縄が日本社会に溶け込んでいく道筋を描いた物語でもある。そのことは、恵里の誕生日が復帰の日の1972年5月15日であることからも明らかだ。
話の補助線として、72年6月15日の毎日新聞に「沖縄の心」という見出しで掲載された記事を見ておこう。
これは沖縄と日本本土で行った世論調査に基づく記事で、本土の「競い合いの文化」と、沖縄の「やさしさの文化」を対比している。いわく「沖縄の人びとの間にいまなお脈々と息づいている信頼感や連帯感、やさしさといった“沖縄の心”は、本土の人びとが失ったことに気づき、取り戻そうと願っている“日本の心”である」。その失われた“日本の心”が復帰を機に帰ってきたというわけだ。
だが同時期には逆の見立てもあった。例えば、復帰の翌年の73年には、沖縄の各界名士から成る「沖縄の文化と自然を守る十人委員会」が「沖縄の心」の喪失と「銭の世(ジンヌユー)」の到来に警鐘を鳴らした。
「ちゅらさん」はと言えば、十人委員会側の悲観的な見方を否認するかのように、「沖縄の心」が本土社会を変えていく可能性を恵理というキャラクターに託す。そのモチーフが全面展開するのは、物語の中盤、舞台が東京に移って以降だ。恵里が東京で出会う人々は、毎日新聞の記事が言う「沖縄の心」を煮詰めたような恵里の個性に当初はたじろぎ、独善的で過干渉な宇宙人のごとき存在として遠ざけようとするが、やがて感染するかのように心を開き、他者への信頼を取り戻していく。
象徴的なのは、恵里が下宿する一風館の変化だ。初登場時は、顔の見えない住人が暮らす薄暗い都会のマンションに過ぎなかったのが、恵里の入居後は疑似家族のような団欒(だんらん)の場に変わっていく。
恵里が周囲の人々の変化を促しながら自分の居場所を見いだしていくストーリーには、冒頭の記事が想定したように、“沖縄の心”が本土の人々を感化し、失われた“日本の心”を回復させるという期待がうかがえる。
最終話の終わり際、語り手として恵里の成長を見守ってきた「おばぁ」(平良とみさん)が突如として視聴者に向き直り、「沖縄を忘れないでね」と呼びかけるのも、そうした期待の表れだろう。基地問題などへの言及は慎重に避けているものの、「ちゅらさん」は願いにも似たメッセージを含んでいる。
では、ドラマのメッセージは現実の社会でどのように受け止められたのか。各種調査から明らかなように、沖縄でも周囲とのつながりを重んじる文化の衰退は著しい。沖縄が本土を感化するどころか、沖縄の本土化が進んでいると言ってもいい。
作り手の思いとは逆に、十人委員会の悲観的なシナリオが進行しているようだ。「ちゅらさん」が創作したイメージと、現実を重ねることで浮かび上がるギャップ。これこそ今回の再放送で注視すべきポイントだろう。
【こはぐら・けい】 1990年浦添市生まれ。沖縄戦後史研究者。明治学院大学社会学部付属研究所研究員。博士(現代アジア研究)。単著に「ポスト島ぐるみの沖縄戦後史」、共編著に「つながる沖縄近現代史」、監修に「『守礼の光』が見た琉球」など。
