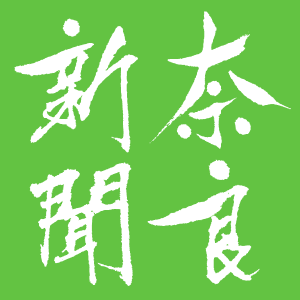初夏の古都を彩る伝統行事「薪御能(たきぎおのう)」(同保存会主催)が17日、奈良市内で開かれた。
夕刻に興福寺南大門跡「般若之芝」(同市登大路町)で行われた南大門の儀は、衆徒(僧兵)による「舞台あらため・外僉義(げのせんぎ)」で幕が開けた。
「源氏物語」の主人公、光源氏のモデルになったとされる源融(みなもとのとおる)が昔をしのんで遊楽の舞を舞い夜明けとともに月の都に帰る物語の金剛流能「融」が、かがり火が揺らめく幽玄の世界で厳かに舞われた。観世流能「歌占(うたうら)」や大蔵流狂言「延命袋(えんめいぶくろ)」も演じられた。
これに先立ち、同市春日野町の春日大社舞殿では「咒師走(しゅしはしり)の儀」があり、金春流能「翁(おきな)」が奉納された。
きょう18日も午前11時から春日大社若宮で「御社上(みやしろあがり)の儀」、午後5時半から興福寺南大門跡で南大門の儀がある(雨天の場合はなら100年会館)。当日協賛席は6500円。
薪御能は869(貞観11)年、興福寺修二会で奉納された猿楽が始まりで、野外能の起源とされる。