
リ・リ・リリッスン・エイティーズ〜80年代を聴き返す〜 Vol.43
渡辺香津美 / TO CHI KA
渡辺香津美とマイク・マイニエリ
前回、吉田美奈子のアルバム『MONOCHROME』に、ヴィブラフォン奏者のマイク・マイニエリ(Mike Mainieri)が参加したのは、渡辺香津美の『TO CHI KA』というアルバムをプロデュースした彼が、その後の「トチカ・ツアー」で来日していた際に…というお話をしました。
ではなぜ、マイニエリが『TO CHI KA』をプロデュースするに至ったのか。まずは香津美さんが『White Elephant』(1972年発売)というレコードを聴いて、深い感銘を受けたのがそもそもです。これは60年代末に、マイニエリが中心となり、ランディ&マイケル・ブレッカー(Randy [trumpet] & Michael Brecker [sax])、スティーヴ・ガッド(Steve Gadd [drums])、トニー・レヴィン(Tony Levin [bass])、ヒュー・マクラケン(Hugh McCracken [guitar])らとともに結成した“The White Elephant Orchestra”(あるいは、“White Elephant”、“Mike Mainieri & Friends”とも呼ばれた)が残した唯一のアルバムです。
そのマイニエリが、深町純が招集した“New York All Stars”の一員として、1978年9月に来日した折に、六本木ピットインでの香津美さんのライブを聴きに来てくれたそうです。その時に、「チャンスがあったらプロデュースしてほしい」→「喜んで」的な会話があったようですが、そういうのは得てしてなかなか実現しないもの。
ところが、1979年11月6日、今度は香津美さんが参加したYMOのワールドツアーの、ニューヨークのボトムラインでの公演終了後、マイニエリが楽屋に顔を出し、開口一番、「プロデュースの話はどうなった?」と切り出したから、これは本気だとなりまして、翌年早々に実現の運びとなったわけです。
マイニエリがまず、大きな方針として提言したのが、日本であれこれ準備せず、早めにニューヨークへ来て、出歩いたり食事したり、ライブを観たり、美術館を覗いたりして、街の空気を浴びながら、曲やアレンジを考えたほうがいい、ということでした。既に何度か海外録音も経験していた香津美さんですが、やはり、人選や工程まで事前に組み立ててから行くのが常だったようで、その初めてのやり方にワクワクしつつも、結局4、5曲は用意していったとのことです。マジメなお人柄ですね。というより、たいていの日本人ならそうするでしょうね。
1980年。ともかくレコーディングは3月くらいから予定しつつ、でもマイニエリの提案通り、1月30日には奥さんを連れて渡米しました。ほんとにミュージシャンの人選も白紙だったようで、たとえば、香津美さんが、たまたまチケットが手に入って観に行った"Weather Report"(以下WR)の話をしたら、ドラマーはWRのピーター・アースキン(Peter Erskine)がいいかも、となって、その場で電話してスケジュールを押さえたそう。
かと思えば、「Unicorn」という曲は、香津美さんがまさにWRの「Teen Town」という曲に触発されてつくったので、当然アースキンでいくんだろうと思いつつ、デモを聴かせたら、これはファンキーなビートがいいからと、スティーヴ・ジョーダン(Steve Jordan [drums])とマーカス・ミラー(Marcus Miller [bass])を、やはり直電で手配したり。
―― といった話は、香津美さん自身が、某音楽誌に掲載された「ニューヨークレコーディング日記」の中で書いています。
こんな話を聞いているだけでもドキドキしてきますが、それぞれの楽器で、世界で10本の指に入るくらいの実力と知名度を持つミュージシャンたちが、電話1本で1ヶ月前にブッキングできるなんて、さすがはニューヨークですねー。
そして、もう一つあった基本方針が、生演奏のグルーヴをだいじにすることでした。そのためにレコーディングスタジオに入る前にリハーサルも行いました。ギターはサイドとソロと、香津美さんは一人でダビングするつもりでしたが、マイニエリは、もう一人ギタリストを呼んで、全体像をつくりながらやったほうがいいと主張し、ジョー・カロ(Joe Caro [guitar])を手配しました。リード楽器のソロも、いくつか後からやり直したものもあるようですが、基本的にはせーので演奏しながら録ったそうです。ミュージシャン同士の“呼吸”と即興性を重視する、つまりはジャズの手法ですね。各曲最低3テイク以上は録ったけど、2テイク目を採用したものが多かったとのことです。

好みじゃなくても好きになってしまうアルバム
以上のような背後のストーリーをまったく知らないでこのアルバムを聴いた時は、正直言って、「なるほど、がんばってるねー」程度の感想しかなかった私でした。
だいたい私は、「録音芸術」というか、レコーディングスタジオで可能な手法を存分に使って音を構築していくタイプの音楽のほうが好きなので、もちろん生演奏のグルーヴは非常にだいじだとは思っていますが、それは「生演奏であるなら」ということで、そもそも生演奏かそうでないかはどうでもよく、どれだけ“面白い”アレンジかということ、そしてもちろんメロディ(たまに歌詞)のよさのほうに関心があります。
なので、私は『TO CHI KA』の前作、坂本龍一や矢野顕子が参加したアルバム『KYLYN』(1979)のほうが好きでしたし、中でも坂本龍一作曲の「E-Day Project」とかが気に入っていました。
いや、ストーリーを知った時も、要するに、メロディやアレンジに時間をかけず、演奏のグルーヴや即興性を重視するということですから、やはり私の好みからは遠いなと、確認できたようなものだったのですが、それから改めて聴いてみると、なんだか妙に親近感のようなものを感じ始めました。
自分の無意識が勝手に冷凍フリーズして無味無臭だったものが、一気に解凍されて、ミュージシャンたちの息遣いとか、放つ熱気が伝わってくるような気になりました。私も何度かは訪れたことがあるニューヨークのスタジオの空気感なども、蘇ってきました。“自己暗示”なんじゃないの?と言われるかもしれません。たぶんそうかも。でも、自己暗示で音楽がよく聴こえるなら、それでいいと思っています。
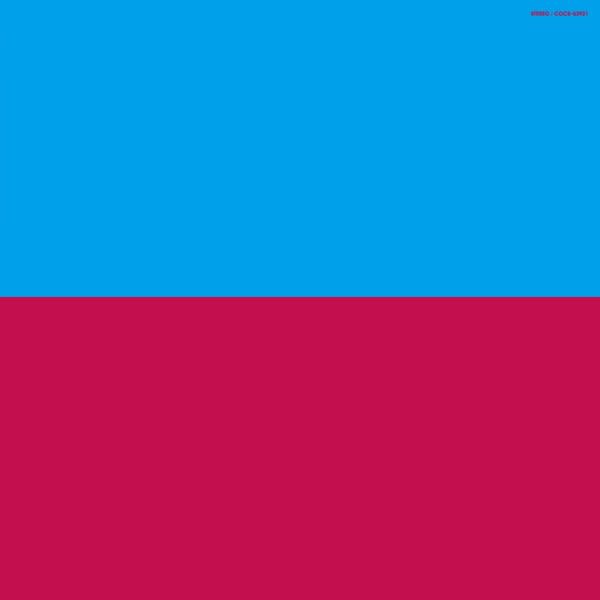
ミュージシャンたちがその身体能力を最大限に発揮しえた作品
たしかにどの曲もメロディ的には心を捉えるものはありません。香津美さんの代表曲のひとつになった「Unicorn」も、テーマは決してメロディアスじゃない。だけど、ミュージシャン全員の息の合い方にはゾクゾクしますし、香津美さんのギターソロはまるで火がついたよう。マイニエリも素晴らしいヴィブラフォン・ソロを繰り広げています。やや希少な楽器だし、たいていはサウンドの背景を静かに描いているような存在だから、このソロは刺激的です。
「Cokumo Island」でのマイケル・ブレッカーのテナーサックスソロもすごい。それを煽り立てる他のミュージシャンたちの演奏もすごい。まさに同時に演奏しないと生まれない世界です。某動画で香津美さん自身が語っていた話によると、ソロが止まらなくて、録音テープのほうが終わってしまったのだとか。だからこの曲は長いフェードアウトになっています。
サウンドも全体的にオーソドックスなフュージョンで、特に目新しいところはありません。この前年にはYMOのツアーで、当時最先端の「テクノポップ」を伝道する立場に居た香津美さん自身の状況や、「ディスコ」の大流行という時代背景を考えると、そういうものからの影響を微塵も感じないことが不思議なくらいですが、マイニエリはあえてこうしたんでしょうね。こういうやり方しかできなかったのかもしれませんが、香津美さんにとってもこれが非常にしっくり来たであろうことは、その後もマイニエリ、そしてエンジニアのダグ・エプスタイン(Doug Epstine)と、何作もコラボレーションしていることで分かります。
ミュージシャンたちがその身体能力を最大限に発揮しえた作品は、音楽としてと言うか、表現として古くならないこと、表向きは地味でも、向き合えばいつでもエネルギーを与えてくれることを、このアルバムに改めて教えられました。
カタリベ: ふくおかとも彦
アナタにおすすめのコラムタイトルタイトル
80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!
