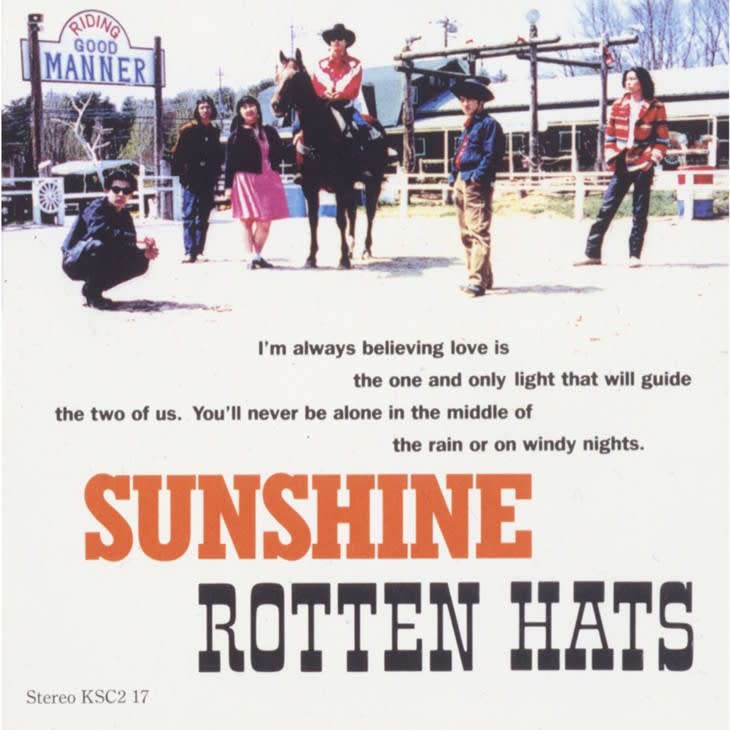
佐橋佳幸の40曲 vol.11 ALWAYS / ロッテンハッツ 作詞:片寄明人 作曲:片寄明人 編曲:佐橋佳幸
渋谷系の大トリ、ロッテンハッツ登場
1980年代後半、東京のライブハウスシーンを賑わしていた “モッズ〜ネオGS ムーヴメント”。そこで交流のあったいくつかのバンド出身のメンバー6人が合流して生まれたのがロッテンハッツだった。やがて6人のうち片寄明人、高桑圭、白根健一はGREAT3を、中森泰弘、木暮晋也、真城めぐみはヒックスヴィルをそれぞれ結成。ふたつのバンドへと分かれてゆくことになるのだが。
結成当初のロッテンハッツは、ダン・ヒックス、ジム・クウェスキン、ジョン・セバスチャンなどに通じるどこか懐かしいフォークソングやジャグバンド・ミュージックを、パンク / ニューウェイブ世代ならではの新鮮な視点で再解釈した独自のサウンドで幅広い世代のリスナーから注目を集めていた。
インディーズからリリースした初アルバムが評判を呼び、1992年にメジャーデビュー。アマチュア時代からの音楽仲間でもあるフリッパーズ・ギターやオリジナル・ラヴ、フィッシュマンズ、東京スカパラダイスオーケストラら “渋谷系” ミュージシャンたちとも互いに刺激し合ってきたことで知られる面々だけに、そのデビューはまさに “渋谷系の大トリ登場” といった風情だった。
初めてのバンドプロジェクトのプロデュース
佐橋佳幸は、彼らがキューンソニー(現:Ki/oon Music)からリリースした2枚のアルバム『SUNSHINE』(1992年)と『Smile』(1993年)のプロデュースを手がけている。
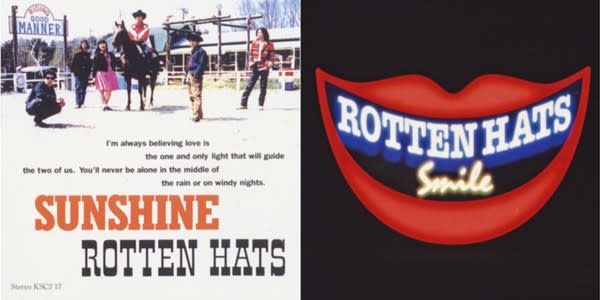
「キューンソニーでロッテンハッツの担当ディレクターだった畑くんという人は、かつて渡辺美里の事務所で宣伝を担当していたの。ある日、旧知の畑くんから突然連絡がきて、“今度こういうバンドがデビューするんだけどプロデュースをしてもらえませんか” と依頼された。ロッテンハッツは全員がもーっっのすごい音楽オタクでね。クラブDJやってたり、レコード屋でバイトしていたり。で、実はディレクターの畑くんも、昔から僕といつも音楽話で盛り上がっていたオタク仲間だったの。それで畑くんとしては、このバンドがやろうとしていることを理解して、彼らと音楽の話で渡り合えるプロデューサーは佐橋くんしかいないだろう… と考えたらしいんです」
「そんなわけで、まず彼らが練習しているスタジオに行って演奏を見せてもらった。練習が終わってから一緒にゴハンを食べに行ったんだけど、そしたら、もう、さっそくオタクトークが爆発してさ(笑)。特に片寄なんか人一倍のマシンガントークだからね。さっきやってた曲は誰それのカヴァーで、その次の曲は僕が誰々のレコードを聴いた時に思いついて書いた曲で、あっちの曲を書いたのは僕じゃなくて誰々で… って、もう、説明を始めたら止まらない止まらない。僕がかなわないって言うんだから、どれだけオタクなのかわかるでしょ。曲もいいし面白いバンドだなと思って。“わかった、引き受けるよ” と。そうして、ロッテンハッツとの日々が始まるわけです。僕にとってはこれが初めてのバンドプロジェクトのプロデュースでした。絶対にバンドだけはプロデュースしないと決めていたのにね」
オレがプロデュースしなかったら誰がやるんだよ

この時期の佐橋はすでにプロデューサーとしての仕事も順調。1990年代初頭のプロデューサー・ブームも追い風となり、次々と以来が舞い込んでいた。佐橋が全面プロデュースするレーベルを立ち上げたいという提案もあった。バンド出身だったこともあり、当然バンドプロデュースの依頼も多数。聞けばびっくりするほどの大物バンドの名も…。
ーーが、バンドのプロジェクトについては、いくつかのバンドのシングル曲でサウンドプロデュースを手がけたことを除いて頑なに断り続けていた。UGUISSでの苦い経験は少しずつ過去の出来事になりつつあったとはいえ、バンドでやっていくことの難しさは誰よりもわかっていたからこそ、だ。が、ロッテンハッツに出会った時、佐橋の心に “これ、オレがプロデュースしなかったら誰がやるんだよ” という思いが湧き上がった。
「バンドのレコーディングだからね。都内でちょこちょこプリプロしてからスタジオに入る… みたいなプロセスで作ってもしょうがないと思ってさ。山中湖のスタジオで合宿レコーディングすることにしたの。UGUISSの時、何かっていうと合宿していたのと同じく(笑)。エンジニアは僕のソロアルバムも録ってくれた山口州治さん。あと、ロッテンハッツにはキーボードがいないから、バンドものに付き合ってくれて、しかも彼らのオタクトークについていけるのは柴田俊文しかいないと(笑)」
「それで柴田にはコ・プロデューサー的なスタンスでやってほしいと頼んだ。中森さんと木暮くんという2人のギタリストがいて、片寄もギターを弾くバンドだから、僕はギタリストではなくプロデューサーとしての仕事がメインだったけど。柴田はライヴなんかもずっと付き合ってたね」
最低限の理論とかコードとか、そういう共通言語を教える佐橋学校
プロデューサーとしての佐橋の仕事は、彼らがやりたいと考えているイメージの具現化だった。音楽的な引き出しは無尽蔵な6人からは多彩で多様なアイディアがどんどん飛び出した。ただ、普段のスタジオセッションには欠かせない “譜面” という共通言語がないことが障壁となった。
「とにかく彼らにはやりたいことがたくさんあるし、イメージもはっきりしているんだけど。具体的にどうしたら自分たちの思う形にできるか、その技術に関してはみんなまだ未知数だった。譜面にも強いわけではないしね。いざ一緒にスタジオに入ってみると、コミュニケーションがあんまりうまくとれなかったんです。どうしようかなと思ってたんだけど、ある時、どっかのスタジオでホワイトボードを持って来てもらって」
「そこでコードの仕組みとか、基本的なことから俺がボードに書いて、楽典の講義を始めたんですよ。要するに “佐橋学校”(笑)。僕もバンド出身だから自己流で覚えていったでしょ。だから彼らの感覚はわかるんだ。でも、やっぱり最低限の理論とかコードとか、そういう共通言語がないとコミュニケーションが難しいなと思って」
今やさまざまなセッションで活躍し、佐橋との仕事も多いベースの高桑圭は、いまだにその時の “佐橋学校” のことを話すという。
「あの時に教えてもらったことが、どれだけ役立ってるかわかりませんって、いつもキヨシ(高桑)には言われる(笑)。でも、理論のことはさておき、実はあの頃から演奏力が抜きん出てたのはキヨシだったんだよ。そのことに俺と柴田とでいち早く気づいて。レコーディングの時も、まずキヨシに伝えてからみんなに説明してもらう… という、ある種の通訳的なこともやってもらってた」
シュガー・ベイブの「パレード」の90年代版をめざした「Always」
そんなふうに高桑とはプレイヤーとして共鳴するところがあった。佐橋といちばん年齢の近い中森とは共通の音楽体験で話し込むことも多かった。メンバーそれぞれ異なる個性を持つバンドから、プロデュースの過程で佐橋もさまざまな刺激をもらった。中でも彼の心をとらえたのは片寄のソングライティング・センスだった。

「そんなこんなで、どうにか1枚目が完成して。「STAY」という曲がTBS系ドラマ『ホームワーク』の挿入歌になって、ちょっと名前も知られるようになってきて。その頃にソングライターとしての片寄っていうのがやっぱりすごいな… と気づいたんです。これからもっと伸びていくんじゃないかなと確信した。趣味もいいしね。中でも「Always」は名曲だと思う。フィフス・アヴェニュー・バンド的な、スイートなニューヨーク・シャッフルというかね。もともとシュガー・ベイブの「パレード」の90年代版をめざそう… といった意図があったんだけど。すごくうまくいったと思う。片寄のソングライターとしての魅力はもちろん、僕が思うロッテンハッツらしい “原点” を感じさせる曲」
さあ、始まるぞ…っていうところでバンドは見事真っ二つに
セールス的に大成功というわけではなかったが、ユニークで上質な音楽性の評判は悪くなかった。業界的にもネクストブレイクの有力候補としてじわじわ注目度が高まっていた。そんなわけですぐにセカンドアルバムの制作が決定。プロデュースは引き続き佐橋が手がけることになった。ところが…。
「さあ、始まるぞ…っていうところで、何か様子がおかしい。なんとなくグループ内で2つに分かれちゃってるんだ。後にGREAT3になる3人と、ヒックスヴィルになる3人に。もともと別々の個性が集まったバンドだから、音楽的指向もそれぞれ違っていて、そこがロッテンハッツの面白いところでもあった。でも、ホントに、見事、真っ二つになっちゃってたの。“これどういうこと?” って聞いたら、やりたいことがいよいよ本格的に分かれてきちゃったんだ、と」
「どうしよう、困ったなと思いながら、それでもアルバムは作らなくちゃいけないからスタジオに入ったの。それで、今回はプリプロダクションをしたほうがいいと判断した。1枚目では、バンドなんだからプリプロなんか必要ない、最初から一緒にスタジオに入ってリハーサルしながら作っていったほうがいい、と。でもGREAT3組とヒックスヴィル組、それぞれにやりたいことができてしまったとなると、いきなり一緒にやっても効率が悪いだろうから。むしろそれぞれのやりたいことをある程度形にしてから一緒にレコーディング・スタジオに入って録音するほうがいいと考えたんです」
「で、2組それぞればらばらにプリプロしてレコーディングへ。前回同様、山中湖で合宿レコーディングしたんだけど。そこでも2組に分かれてるからさ。ある日、食事の場所で俺、説教したんだよ。お前ら、仲良くしろって(笑)。まあ、彼らの成長を間近に見てきたから、2つに分かれるのも必然だと理解はしていたの。曲作りの面でもそれぞれ、ヒックスヴィル組の曲はすでに今のヒックスヴィルみたいなテイストへと成長してきていたし、GREAT3組のほうも今で言うちょっとシティポップ的な方向性になっていたし。ただね、バンドだからさ…」
絶対に解散するなって思いながらアルバム作るのはすごくつらかった

こうして完成したアルバム『Smile』は、残念ながらロッテンハッツにとってメジャーからの2作目にしてラストアルバムとなってしまった。が、バンド解散後も、片寄のソロプロジェクトで佐橋がプロデュースを手がけることになったり、佐橋から松たか子への楽曲提供を依頼したり。前述のように、高桑とは数々のセッションで共演したり。と、折々でメンバー個々と仕事をすることも。
「うん。だからね、やっぱりバンドは難しい。個性的であればあるほど難しい。2枚目のアルバムもすっごくいい曲がいっぱい入ってるんだけど、なんか、これ絶対に解散するなって思いながらアルバム作るのはすごくつらかった。しかも、柴田も一緒だったでしょ。2人でUGUISS時代のこともずいぶん思い出しちゃってさ。こいつら、もうちょっと仲良くできなかったのかなーとか、もうちょっと俺にできることはなかったのかなーとか、いろんなことを考えた」
「でも、結果バンドは解散。僕もそれまで頑なに断ってきたバンドのプロデュースを引き受けたのに、そうなってしまったことには複雑な思いもある。ただ、貴重な、面白い経験をさせてもらったことには感謝しています。特に1枚目を作っていた時の彼らが醸し出していたバンドとしての雰囲気が忘れられないな。それまで感じたことのないものだったから。やっぱりいいバンドってさ、ギリギリのバランスの緊張感が良かったりするんだね。ライブも楽しかったし。彼らがステージに立つと、すごくお客さんを幸せにするオーラみたいなのが放たれて。まぁ、二度と一緒にやることはないのかもしれないけど、あの頃のことを思い出すとね、やっぱりまたやればいいのになって思ったりもしてしまうんだよね」
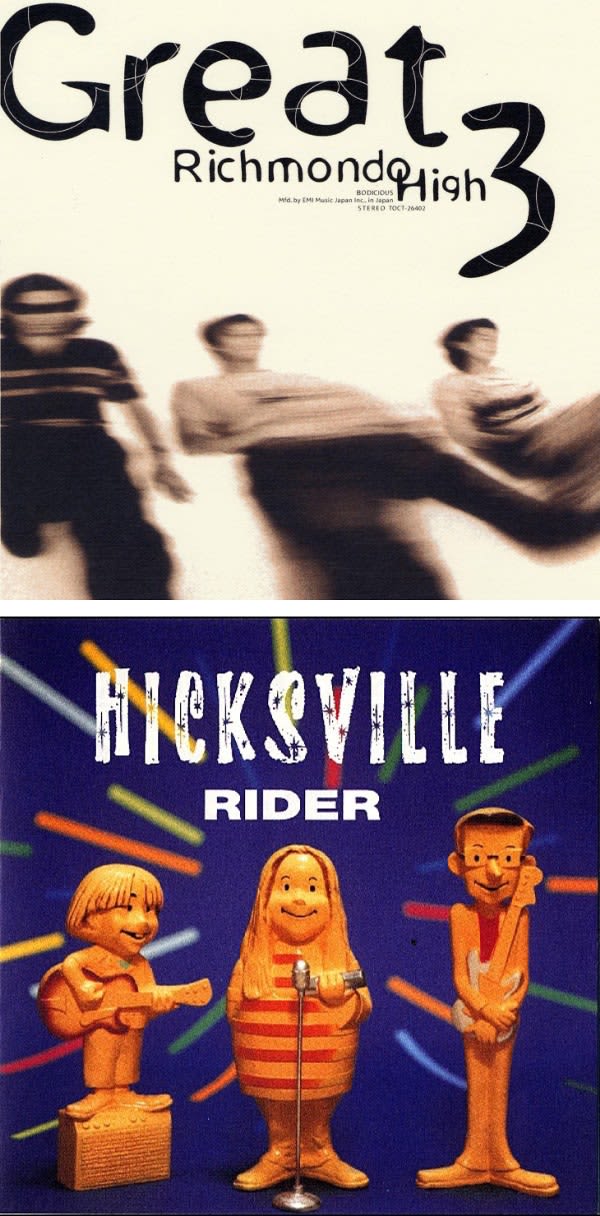
次回【佐橋佳幸の40曲】につづく(2/3掲載予定)
カタリベ: 能地祐子
アナタにおすすめのコラム【佐橋佳幸の40曲】鈴木祥子「ステイションワゴン」の背景にあるサウンドの秘密とは?
80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!
