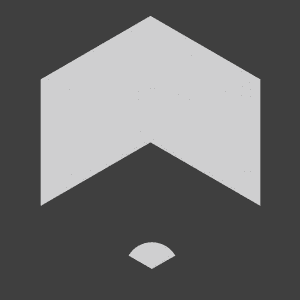中国や米国を渡り歩き21年から東大教養学部で教壇に立った王欽(おう・きん)准教授(東大大学院総合文化研究科)は、魯迅(ろじん)など中国近現代文学を下地としながら日本のサブカルチャーに関心を持つ新進気鋭の研究者だ。現在の研究への道のりや、緊迫する国際情勢に対する文学研究者の視点からの展望を聞いた。(取材・高橋潤)
偶然のままに進んだ研究者への道
──華東師範大学、ニューヨーク大学、北京大学そして東大という学究の経歴を持っていますが、研究者への道のりはどのようなものでしたか
2004年から華東師範大学の中文系(日本で言う中国語中国文学科)に入り、中国近現代文学を専攻しました。もともと魯迅に関心があり、魯迅全集も読んだことがあったので、自然に魯迅研究という領域に入ったという感じですね。結局、卒業論文も魯迅の『狂人日記』についての新しい読解を示すというものでした。そこから成績が良かったので自然と華東師範大学の大学院に入り、引き続き魯迅やそれに関わる作家など、中国近代の研究を進めようと思いました。
偶然にも、そこで後の指導教員となる先生に出会い、ニューヨーク大学への留学に誘われました。そのときは博士課程のことなど全く考えておらず、将来どうすべきか、あるいは何をしたいかなど一切考え無しで、ただ毎日勉強していただけでした。ですから、この事件(笑)によってその後の人生が決まったといったところでしょうか。2年間猛勉強してニューヨーク大学の比較文学専攻に進学し、米国で6年間滞在しました。
比較文学と言われてもあまりピンと来ないかもしれませんが、米国の比較文学専攻では、例えば日本文学と中国文学とを比較するといったことは一切やらないのです。むしろ、いわゆるヨーロッパ哲学を読むところですね。一方、哲学専攻は主に分析哲学や道徳哲学に集中しています。例えば、カント、ヘーゲル、マルクスなどは、ほぼ比較文学で扱われています。
博士論文のテーマは「20世紀中国近代文学における個人あるいは個体の形づくり」でしたが、正直に言って頭には文学者と言うより、デリダやアガンベンなどの20世紀後半の哲学者のことがありました。つまり、いかに 20世紀中国近代文学を手掛かりにして、デリダやアガンベンの議論と対話をしていくか、という仕事でしたね。
それから中国に戻って北京大学で2年間にわたってポスドクをやりました。なぜならそこの中文系は「宇宙一」と呼ばれているからですね(笑)。北京大学の先生や学生には、自分たちがやっていることは本場の中国近代文学研究なのだ、という雰囲気がありました。私はよそ者としてちょっとそれに首を突っ込んでみようかな、という気持ちでした(笑)。そこでは自身の研究を整えて英語で一冊の単著として出版しました。

──留学から今に至るまでをどのように振り返りますか
留学していた2011年から2017年という6年間を振り返ってみると、その期間は一つの歴史的に重要なターニングポイントだったと思っています。ここから少しさかのぼれば08年の北京オリンピックなど、改革開放政策がもたらした鮮やかな時期でした。ただ、それ以降は中国を取り巻く全体的な社会的・政治的・文化的なイメージがますます複雑化しました。まさにその時期に私は米国にいたわけです。ですから北京大学へと向かったときは、自分では経験し得なかった「新しい中国」というものに向き合わなければいけませんでした。ただ、その後すぐに日本へと渡ったので、そうした状況に向き合う時間はありませんでしたが。
魯迅研究からサブカルチャーへ
──現在の研究活動は
今は、二つのことを並行して進めています。一つは柄谷行人に関する論文集です。初期から現在までの柄谷行人を一貫して考察するものになります。もう一つは日本の社会問題とでも言いましょうか。アイドル文化やメイドカフェなど、日本社会の周辺部に置かれている若者の文化というところを論じていきたいと思っています。
魯迅に関しては、去年書籍を一冊出版しました。ある意味では、これは私にとって一つの結実です。引き続き魯迅に興味はありますが、2冊目を書く予定はありません。
──魯迅研究をやめた理由は
これまで私もやってきた、歴史的研究・文学的研究・哲学的研究などアカデミアの中で常道とされている研究に飽きたからです。無論、それらの研究はとても大切ですけれど、自分にはちょっと向いていないと思っています。北京大学在籍時、トップの大学で学生や先生とやりとりしていて鮮明に感じたことがあります。中国近現代文学研究という領域に限って言えることですが、皆新しい学問やその方法論を唱えながらも、旧来の伝統を守るのが中心だったということです。学問の方法論に関して、何が正しく何が正しくないのかという線引きが、皆はっきりと認めようが認めまいが、あったわけですね。そうした部分が私には受け入れ難いと感じました。
若者の文化ないしサブカルに注目するのは、これまでの学問の領域を出たいと思うからです。ただ、これを手掛かりとして学問を一般に向けてより開いていくことができるかもしれないとも思っています。世間一般の考え方は、その時代特有の雰囲気でもあります。それを受けて自身の研究を捉え直すという、ある種の双方向的な動きは重要だと思っています。このテーマについて既に中国語でまとめた論文は何編かあります。それらは日本の若者についてのものですが、実は中国の若者を理解する手掛かりにもなるかと思いますね。
──特に日本の若者の文化に関する研究は大きな路線変更です
私から見れば、日本だけでなく中国ひいては世界の若者というのは、ある意味で、連絡なしに全体的な文化を共有しています。それは2000年代初頭から始まった、いわゆる文化的グローバリゼーションのもたらした結果の一つです。例えば、中国の若者は毎日TikTokをいじっていますね。米国や日本の若者もそうですね。昨今、政治的な問題に関してはさまざまな線引きが強化されている一方で、若者の行動は、厳しく引かれている境界線をさりげなく越えてしまいます。突き詰めていけば中国や米国の若者も含めた世界的な現代文化や現代思想、すなわち現在進行中の思想がそこにあるのではないかと思います。

恐ろしいほどの言葉の流動性から政治を、そして社会を見る
──とはいえ国際政治の緊張は日々高まる一方です
私が強調したいのは、どのような政治であれ必ず言葉というものを使わなければならない、ということです。リベラリズムにせよ共産主義にせよ、すべての政治は必ず言葉を使わなければなりません。政治の出発点となっているのは政策でも立場でもなく、言葉そのものです。ですから、言葉というものがいかにして使われているのかというのは重要な問題です。政治の中に使われる言葉は、社会的にいかなる効果をもたらし、そしていかなる人々に理解されているのか、それらは文学研究にとって大事な関心事です。
今の世界中のSNSにはいわゆるヘイトスピーチがあふれています。そこで皆何について議論しているのか、けんかしているのかと問うたら、実は議論の基となる客観的な事実は何一つないのです。皆言葉について、言葉の意味について言い争っているだけです。
ですから、文学研究者にとって重要なのは、言葉の使い方──例えば、ある言葉は異なる時代においていかにして理解され解釈され、新たな意味を与えられているのかということ──をつぶさに考察することで、言葉を新しい側面、新しい使い方、新しい意味に解放し、言葉にひそむ可能性を想像・創造していくことですね。
さらに、現在の人々が使っている「自由」や「平等」などの政治的な言葉──それらの言葉の使い方と、例えば魯迅の時代の使い方は明らかに異なるわけです。両方を比較しながら、果たして今何が問題になっているのかを社会的、政治的に考えるのは文学研究のやるべきことだと思います。
──予想もできないことが頻発する中で、目まぐるしく変遷する多くの言葉や概念の再措定を迫られていると
その通りです。私から見れば、文学研究は他の社会学的な研究、政治学的な研究あるいは国際政治や法律などの研究の大前提とならなければならないのです。われわれは言葉にこだわらなくてはなりません。
言葉は実は政治家に嫌われています。というのも、政治家は言葉の使い方をコントロールしようとしても、できないからです。ですから言論に対する審査があり、SNS でも厳しいポリシーが課されている。言葉をコントロールしたいという事実は、逆説的に言葉の使い方は本来コントロール不可能なものであるということを示しています。
誰だって好き勝手にさまざまな言葉を使っていますが、この事実に対してはほとんど自覚がありません。昨日SNSで使ったばかりの言葉は今日になると忘れてしまう。自分が何を言ったか覚えていないし気にしてもいない。それは、実は文学に関する話でもあります。文学というと、フィクションと理解する人が多いかもしれませんが、決してそうではないと思います。むしろ、文学はわれわれが毎日使用している言葉そのものにあると思います。言葉の意味がますますコントロールできないようになっている今の時代において、文学はますます形を変えながら、流動性として自己を実現していくのではないでしょうか。これほど文学的な時代はありません。現在、伝統的な文学は読まれなくなっているかもしれませんが、時代の雰囲気はますます文学的になっていると思います。言葉にはコントロールできない意味がある、ということにいっそうの注意を向ける必要があるのです。

──文学が不定なものであり、今の時代の流動性がもたらされていると
私から見れば、今の国際政治での政治家の発言における言葉は、無意味になればなるほど固くなっています。皆気を付けながら適切な言葉を探して発言をするわけですから。穏当に、できるだけ害を与えないような丁寧な言葉の選び方をしている。
一方でSNSはヘイトスピーチだらけです。誰も言葉の使い方など注意せず、好き勝手に発言している。社会のレベルと政治のレベルとで言葉の使い方が隔てられているのです。重要なのは、この二つがほぼ調和できない状況に現在のわれわれは置かれているということに、向き合うことです。
──言葉の流動性は今の日本においてどのような状況をもたらしていますか
若者の使っている言葉──しいて言えば「言葉らしくない言葉」──にダイナミズムがあるのではとずっと思っています。例えば少し前に流行った「ぴえん」ですが「ぴえん」は何を意味しているのかと聞くと答えられる人はそう多くありません。多くの人々はこの言葉の意味を把握しないまま使っていたということです。特に高校生などは「ぴえん」(の響き)に興味を持つままになんとなく使っていた。ノリに乗っかるということですね。これはとても大切な感性だと思います。
言葉のダイナミズムは実に恐ろしいものです。政府の公式発表に「ぴえん」などという言葉が現れるはずはありませんよね。「ぴえん」という言葉はそもそも何を意味するのか、そうした簡単なことさえ分からない。さらに若者にとってみれば、その「ぴえん」もすでに時代遅れになっています。今はもうほとんど使われていない。若者は目まぐるしく新しい言葉を発明し、またはさまざまな言葉を生かしている。こうした特別な半ば閉じられている言葉の世界には、言葉の新しいダイナミズム、新しい潜勢力があるのだと私は思います。それは、時には映画や漫画を含める文学作品よりもこの社会に衝撃を与えるものだと思います。
──そうしたダイナミズムが抑圧の対象になっていくと
その通りです。一つ興味深い例を挙げると、中国では旧暦の春節の大みそかに必ず上映されるバラエティー番組(「春晩」と呼ばれる)があって、その番組の中で、コントの出演者が現在の中国社会で流行っている若者の言葉を時々使ってみることがあります。これはよく考えてみると面白いことですよ。もし、聞いているのが若者なのであれば、そうした言葉にそもそも詳しいはずですから面白く感じられません。一方若者でなかったら、そうした言葉を聞いてもピンとこないでしょう。何の話か分からないからです。つまり、この若者の言葉を使ってみるというのには聞き手が存在しないのです。ではなぜあえてそうしたことをするのかというと、それはまさに言葉をコントロールしたいと考えている側が「お前らの言葉は知っているぞ」という姿勢を見せたいからです。中国にも日本にも、そうした訳の分からない言葉はたくさんありますが、それらにどう対処すべきか、というのは政治の側にしてみれば一つの難問でしょう。
そこで学者がやるべきことは、こうした言葉を集めてカテゴライズすることでもなく、そのまま若者を支持していくことでもありません。それらの訳の分からない言葉に潜められている時代的なシンボルを読み取ることです。つまり、例えば「ぴえん」を通じて日本社会を読む、ということです。「ぴえん」は完全に何も意味しないわけではないですよね。「泣く」というか、情動的な泣き方といったものを意味している。それがなぜこの段階で現れたのか、その現れ方に時代の文脈が刻まれていると私は思います。
──しかし、複雑な話、込み入った話になればなるほど、言葉の意味を定義しなければ理解が難しくなります
辞書であれば、言葉と意味を並べればことは足りますが、そうではなくむしろ言葉の意味しようとするものは一旦脇に置いて、言葉が意味し得ないことをつかまえることが大事なのだと思います。なぜ「泣く」ではなく「ぴえん」と言わなければならないのか。それは、相手に言語化できない部分も含めて伝えようとする自分の気持ちがあるからですね。このようなとても不安定な気持ちは、この時代の一つの症状に他なりません。どの情緒にも還元できない曖昧なものがどんどん膨らんでいったことは、この時代の文法を語っていると思います。
ですから、文学研究者のやらなければならないことは、一つ一つの言葉の形、言葉の表情を読むこと、そして、その意味ではなく、言葉に潜む時代の文脈を捉えることだと思います。

The post 言葉は躍動し、時代はますます文学的になっている 王欽准教授インタビュー first appeared on 東大新聞オンライン.