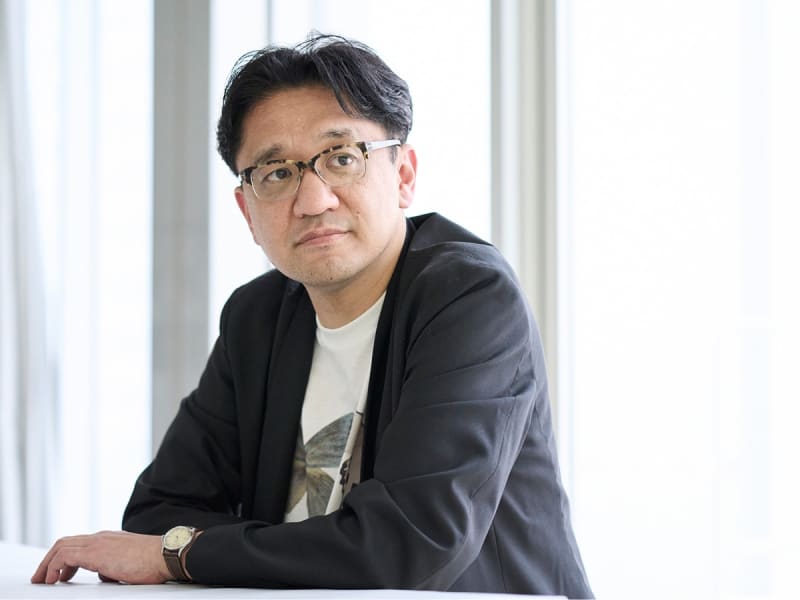
独自の世界観を構築した『人数の町』(20)で、鮮烈なデビューを飾った荒木伸二監督。待望の第二作目『ペナルティループ』がいよいよ公開される。タイトル通り“タイムループもの”である本作は、日本映画らしからぬソリッドな世界が展開。まるでA24のラインナップのような、エッジの効いた作品に仕上がっている。荒木監督はいかにしてこの世界を築き上げたのか? 話を伺った。
『ペナルティループ』あらすじ
おはようございます。6月6日、月曜日。晴れ。今日の花はアイリス。花言葉は「希望」です。――岩森淳(若葉竜也)が朝6時に目覚めると、時計からいつもの声が聞こえてくる。岩森は身支度をして家を出て、最愛の恋人・砂原唯(山下リオ)を殺めた溝口登(伊勢谷友介)を殺害し、疲労困憊で眠りにつく。翌朝目覚めると周囲の様子は昨日のままで、溝口もなぜか生きている。そしてまた今日も、岩森は復讐を繰り返していく――。
自分が観たいものを撮っている
Q:長編2作目ですが、前作と比べて慣れた部分はありましたか。
荒木:ないですね。映画作りは冒険なんで慣れちゃダメだと思います(笑)。前作の反省から修正した部分はもちろんありましたが、修正して改善してよりよいものにするなんて、映画に対して失礼な考え方だと思います。スポーツじゃないんだから。新たな冒険を設定して、どうしたらいいのか答えが見つからず悶え苦しみ、有能な仲間たちに助けてもらいながら、最後は自分で決めて進む。それだけです。

『ペナルティループ』©2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS
Q:撮影や編集などメインスタッフが変わっているにも関わらず、前作に続き自身の世界観を確立出来ていることに驚きました。
荒木:褒め言葉として受け取りましょう。ありがとうございます。劇作家(映画監督・CMディレクター)の山内ケンジさんからも「まさかカメラマンが違うとは」と言われました。別にコントロールマニア的に全てを指定している訳ではないですよ。寧ろ、それぞれのスタッフに才能を発揮してもらって頷いているだけです。カメラマンは『人数の町』の後『ドライブ・マイ・カー』(21)でカンヌと世界を制してしまった四宮秀俊さんから、『夜を走る』(22)で見つけた大変意気のいい若手、と言ってもキャリアは結構あるので業界の大先輩にはなるのですが、渡邉寿岳さんに代わりました。僕も寿岳さんも別に前作に似せようとしているわけではなく、一緒にカット割りをしながら、互いが直感的に良いと思うものを撮っているだけです。
編集は、以前『星の子』(20)を観て「めちゃくちゃ上手いな」と思った早野亮さんにお願いしました。編集室はまるで飛行機のファーストクラスに乗っているような感覚で、席に座って欲しいものを口にすれば出てくる、夢のような時間でしたね。だからこちらも無理にコントロールしているわけではない。音楽も渡邊琢磨さんから渡邊崇さんに変わったし、変わってないのは美術の杉本亮さんだけだと思います。
片手にSF、もう片方に社会性
Q:前作と今作に共通するSFの世界観に引き込まれますが、ご自身の中で意識されているものはありますか。
荒木:僕は70年生まれで、7歳のときに『未知との遭遇』(77)と『スター・ウォーズ』(77)に出会ってますから(笑)。60年代の熱狂が完全に終わっていた時代では、UFOとか「ムー」とか、そういう怪しげなものも含めた全てがSFだった気がします。SF的なCGや仕掛けがすごく好きなわけではなく、考えを解放する場所としての“未来”や“装置”などに惹かれるのでしょうね。僕の世代だとそれが最初にセットされているような感覚もあります。勉強でもずっと理数系の方が好きでしたし、文学的なことよりも数学的なものに興味があった。「未来はどうなっていくのだろう」と今もまだ考えていますね。

『ペナルティループ』©2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS
Q:日本映画でこういった世界観を確立するのは難しいと思いますが、制作にあたり気をつけていることはありますか。
荒木:片手にSFを持っているので、もう一方では社会性みたいなものを持っているつもりです。“LGBTQ”、“ハラスメント”、“反戦”などを羅列してトピックとして捉えるのではなく、それが自分の人生や価値観にどう絡んでくるか、そういう視点を求めています。SF、社会性と両手にそれぞれ持っているので、トピックとして単体で扱う余裕もないんです。海外はそこが上手ですよね。むしろそれ無しには製作のGOが出ない感じすらある。一方で邦画が言うエンタメって王道という名の使い古された感動話が好きだから、社会性を扱っているようでそれが全く表現に結びついていない。何の問題を描いても、同じような内容で問題がすげ替わっているだけな感じがします。
また邦画全般について、そもそも「そのルックでいいの?」という感じもありますよね。たとえドローンを使って豪華に見せたとしても、とにかくダサい。簡単にいうと、例えばNetflixで流すのにそのルックはないだろうと。誰もが映像を撮れる時代だからこそ、“プロが撮った映像”というものをそれぞれ意識する必要があるのではないでしょうか。
Q:本作を観ている時はエンターテインメントとして堪能しているのですが、観終わったあとにじわじわと社会性が湧き上がってくる感覚がありました。
荒木:「この映画ではこの社会問題を扱います」と言われると、その問題について考えている人しか観にいかない。その問題から逃げたい人は観に行かないですよね。政治的といわれる邦画のほとんどが社会の機能の中では全く政治性を発揮していないと思います。そこは仕掛けを考えないと。それでいうと、『TAR』(22)で主人公を女性にしているところなんかは本当に巧妙で、見習う必要があると思います。
キャストやスタッフからのアイデアを使い尽くす
Q:脚本はご自身で書かれたものに対して、プロデューサー、助監督、主演の若葉さんを交えて作り上げたそうですが、脚本作りはいかがでしたか。
荒木:広告では考えたアイデアに対して何かを言われる場合、ほぼ絶対アイデアにとって良くないこと言われるんです(笑)。だから『人数の町』で初めて脚本の打ち合わせをするってなったときにすごく恐怖がありました。いろいろ言われて「僕の考えた大事なお話がこんなふうになっちゃうの?」ってなるんじゃないかって(笑)。でも『人数の町』での作業を経て、少しでも面白いものになるようにと皆が意見を言ってくれていることが分かった。意見を言うだけじゃなくてアイデアを出してくれることが分かった。で、たとえそれを採用しなかったとしても誰も文句を言わない。監督が自由に取捨選択できるんです。それってつまり脳みそを何個も借りられるってことだから、使わない手はないですよね。自分一人の脳みそなんて性能はたかが知れてますから。だからどんどん言ってもらう。で、その際に人に言われたアイデアを自分が採用しないとき、自分の境界線っていうか輪郭みたいなものが、より明らかになっていくんです。
また、今回の話は“無理ゲー”すぎて解くのに結構時間が掛かり(笑)、前回よりもかなり稿を重ねました。撮影の3〜4ヶ月前に、長い打ち合わせを繰り返しやりました。プロデューサーと助監督がそこに居るので、実際にどう撮影するかも想定しながら話せるので、とても能率的でした。前回は開発と制作が段階的に進んでいく感じでしたが、今回は開発をしつつ制作準備も進めるような感じでした。物理的に撮れる方法も想定しながら脚本を詰めることによって、欠番や変更を最小限に留めることが出来たのです。
Q:工場や水耕栽培の施設など、シンプルな美術設計が説得力ある世界を作っていますが、どのようにオーダーされているのでしょうか。
荒木:最初はもっと鈍臭い工場を考えていて、ベルトコンベアが欲しかったのですが、ベルトコンベアのある工場が意外と無い。そんな中、美術の杉本さんが「別の撮影で水耕栽培を撮影したんだけど、あれカッコいいよ」と教えてくれたんです。ネットで見てすぐに飛びつきましたね。もしベルトコンベアにこだわって工場が見つからなかったら一体どうしていたのかと(笑)。そうやってスタッフ一人一人が知恵を絞っていろいろ出してくれるので、とても助かっています。
肌触りみたいなところでいうと、すごくピカピカしたものよりも少しアナログ感が残ったものが好きです。唯一、前回から引き続きの杉本さんがそこを読み取ってくれてどんどん提案してくれます。その点については、引き続き同じスタッフでやるのもいいですよね。

『ペナルティループ』©2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS
Q:ボウリング場のシーンが個人的にとても好きでしたが、そもそもなぜボウリング場になったのでしょうか。
荒木:あのシーンは岩森と溝口の関係性が大きく変わってくるところで、同じループの中に囚われている二人の人間として、関係性が生まれ出す。なぜかボウリング場にしてみました(笑)。ボウリングって面白いモチーフだなとずっと思っていて、そもそも同じ方向を向いてやるスポーツっていうのが変ですよね。なぜ向かい合わないんだろうなと(笑)。『人数の町』でもボウリング場のシーンがあるのですが、「ツナギとボウリング場がそんなに好きなの?」って言われると困ります。気づいたらそうなってました。偶然です(笑)。
筑波山の麓にあるボウリング場で撮影させていただいたのですが、プロボウラーだったご主人がやっているかなり年季の入ったところでした。大掛かりな美術が組めない中で、光と色を駆使しながら作り込んでいき、照明の水瀬さんが「今ハリウッドではコレですよ!」と、見たことないようなマシンを使って照明の色を何パターンも見せてくれました。実際のあの場所を見たら驚くと思います。撮影時間的にもギリギリでアクションの難易度も高く、スタッフたちがテキパキやってくれたおかげで何とか乗り切りました。本当によく撮ったなって感じです。
あのシーンでは、岩森がボウリング球に勝手に動かされる動きがあったのですが、若葉くんからは「これ絶対“がーまるちょば”みたいになるよ」と言われしまい、「“がーまるちょば”になるのは嫌だな…」と思っていたら、若葉くんが色んな動きを提案してくれて、どんどん可能性を広げてくれた。撮っていて興奮しましたね。そうやって色んな人のアイデアが集まって、何とか作り上げることが出来たシーンです。
約2年ぶりの映画出演、伊勢谷友介
Q:若葉さん、伊勢谷さんの組合せが絶妙でした。キャスティングの経緯を教えてください。
荒木:基本、アテガキはしないのですが、“岩森”という漢字が“若葉”に形が似ているように、執筆の途中から完全に若葉さんじゃなきゃと思ってました。オファーした若葉さんが乗り気になってくれて、岩森役は若葉さんに決まると、プロデューサーから溝口役として伊勢谷さんを提案されました。想定外だったし、最初は確信が無かったです。会ってみようかって話になって、もしかしたら落ち込んでブクブクに太った伊勢谷友介に会えるかもと期待していたのですが、逆に身体がメッチャ締まっているんです(笑)。皆の前でも明るく振る舞っているし、想像していたのと違っていました。しかし、そんな彼の中にも久しぶりの現場であることの、戸惑いや恐れみたいなものが感じられて、その繊細な部分をどうにか映像に落とし込めないかと考えました。休む直前に出ていた映画は大作ばかりで、分かりやすい大きな演技を要求されるものが多く、説明台詞も彼に集中していました。それも含めて、今回の手作りで比較的コンパクトな映画で求められることに最初は少し戸惑っている感じがありました。それをかなり初期から察知していた若葉さんが上手いこと伊勢谷さんを乗せてくれたことは大きいですね。若葉さんの助けで役が出来上がっていく感じでした。

『ペナルティループ』©2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS
伊勢谷さんは絶対的なフラがあります。カメラを前にすると、すごく華がある。それに加えて、今回のことでいろいろ傷ついて様々な経験をしたことから、“深み”が出てきたんじゃないでしょうか。彼の背中がとてもいいですよね、今回。
Q:今後はどのような作品を作っていきたいですか。
荒木:またオリジナルを書きたいと思っていますが、先日ある監督と話したら「よくそんな面倒くさいことやるね」と言われました(笑)。彼曰く「自分だったら、面白い話を思いついたらそれにそっくりな話を探す。それに乗っかればいいし、そこに答えまで書いてある。思いついたことから起承転結作るのは大変でしょ」と。それを聞いてますますオリジナルで作ろうと思いましたね(笑)。でも後になって、原作モノも良いなと思うかもしれませんが(笑)。漫画はすでに絵があるからすごく難しいと思います。小説だと面白いものが出来るかもしれない。特に海外の小説なんかいいと思います。
オリジナルの場合はどこまでも自由で、歩ける場所が広い。あんなのはどうか、こんなのはどうかと、煮たり焼いたりしながら毎日考えています。3作目が出来たらまたぜひ観てください。
『ペナルティループ』を今すぐ予約する↓

監督/脚本:荒木伸二
1970年生まれ、東京都出身。東京大学教養学部表象文化論学科卒。CMプランナー、クリエイティブ・ディレクターとして数々のCM、MVを手掛ける。その傍らシナリオを本格的に学び、テレビ朝日21世紀シナリオ大賞・優秀賞、シナリオS1グランプリ・奨励賞、伊参映画祭シナリオ大賞・スタッフ賞、MBSラジオ大賞・優秀賞など受賞。17年、木下グループ新人監督賞で準グランプリを受賞したオリジナル脚本『人数の町』(20/主演:中村倫也)で長編映画デビュー。同作は新藤兼人賞の最終選考作品に選出され、モスクワ国際映画祭、バンクーバー国際映画祭で招待上映を経て、シカゴで開かれたアジアンポップアップシネマ映画祭のオープニング作品に選ばれた。本作で2作目となる長編演出に挑む。
取材・文: 香田史生
CINEMOREの編集部員兼ライター。映画のめざめは『グーニーズ』と『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』。最近のお気に入りは、黒澤明や小津安二郎など4Kデジタルリマスターのクラシック作品。
撮影:青木一成
『ペナルティループ』
新宿武蔵野館、池袋シネマ・ロサほか全国公開中
配給:キノフィルムズ
©2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS
