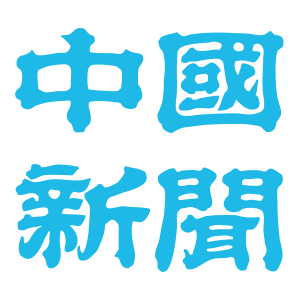朝5時過ぎ。広島市安佐北区の大学4年、政井和花(のどか)さん(23)は、母が運転する車で薄暗い道を最寄り駅へと急ぐ。「行ってらっしゃい」の声に見送られ、始発に乗り込むとほっと一息つく。
広島県呉市にある広島文化学園大までは片道2時間。毎日の通学は大変だが、目標ははっきり見えている。養護教諭か看護師になって、心や体に不調を抱える子どもをケアすること。必要な知識は膨大で、病院や介護施設での実習も増えた。目の回るような毎日は、生きていることを実感させてくれる。
あの頃は違った。高1を3年間やった。「私、学校に行けない時期があったんです」
始まりは中学1年の1学期だった。勉強が嫌なんじゃない。いじめられているわけでもない。「行かなくちゃ」と思っているのに体が動かない。どうすればいいの? 母は毎朝、ベッドから引きずり出そうとした。こんなにつらいのに、誰も分かってくれないなんて。いつも思っていた。「もう消えてしまいたい」
朝、ベッドから出られない。何かが体にずっしりのっかっている感じ。全身が重くて、だるくて…。和花さん(23)はかつて、そんな症状に苦しめられていた。
変調が現れたのは、中学1年の中間試験の直後だった。「私、完璧主義者なんです。全力投球して、燃え尽きたみたいで」。当時は両親、弟の4人暮らし。母の真由美さん(50)は、動揺を隠さなかった。「なんで行きたくないん?」「どうするつもりなん?」。何度も問い詰められた。
違うよ。行きたいのに行けないの―。そう思うのに言葉にならず、涙があふれるばかり。すると母は馬乗りになり、布団を引き剝がした。車に押し込まれ、学校に連れて行かれる。迎えに出てきた担任や友人の前で車から引きずり出され、特別教室へ。他にも生徒が2人ほどいたが、声を交わした記憶はない。ただただ、毎日が苦痛だった。
「今思えば母も必死だったんですよね」。底抜けに明るい人なのに当時はよく泣いていた。原因も分からないのに、人から良いと聞けば、高額な漢方薬やビタミン剤を次々に飲ませようとした。
トラック運転手の父が帰ってくるのは週1、2日。母は一人で悩んでいたに違いない。ある時、こう漏らした。「子育て、失敗したな」。そんな思いをさせたのは私なんだと、また自分を責めた。
何とか仕切り直したいと、高校は地元から遠く離れた私立校を選んだ。母も賛成してくれた。その頃だ。テレビで起立性調節障害という言葉を知った。朝は不調で起きられず夜は眠れない、思春期特有の症状らしい。「絶対これだ、と思って」。母に付き添ってもらい、病院へ。思った通りの診断が出た。
ただ原因を知り、ほっとしたのはつかの間だった。処方された薬の効果は感じられず、つらい朝が続いた。その後も登校できず、焦りが募った。「今日は行けそう」と言えば、高速を使ってでも車で送ってくれる母に申し訳なくて、ツイッターで誰にともなくつぶやいた。「逃げ出したい」「もう頑張れない」
転機は翌春。通信制の高校に移り、3度目の1年生を送ることにしたのだ。そこには、見守ってくれる教員や同じ苦しみを知る生徒がいた。登校日を週1日にしたのも良かったのか、学校に行けるようになった。少しずつ自信がつくと、ある思いが芽生えた。「自分と同じような子を支える仕事に就きたい」。3年からは週5日登校し、進学を果たした。
昔を思い返すと、今も胸の奥がきゅっとなる。布団を引き剥がす母の姿。「私を分かってくれなかった頃の母をまだ許せていないのかも」という思いがよぎる。朝の体調も万全とは言い切れない。大事な模試や実習の前夜は不安で徹夜することも少なくない。
それでも、和花さんは自分の変化を実感している。不登校だった頃を「まあ、いいか」と思えるようになった。当時の母の苦しみを少しだけ理解できるようにも。「母は最悪な時を一緒に乗り越えてくれた同志だとも思うんです」
子どもの痛みに寄り添える存在になれたなら、つらい経験が「無駄」ではなくなるかもしれない。これから卒業に向けては正念場の1年だ。卒論に教員採用試験、看護師の国家試験もある。今日も母の握ってくれたむすびを持って、大学へ向かう。