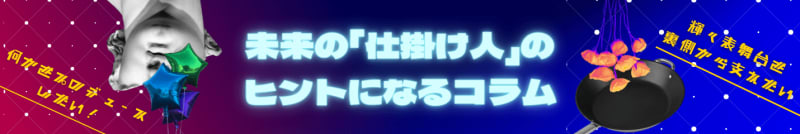ドラマや映画などの制作に長年携わってきた読書家プロデューサー・藤原 努による、本を主軸としたカルチャーコラム。幅広い読書遍歴を樹形図のように辿って本を紹介しながら、自身の思うところを綴ります。
母親にこうあって欲しいなんて思わない
僕は生まれつきの運動音痴なのですが、幼い頃から夏の高校野球の季節が近づくとその時だけは胸が疼きます。地方予選から全国大会決勝までトーナメントで一回負けたら終わりと言うシステムが、自分のようなゴロもフライもまず捕れない男でさえも熱くするのです。
時はさかのぼりますが、僕が高校3年生の夏、住んでいた京都の代表は、京都商業高校と言う当時の甲子園常連の私学でした。下馬評は高くなく、代表になった時は京都市民も甲子園での活躍をあまり期待していない空気を肌で感じていましたが、結果的には全国大会で準優勝を果たすことになります。僕の同い年の選手として、兵庫の報徳学園に金村(ここが優勝)、名古屋電気に工藤、一年下に当時は東東京代表だった早稲田実業に荒木大輔がいた年です。決勝で報徳と当たるまで、名電にも早実にも当たることはなく、くじ運に恵まれたなどと大会後に陰口を叩かれたりもしましたが、準決勝で熊本の鎮西高校に1−0で勝った時は、四条河原町などで京都新聞の号外が出る騒ぎになりました。
ここで急にプライベートな話になってしまうのですが、僕が当時交際していた同級生の女性が、当時京商の投手だった井口くんと言う人と中学の同級生だったと言うのもあって、大喜びして甲子園決勝を応援しに行くと言い出しました。僕は恥ずかし気もなくそのことで井口に対する嫉妬の炎を燃やしてひどい言葉を彼女にぶつけてしまったのですが、それも今ではいい思い出です。
そんな時代を経て大人になれば高校野球のことなんて気にならなくなるだろうと思いきや、60歳になった今もやっぱり燃え上がってしまうのです。
僕の場合、全都道府県どこの代表でも、基本的には公立高校を応援するスタンスです。強い私学を中心に、全国の中学校から有望な選手をスカウトしたりしているらしい、と言うのが、夏の高校野球=ふるさと応援主義、だと捉えている自分のような人間にはどうしても邪道に思えてしまうからです。
前置きが長くなりましたが、そんな僕が今回読んだ本が、早見和真『アルプス席の母』でした。このお話、神奈川の中学で投手として鳴らした少年が、大阪の新興の野球私学にスカウトされ、全寮制のその高校で野球留学することになり、その母も一緒に大阪に移り住むことになるところから始まるもので、僕の甲子園美学からすると受けつけないのですが、朝日新聞で藤田香織さんと言う野球に何の興味もないと言う書評家の人が、何だか絶賛していてそんなに言うなら読んでみようかと思いました。
一読、よくできた胸アツの小説だった、と言いたいところなのですが、僕にはどうしても違和感の拭えない小説でした。内容も構成もそこからの抜け感も実にちゃんとした小説なのですが、これは一体何だろう、とずっと考え、この母と息子の人間像そのものにあまり共感できない僕のヘタレ感性のせいだと気づきました。
中学の時からシニアリーグで活躍しているこの息子は、父親を早くに事故で亡くしているのですが、ダントツの投手力で将来はプロ野球選手になりたいと考えています。この少年はもうこの時点である意味大人の感覚を持っており、自分の実力とかについてもカン違いしないし、自分のために生きてくれていると言っても過言ではない母親を物凄く大切に思っている若者であることが伝わってきます。
でその“女手ひとつの”母が、この小説の主人公なのですが、息子へのふるまいや考え方がなんだか、母、ではなく、彼女、のように見えてしまうのです。具体的な描写については、これからお読みになる方のために省きますが、もう息子のためを思ってそれだけのために生きているような感じが、僕にはもう暑苦しくてしかたがありませんでした。もちろん世の母親にこういう人がいっぱいいるであろうことは、子の親になったことのない僕でも知っていますが、仮にも小説の主人公である以上、もう少し息子のことを離れて自分自身のために生きる側面もある人であって欲しい、と僕などは思ってしまうのです。つまりこれは子離れできない逆マザコンの母、の話ではないかと。
この母親は、周囲の人への対応とかも含め、社会的常識もあってきちんとしており、高校の監督の不正裏金疑惑の時には英断的行動もしてしまう(この小説の白眉はこのくだりだと思います)ような人ではあるのですが、息子のためにどうすることが正解なのか、それしか考えてない人であるのが、僕の違和感の最大の理由です。
ある意味、著者が、野球少年の息子を持つ母親に、こうであって欲しいという願望をそこに込めて書いたのではないかとさえ考えずにおれませんでした。
そうでなくては紆余曲折あっても結果的にこんなゴールを小説の最後に持っていくことはないのではないか。
その意味でこの本を読んだ人の感想をいろいろ聞いてみたいです。
母の子どもに対する思い、と言う側面で、これとは全く違う味わいを感じたのが、角田光代の新作『方舟を燃やす』でした。
こちらは自分の産んだ子の健康と幸せを思うばかりに、たまたま目の前に現れた信頼できると思えるカリスマ的大人の意見に影響されて、一種の陰謀論に囚われ子どもが幼いうちに受けるのが一般的と言われるワクチン接種をさせなかったりする母親が主人公の一人です。客観的に見るとかなり歪な過保護になり過ぎて、夫からも子どもからもやがては愛想を尽かされる展開になっていくのですが、僕にはこの母親のありようがどうしようもなく切なく感じられ、なんでそんなことをしてしまうんだ、と言う思いも抱きつつ、この小説にとっては物凄くいい読者のまま突っ走りました。
ネタバレにはならないと思うので加えて言うと、この小説はハッピーエンドともバッドエンドともあるいはビターエンドとさえ言えない結末を迎えます。角田光代と言う人はやはり熟練した作家なのだなあと感じました。
こう言う最悪の事態だけは避けて欲しいけどそういう終わり方なの!?とか、あるいはこうなって欲しい!などと読者の多くが抱くであろう願望も、どちらの想像も叶えない。
でもそれでこそが予定調和でない小説のリアルでもあると僕は思いました。
ちなみに僕自身の母親は、自分が高校2年生の時に病死しました。親族などからは、自分が母親っ子のように見られがちだったことへの反発心のようなものもあって、母が亡くなった翌日から始まった高校の期末試験も欠席せずに全部受け、その後の、冒頭の高校野球騒ぎのような青春も経て、母の像は僕の中でどんどん過去のものになり風化していきました。存外母と子どもの関係というものもそんなものではないのか、という思いが僕にはあります。
その意味で、男の子はつい好きな女の子に母親の像を追い求める、的な内容を描きがちな映画監督・大林宣彦が僕は苦手なのですが、それはまた別の機会に。
info:ホンシェルジュTwitter
comment:#ダメ業界人の戯れ言