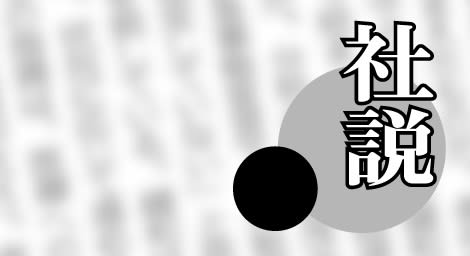政府は4月末が期限だったガソリン補助制度をさらに延長した。これまで4・3兆円もの補助金が投じられ、延長は何と7回目になる。
「一時的な緊急避難措置」とされながら、既に2年以上が過ぎている。効果にも疑問点が多い政策を、いつまで続けるのだろうか。
温暖化防止の視点からみると、化石燃料の使用を減らすことこそ喫緊の課題だろう。補助制度はそもそも脱炭素化の流れに逆行しているにもかかわらず、今回の延長には期限も付けられなかった。国民ではなく、石油元売り会社に補助金を渡し続ける手法にも疑念が残る。
歴史的円安が招いた物価高への対策は必要だ。しかし、一方で化石燃料の使用を減らしていく社会の実現には政府の思い切った政策誘導も欠かせない。出口戦略を示さない政府の対応は極めて場当たり的と言わざるを得ない。
資源エネルギー庁によるとレギュラーガソリンの全国平均小売価格は4月30日現在で174・7円。石油元売り各社に渡る補助金は1リットル当たり30・1円に膨れ上がり、これがなければガソリン価格は204円台のはずだという。
うのみにはできない。元売り会社に補助金を出して卸売価格を抑えたところで、小売価格を決めるのはガソリンスタンドだ。実際の値下げ効果には不確かな面も多く、会計検査院が「補助分が小売価格に反映されていない可能性がある」と指摘していることも見過ごせない。
補助金ではなく小売価格に直接反映されるトリガー条項の撤廃も議論になった。3カ月連続で1リットル当たり160円を超えると、揮発油税に上乗せ徴収する25円分の課税を一時停止させる仕組みだ。
東日本大震災の復興財源に充てるなどの理由で、条項が凍結されているに過ぎない。しかし、岸田文雄首相の国会対応は「協議する」と言うばかりで、まるでやる気が感じられなかった。国民から徴収する税源をいつまでも見直さず、補助金でごまかすような態度は不誠実過ぎよう。
自民党は、元売り各社が名を連ねる石油連盟から年5千万円の政治献金を受け続けている。「政治とカネ」の問題が厳しく問われる今、巨額の補助金政策を続けることがふさわしいとも思えない。
電気・ガスへの補助制度は今月使用分で終了する。液化天然ガスや石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵攻による価格高騰前の水準まで低下したのが理由とされている。
しかし、一時1バレル120ドル台に高騰した原油価格も80ドル前後で推移している。最近の高値の原因は円安であり、ガソリンだけ補助を続ける明確な必要性は感じない。
岸田政権の支持率は低迷している。政権の浮揚を目的にした人気取りのために、補助制度を延長したのだとすれば許される話ではあるまい。
燃料費の高騰が与える影響は大きい。補助は必要だとしても、低所得世帯などに絞った形に切り替えるべきだ。国民の暮らしを支える手法は見直す時期に来ている。