⽝は胃腸などの消化器に何らかの不調があると、さまざまな症状があらわれ、病院での治療が必要となる場合もあります。元気で⾷欲がある場合は、しばらく⾃宅で様⼦をみてもよいでしょう。ただし、元気で食欲があっても3日以上下痢が続く場合は動物病院に相談しましょう。今回は、⽝が胃腸などに不調をきたす原因と、胃腸ケアに有効な⾷事管理法や療法⾷について解説します。
犬が胃腸などの消化器に不調をきたす原因とは

胃や腸などの「消化器」と呼ばれる器官は、食物を食べて消化吸収し、不必要なものを排泄する働きをしている器官です。体外から食物という物質を取り込む場所ですから、微生物など危険なものが入り込まないように待ち構える免疫の最前線でもあります。
そのため、そこに何かしらの問題があると、下痢や便秘、嘔吐などのさまざまな症状が見られます。消化器疾患は、例えば下痢だとしてもたかが下痢とあなどってはいけません。自然と治ることも多いのですが、体重減少を引き起こしたり、命に関わる重篤な疾患によって引き起こされることもあります。このような症状があらわれたら早めに動物病院を受診しましょう。
・胃腸に不調をきたす原因
犬が胃腸に不調をきたす原因はさまざまです。寄生虫やウイルス、細菌感染による場合も考えられますし、急にドッグフードを替えたり、食べすぎたりしても消化不良が起こり、下痢や嘔吐などの症状が見られます。そのほか、赤ちゃんやほかの動物が家族に加わる、引っ越しをしたなどの環境の変化によるストレスも原因の一つです。
胃腸ケアには食事管理は欠かせない
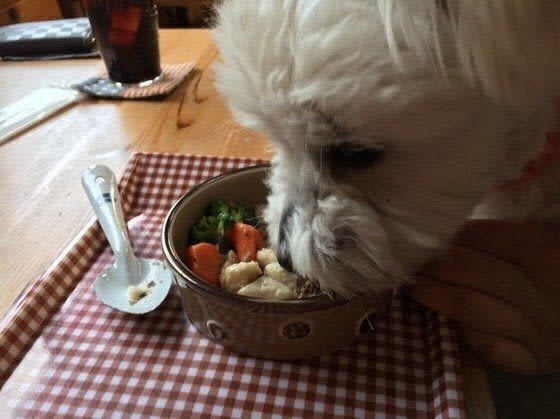
まず、愛犬に下痢や嘔吐などの症状が見られたら、動物病院を受診しましょう。獣医師の指導のもと治療を進めていきます。
元気や⾷欲があって3⽇以内に下痢がおさまっているような場合は、⾃宅でしばらく様⼦をみるケースもあります。その場合、お腹の負担を減らすために、⾷事管理も重要な対策になることが多いようです。
では、どのように⾷事管理をするのがいいのでしょうか。
・消化のよい食事を与える
まず第一に考えるべきなのが消化がよいものを与えることです。消化不良を起こしてしまっては必要な栄養素を吸収することができません。消化がよく、少量で栄養やエネルギーを満たすことができるフードが理想的です。そのためには適度に脂肪が含まれているフードを選ぶといいでしょう。脂肪が多いとお腹に負担がかかるように思われるかもしれませんが、犬はもともと脂肪の消化吸収は得意な動物ですから、「すい炎」など特定の病気でなければ、特に脂肪を減らす必要はありません。
・動物病院で治療に使われる食事
激しい下痢・血の混じった便がみられる場合や、下痢だけでなく元気や食欲がない場合、元気や食欲があっても下痢が3日以上続く場合などは、すぐ獣医師に相談しましょう。動物病院では下痢を治療するために食事指導をしてくたり、療法食をすすめてくれたりすることがあります。
療法食とは?
療法食とは、特定の病気に対応するために、栄養バランスが特別に調整されたドッグフードのことです。人が心臓病になったら塩分控えめの食事をとるのと同じように、消化器系の病気以外にも食事制限が必要となる犬の病気は数多くあります。
とはいえ前述した通り、こうした病気に合わせた犬の食事を、飼い主さんが毎日自分で作るのはほぼ不可能といえるでしょう。
そこで、獣医師による専門的なアドバイスや処方に従って与える、療法食が作られるようになったのです。現在では、さまざまな病気の治療に対応した療法食が、さまざまなメーカーから開発されています。
療法食は獣医師の指導に従って与えましょう。また、継続的に食べる場合も状態が変わっていることもあるので、毎回、獣医師の判断を仰ぐことが必要です。
・アレルギー対応の食事
下痢の原因が食物アレルギーであることもあります。特に、下痢が長く続く場合は要注意です。食物アレルギーは食べ物に含まれるアレルゲンによって症状が引き起こされます。腸は食べ物が体の中に入る入口であるため、食べ物に含まれるアレルゲンと最初に接触する腸でアレルギー反応が起こって下痢などの消化器症状が出てしまうのです。⾷物アレルギーの治療は、アレルゲンを⾷事から排除することです。⾷物アレルギーはフードでコントロールすることができますので、獣医師の指示によく従って、指示されたフード以外は与えないようにしましょう。
・高食物繊維食
慢性腸炎やストレスによる下痢など、高食物繊維食が推奨されるケースもあります。この場合、やみくもに食物繊維を与えるのではなく、その個体に合った食物繊維の種類を考慮することが大切です。消化器疾患の種類によって適切な繊維が異なりますので、獣医師はそれらを使い分けています。
・低脂肪食
低脂肪⾷とは、カロリーに対する脂肪の量が少ない⾷事のことを意味しています。消化器の病気でも「すい炎」のように脂肪の制限が必要な病気もあります。この場合は、低脂肪⾷が推奨されているので混同しないようにしてください。
病気の時の食事管理は獣医師の指導に従って、⾏うことが⼤切です。もしも⾷事の説明が特に無かった場合、獣医師に聞いてみるといいでしょう。きっと詳しく教えてもらえると思います。
犬の消化器病~症状と対策・食事療法
監修/徳本一義先生(有限会社ハーモニー代表取締役)
