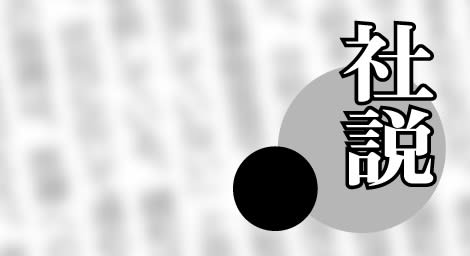
空き家の数が昨年10月時点で全国で900万戸に上ったという。総務省の住宅・土地統計調査(速報値)によれば5年前の前回調査から51万戸増え、過去最多になった。
空き家は景観悪化のほか、地域の治安にも影響することが指摘されてきた。加えて、災害時のリスクが1月の能登半島地震で明らかになった。倒壊して被災者の救助はもちろん、復旧・復興の妨げにもなることだ。
空き家が社会問題だという認識は広がってきた。カフェや観光交流施設に改修して活用する動きも地域にあるものの、増加のペースには追い付いていないのが現状だ。
空き家対策特別措置法に基づき、自治体が解体を代執行するケースもある。しかし、それぞれに放置された事情や状態が異なり、行政が立ち入りにくい面もある。
さまざまなケースに対応できるよう法整備を進めていかねばなるまい。とはいえ住宅は個人の財産である。空き家を生み出さない対策や処分などの責任もあると自覚することが所有者には求められる。
住宅総数は6502万戸。空き家が占める割合(空き家率)は過去最高の13・8%という。約7戸に1戸は住む人がいないのだ。
広島県に空き家は23万1千戸あり、割合は15・8%だった。中国地方の他県でも山口19・4%、島根17・0%など空き家率は増えていた。所有者特定の難しさなどから解体や活用が進まぬ状況だ。
とはいえ倒壊の危険性やさまざまなリスクが潜むほか、まちづくりの支障となる空き家。代執行によって解体を進める自治体もある。
福山市は今年2月、代執行による解体に着手した。同市では2例目。約2年前、環境や景観に悪影響のある特定空き家に指定し、所有者に指導や勧告をしていた。市内にはこの家屋を含め、特定空き家が64棟あるという。
だが公費で解体する代執行には費用回収の問題もあり、進みにくいのが現状だ。
政府は昨年12月、改正空き家対策特別措置法を施行し、対策を強化した。適切に手入れしなければ、固定資産税の優遇措置を解除する空き家の範囲を広げた。
今年4月には所有者が不明な土地の解消を目的とした相続登記の申請義務化も始まった。それでも空き家は一層増えていくと懸念される。
人口減少のほか、所有者の高齢化が進むためだ。施設入居や都市への転居などが進むことで空き家は増えそうだ。
空き家需要のある都市部では、情報を提供する「空き家バンク」などで利活用を一層図りたい。一方で、過疎化の進む地方では空き家を撤去し、宅地を増やすべきでないと指摘する専門家もいる。
行政には、空き家それぞれの実情に応じて優先順位を付け、法的な措置を取ることが求められるだろう。
所有者は管理や撤去について自治体窓口に相談もできるはずだ。相続などを家族らと対話することが欠かせない。お盆などに帰省した際、話し合う機会を持っておきたい。
