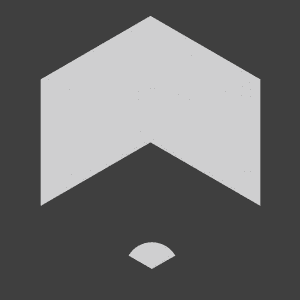今年の五月祭のテーマは「しずく融け合う、水模様」。人と人が出会う祭りを水面になぞらえたものだ。普段の生活で何気なく使っている水について、われわれは正しい理解ができているのだろうか。水の全てを扱う学問「水文学(すいもんがく)」の第一人者であり、「水のノーベル賞」とも言われるストックホルム水大賞の今年の受賞者で、春の紫綬褒章も受賞した沖大幹教授(東大大学院工学系研究科)は、水について表層的な捉え方をするのではなく、より深く理解してほしいと語る。水文学の重要性や学生時代、五月祭の思い出を聞いた。(取材・石橋咲)

水を究める「水文学」 水の循環はどう変化するか
━━水文学はどのような領域を扱う学問なのでしょうか
地球上の水循環、つまり、雨が降って地面に浸(し)み込んだり川に流れたり地下水になったりして、また海に戻っていくという水の循環全体を扱います。ある地域で雨が山の斜面にどう浸み込むかとか、浸み込んだ地下水がどんなふうに、何年かけて地表に出てくるのかを研究している人もいますし、洪水や渇水などへの応用研究をしている人もいます。地球物理学、自然地理学的な分野もあれば、化学的に水質を調べる研究、生物の水の利用を考える生物学的な研究、利用可能な水を増やす農学的・工学的な研究、さらには人間活動の影響や水を使う権利などを調べる人文社会学系の研究など、対象がとても幅広い分野です。つまり、水に関する森羅万象を扱うのが水文学です。
━━水文学者になった経緯や学生時代の思い出を教えてください
大学に入学した頃は科学史や科学哲学に興味があり、文系と理系の両方、あるいはその中間的な研究をしたいと思っていました。進振り(当時、現・進学選択制度)では、技術に基づきつつも社会のためになる学問を学びたいと工学部土木工学科(当時、現・社会基盤学科)に進学しました。土木工学科では、五月祭で「地下鉄乗り換え」という展示を行いました。乗る駅と降りる駅を入力すると経路が出力されるプログラムを同期の友人が組んだのです。東京の地図に地下鉄路線と主要乗換駅の模型を置き、パソコンをつないで経路が見えるようにして。今から40年ほど前の話で、当時のお客さんは「ふーん」という感じ。今では当たり前のようにアプリで検索できますが、なかなか先駆的だったと思います。普段は意識しない地下鉄の駅の位置関係が分かるのも面白かったです。
学部4年生に進級する際、研究室を選択する機会がありました。「人間活動のニュートンの法則を見つける」という先生の研究室で研究したかったのですが、定員よりも志望者の方が多く、選抜のじゃんけんに負けてしまって。セカンドベストだと考えた水文学の研究室に入りました。水文学は自然科学と社会との接点がある文理融合の学問で面白そうだと思いました。
卒論では、地域性豪雨をシミュレーションで再現しようと考えました。しかし、数値計算がなかなかうまく動かず、満足のいく結果が出なかったので、修士でもその研究を続けました。修士に進んでからは研究が面白くなってきました。当時はバブルの真っ最中だったので、民間企業に就職するのも魅力的だと思いましたし、あるいは官僚になって国を動かすのも面白そうだとかなり悩んだのですが、大学にしました。どの進路を選んでもうまくいけばやりがいがあるだろうと想像しましたが、うまくいかなかったときに大学が一番ましかなという消極的な決め方でした。
━━現在はどのような研究を行っていますか
地球規模でどのように水蒸気が移動して、どこでどのくらい雨が降って、どのくらい蒸発して、川にどのくらい流れて、人がどのくらい使って……。水循環がこれまでのところどのように変動して、また気候変動によって今後どう変わるかということを調べています。
日本の気象庁や各国の気象局が気温や湿度、風速の分布などあらゆるデータをリアルタイムで測定、公開しているので、そのデータを利用することができます。灌漑(かんがい)やダムなどの状況を調べるために統計データを集めたり、コミュニティーで共有されたデータを使ったりもします。インターネットがない頃は各国の河川の流量データも集積されていませんでしたが、ちょうど私が研究を始めた頃にデータを集めるセンターができて、そこのデータを使わせていただけるようになりました。
そのようにして得たデータについて、相関関係を抽出する統計的手法を用いたり、土地利用などを考慮し物理的概念を持った上でモデル化し、数値計算をしたりしています。同じデータを使っても、上手な人だと一瞬で結果が出せるのに下手な人は全く結果を出せなかったりするので、研究者間でスキルを磨き合い、皆が効率良くデータを扱えるようにノウハウを蓄積する必要があります。
フィールドワークも行います。例えばタイでは、10メートル程度のタワーを建てたり、通信用の鉄塔に測器を取り付けさせてもらったりして、耕作地の表面からの水の蒸発散量を計測しました。また、耕作地の増え過ぎによる河川流量の長期的な減少や、都市化により11年の大洪水で甚大な被害が出た実態の調査など、日本での研究だけでは分からない現象が理解できました。私の場合、直接的に論文という形にはなりにくいのですが、現場で何が起こっているのかを観察し着想を得て、数値シミュレーションに反映するのが非常に重要です。データだけを見ていても実感が湧かないですし、行ける機会があれば、さまざまな地域に調査に出かけたいと思っています。
━━研究のやりがいは何ですか
データ解析や数値計算によって仮説の裏付けが取れて、それを論文にして世に出し、伝えたいメッセージを伝えられた際にやりがいを感じます。2006年の『Science』に掲載された論文では、人間活動も含めたグローバルな水循環の数字入りの概念図を作りました。それがいろいろな教科書に引用されてうれしかったですね。また、2050年代に水不足で困る人の数を予測したのですが、予測が外れれば成功、裏を返せば「対策を取らなければいけない」というメッセージや、科学研究と社会とのインターフェースの重要性を伝えられたのが良かったと思っています。
言われたらなるほどと思うけれども、誰も気付いていない考え方って多いですよね。そのような論理をコロンブスの卵(誰でも思いつきそうなことでも、最初に考えたり行ったりするのは難しいということ)のように示すのも研究の楽しさです。

社会と水循環の相互作用を研究し、知見を社会に伝える
━━今年、「水のノーベル賞」と言われるストックホルム水大賞(水分野で世界最高峰とされる賞。学術研究だけでなく、政策・実践も対象業績に含む)の受賞者に選ばれました
最初は国際的な詐欺ではないかと疑いましたが(笑)。うれしかったですね。受賞前と後で言う話は変わりませんが、耳を傾けてもらえる機会が増えるだろうと思います。
━━一般向けに知識を伝えるために工夫していることはありますか
テレビや新聞の取材依頼が来たらできるだけ受けてお話をしています。本当は若い人に向けてYouTubeで3、4分の動画をたくさん出すという挑戦もしなければと考えていますが、面白くなければ誰も観ないですよね。不特定多数の人に情報を届ける方法は模索中です。
東大では今年から新入生向けにグリーントランスフォーメーション(GX)の教育動画を作成し公開しましたが、その動画の中でも話をしました。そういったコンテンツを通じて多くの人に関心を持ってもらい、社会と対話するのが役目だと思っています。
━━水文学に触れることの重要性を教えてください
水文学は多岐にわたる分野にまたがっていますが、高校までは物理、化学、生物、地学、地理というようにその分野が教科ごとに分かれています。しかも地学はほとんど習わない。地理でも水文学に近い内容はあまり扱いませんし、普通科高校ではエンジニアリングや農学も習わないですよね。普通に初等中等教育を受けていると習わない学問が世の中にはたくさんあり、そこにも学術的な面白さがあるという一面を水文学からご理解いただけると思います。
また、研究者でなくても、水についてまっとうな理解をしてほしいと考えています。日本は水が豊かだから水に困らないと思っている方も多いですが、水に困らないのは自然条件のおかげではなく、貯水池、水路、浄水場、水道管、下水道などのインフラストラクチャーを作り維持・管理してきたからです。今年1月に発生した能登半島地震の影響で大きな断水の被害が出たように、震災でそういった基盤が少しでも壊れると水に困る事態に陥ります。他にも、アフリカで水に困っている人がいるのは乾燥した地域だからというのは間違いで、開発の問題なのです。こうした実態を理解し、普段の水との付き合い方を考えてみてほしいと思います。
私たち水文学者が今考えていることが100年後も100%正しいかどうか、そもそも唯一の正しい答えがあるかどうかは分かりません。しかし専門家の見解を知って、自分はどの考えが正しいと思うかという思考まで突き詰めていくと楽しいと思います。水は単なる再生可能資源だという表層的、実用的な捉え方からもう少し深い理解をすれば、人生がより豊かになるのではないかという気がします。
普段忙しいと自分の周りだけに目を向けてしまいがちですが、折に触れて意識して視野を広げてほしいですね。そして、気候変動や環境問題に深い見識を持った方々が、研究や気候、環境問題に関係のない場でも、社会の隅々で活躍することが大切なのではないでしょうか。
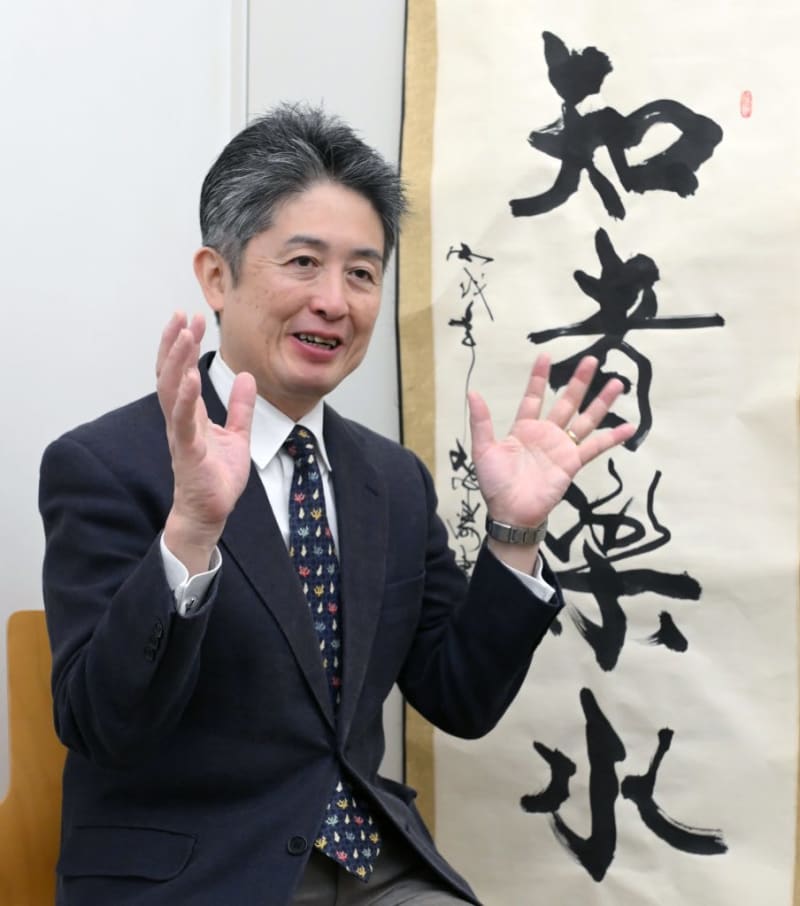
負け戦だと思っても挑戦して
━━これからどのような研究を行っていきたいですか
地球の気温が上がると、大気が温まり水の蒸発量が増えます。雨が短時間で激しく降るようになると川の流れ方も変化して、結果的に干ばつや洪水など、水の災害の起こり方も変わってきます。また都市化が進み人口が都市に集中すると、都市の水が足りなくなったり災害の被害が大きくなったりする傾向があります。
水の循環は物理法則に従うので計算や将来予測がある程度可能ですが、例えば20年後の人口分布や街の姿については、政策により変わる側面もあるので自然の法則だけでは予測不可能です。社会が変わると水の循環も変わり、そしてまた社会が変わるという相互作用も生じます。将来どれだけの人が水不足や水害の被害を受けるリスクがあるのかを推計するには人口分布の予測データが必要ですが、丁寧に作られたデータがありません。適切なデータを構築するとともに、人類はどのような地域に街を作り、水と関わって住んできたかを知りたいと思っています。農耕が始まる前は飲み水さえあれば良いので水はそこまで繁栄の律速(物事の進度や性能を左右する要因)にはならなかったと想像されますが、いわゆる文明ができてからは、水路がないと大量の物資や人を運べないので港や川がないと栄えなくなりました。面白いと思いませんか。これは「社会水文学」が扱う分野です。
今まではすでに与えられた条件下での水の循環が主に研究されていましたが、境界条件との相互作用も考慮するようになりました。水文学もさらに広がっていくでしょう。
━━東大生へのメッセージをお願いします
水文学の研究を始めた当時はデータも測定機器も多くはなく、水文学は比較的地味な分野でした。私の研究の道筋はある意味先駆的だったので、いわばアイドルグループのセンターのような立ち位置でした。目の前は真っ黒な客席で何も見えず、後ろに立つ他のメンバーがどんな立ち振る舞いをしているかも見えないような。それでも挑戦し続けていました。今は先駆的な研究ばかりしているわけではなく、他の論文を読んで「これは自分たちでもやってみたい」と思うときもあります。すでに先方に先取は取られてしまっていますが、追い付いて少しでも抜かしてやろうと思って頑張ったりもします。
できそうにない負け戦だと思っても、やってみたいと感じる目標や、実現できたらいいなと思う目標には、皆さんもぜひ挑戦してほしいと期待します。
The post 日本は水に困らない? 水について客観的な理解をしよう 沖大幹教授インタビュー first appeared on 東大新聞オンライン.