
相続の状況はさまざまですが、遺産トラブルの原因は、どの家庭にもありそう。何が悪かったのか、どうすればよかったのか、曽根恵子さんに伺いました。
↓↓こちらもあわせてどうぞ

お話を伺ったのは
曽根恵子さん
そね・けいこ●相続実務士。一般社団法人相続実務協会代表理事。㈱夢相続代表取締役。
㈱PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続実務士として約1万5000件の相続相談に対処。「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポート。
『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'23~'24版』(成美堂出版)の他、相続関連の著書は78冊を数える。
CASE① 負の遺産を相続して夫婦関係がギクシャク
【実例】
夫が資産価値ゼロの実家を相続過疎地にあり資産価値ゼロの夫の実家。買い手もなく、誰も住まない家を取り壊すには数百万円かかります。なのに「実家は長男のあなたが相続していいから、預貯金だけ半分ずつ分けよう」と言う義姉。ずるい義姉にも腹が立つけれど、義姉に言われるまま相続した夫に腹が立ち、険悪な状態に。
実家をどうするかは、 親が元気なうちに相談、対策を
相続は夫のこととしても、経済的に負担のかかる「負動産」を相続する前に、夫から相談してもらい、夫婦で情報共有しておきたかったですね。長男だからと、全部押しつけられても困りますよね。実家の維持費や解体費は、義姉にも負担してもらうべきだと思います。
全国各地で、相続してもそのまま放置されている空き家の増加が問題になっています。相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が2023年にスタートしましたが、引き取ってもらうには、さまざまな要件があり、建物は処分して更地にしなければならないので解体費用がかかります。
「相続放棄」という方法もありますが、その場合は不動産以外のすべての財産を放棄しなければなりません。また相続放棄をしても、その土地が国庫へ帰属するまでの管理費などは負担する必要があります。裁判所に申し立てて手続きをするとなると、費用も時間もかかり、手続き終了まで2年くらいかかることも。
相続してしまい、とにかくお金をかけずに処分したいのであれば、実家近くに住む親戚や知人に贈与するのも一つの方法です。
誰も住む予定のない実家をどうするかは、親が元気なうちに考えておきたいですね。まず売れるかどうか調べて、売れるのであれば、親が施設に移ったりして空き家になった時点で処分する。売れそうにないのであれば、引き受けてくれる人がいるか探す。親子で話し合い、早めの対処が必要です。

「相続放棄」とは?
相続財産には、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれる。このためプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合も。マイナスの財産が多い場合や、相続を辞退したい場合、相続権を放棄する「相続放棄」を選ぶこともできる。
相続放棄には法的な手続きが必要で、相続人が被相続人の亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする。
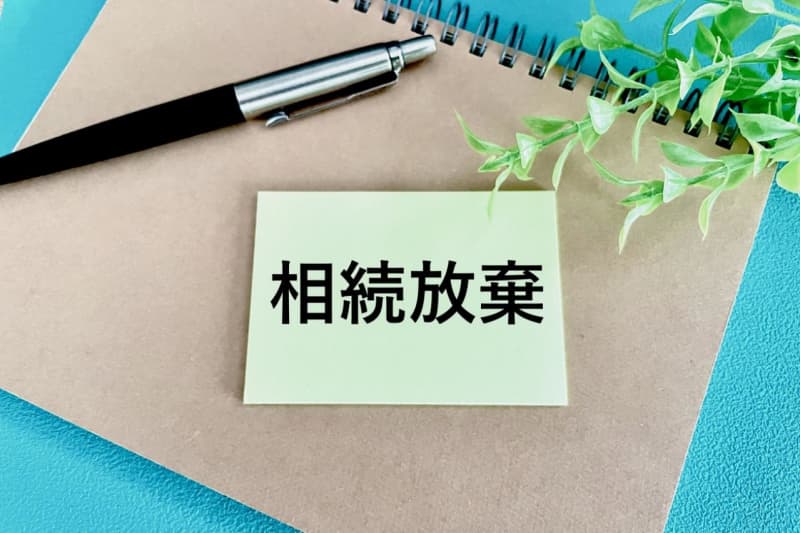
CASE② 相続した財産が自宅不動産のみ、分割できず大もめ
【実例】
親と同居し世話をしたのに実家がもらえない父親と同居し、ずっと世話をしてきました。父は「自宅は私に譲る」と言っていたのに、独立して暮らしている妹と弟は「聞いていない」と言い、「家を売って3人で等分しよう」と主張。話し合いがつかず膠着状態です。相続財産はほぼ自宅のみ。このままだと私は住む家もなくなります。
唯一の財産の家を相続するには 「遺留分」の対策も必要
今は長生きする親も多く、亡くなったあと、預貯金はわずかで財産は自宅不動産のみというケースも多くなっています。誰も住む人がいなければ売却して分ければいいのですが、同居していた子がいるとトラブルになることも少なくありません。
まず同居していた人は、「家は自分が相続するのが当然」と思っていることが多い。対して他の相続人は「自分たちはローンを組んで家を買ったり、家賃を払ったりして暮らしているのに、あいつは家賃もかからず得している」と面白くなく思っている。実家をあげるなんてとても納得できない、となるんですね。
この場合、父親が「自宅を相続させる」意思を、遺言書で明確にしておく必要がありました。法的に有効な遺言書があれば、父親名義の自宅はこの方の名義にして相続登記ができます。ただしここで問題になるのが「遺留分」です。妹と弟にも相続人としての遺留分の権利があります。
相続人はきょうだい3人なので、遺留分は法定割合の3分の1の半分。つまり、それぞれ全財産の6分の1です。この方が実家を相続し、妹、弟から遺留分を請求されたら、遺留分の額の金銭を妹と弟に渡さなければなりません。自宅を相続した人が遺留分を払えれば問題ありませんが、払えなければ泣く泣く家を売って現金を捻出するしかありません。
特に不動産の価値が上がっている地域では、遺留分も相当な額になります。遺留分対策として、親は自宅を相続する子を受取人にして生命保険をかけておく方法もありますが、生命保険に入るお金が必要です。
自宅を売らず、同居していた子が相続するためには、生前から遺留分対策が必要。心配がある人は専門家に相談することをおすすめします。
遺言書を作成する際も、ただ「自宅を相続させる」だけではなく、付言事項に「介護で世話になった感謝から」などと思いも書き添えてもらいましょう。法的効力はありませんが、親の意思が伝わり、説得材料になります。元気なうちに親から、きょうだいに遺言書の内容と存在を伝えてもらうことも大事です。

「遺留分」とは?
一定の法定相続人に認められた、最低限の遺産を受け取れる権利が「遺留分」。遺留分が認められているのは亡くなった人の配偶者、子・孫などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分はない。遺留分の割合は法定相続人が誰かとその組み合わせによって異なる。
たとえば、相続人が長男、二男の2人で、遺言書に「全財産を長男に相続させる」とあっても、二男には「遺留分」があり、この場合の遺留分は法定相続分(全財産の2分の1)の半分なので、全財産の4分の1の額を二男は長男に請求できる。
※この記事は「ゆうゆう」2024年6月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。
取材・文/田﨑佳子
\\あなたの声をお待ちしております// ↓↓をクリックしてアンケートへ
【読者アンケート実施中!】ハマっていることも、お悩みごとも、大募集!!
