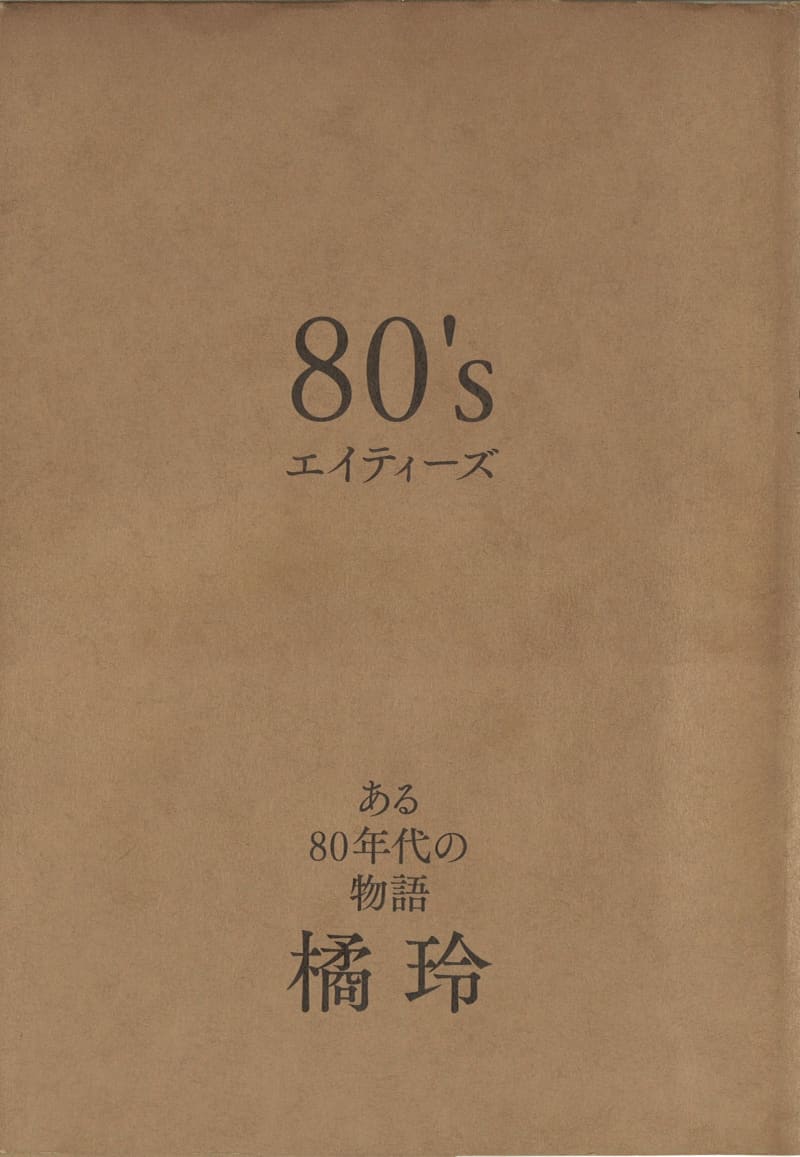
「日本がいちばんきらきらしていたあの時代、ぼくは、ひたすら地に足をつけたいと願った」
帯の惹句にあるこの一文が象徴しているように、本書は80年代に青春を過ごした著者が、時代に浮かれることも踊らされることもなく、世の中の仕組みを見定め、自分に相応しい居場所を求めていこうとした記録である。
高校停学中にドストエフスキーを読んだことをきっかけにして、ロシア文学の魅力に取り憑かれた「ぼく」は、東京の私大でロシア文学を専攻。この時点で「ふつうの」人とは違う道を歩もうと心に決めていた。
「世の中の真実は社会の底辺にあり、大企業のエリートは“ほんとうのこと”などなにも知らずに、平凡に働き平凡な結婚をし、平凡な家庭で平凡な子どもを育て、平凡に死んでいくだけのつまらない小市民」
「ぼく」はそう考えていた。
マクドナルドの深夜清掃のアルバイトから小さな出版社に潜り込み、その後は編集プロダクションを立ち上げてティーンズ雑誌を創刊。女子高生の生態を性の部分も含めてそのまま取り上げたその雑誌は、国会で糾弾されて廃刊に追い込まれた。
やがてフリーランスの編集者となり、中堅出版社で様々なムック本を担当、話題作をいくつも手がけた。そしてその仕事の流れで部落解放同盟やオウム真理教の人々と出会うこととなった。
10代の頃に決めていたように、「平凡」から遠ざかろうとして悪戦苦闘し続けた「ぼく」は、「社会の底辺」に埋もれていた「世の中の真実」を自力で掘り当てていった。それによって「ぼく」はその後、作家として成功することになるのだが、80年代に出会った人の多くは、まるで真実の波に呑まれてしまったかのごとく、罪を犯したり、行方をくらませたり、早死にしたりしてしまった。
80年代の何が良かった、悪かったという話ではない。「ぼく」も含めてバブルの熱狂を冷ややかに眺め、時代の裏側を見つめるように思考していきた人たちがいることで、90年代以降の日本が出来上がったのだ。
時代を作るのは、必ずしも日の当たる場所で華々しく活躍している人ではないのだと、本書によって気付かされた。
(太田出版 1600円+税)=日野淳
