
内村鑑三肖像画(アメリカ・アマスト大学所蔵、内村は同校卒業生)
内村鑑三の思想的背景
“I for Japan,
Japan for the World,
The World for Christ,
And All for God. ”
よく知られた内村鑑三の墓碑銘である。内村は「2つのJを愛する」とも言った。
Japan とJesus(日本とキリスト)である。
内村鑑三(キリスト教指導者、1861~1930)は、彼自身が唱えた無教会主義キリスト教について言う。
「真正(ほんとう)の教会は実は無教会であります。天国には実は教会なるものはないのであります。『われ城(まち、天国)の中に殿(みや、教会)あるを見ず』と約翰(よはね)の黙示録に書かれてあります。監督とか、執事とか、牧師とか、教師とか云う者のあるは此の世限りの事であります。彼所(かしこ)には洗礼もなければ晩餐(ばんさん)式もありません。彼所には教師もなく、弟子もありません」
「世に無教会信者の多いのは無宿童子の多いのと同じであります。茲(ここ)に於いてか私共無教会信者にも教会の必要が出て来るのであります。此の世に於ける私共の教会とは何であって何処にあるのでありましょうか。・・・神の造られた宇宙であります。天然であります。是が私共無教会信者の此の世に於ける教会であります。其の天井は蒼穹(あおぞら)であります。其の板に星が鏤(ちりば)めて有ります。其の床は青い野であります。其の畳は色々の花であります。其の楽器は松の梢(こずえ)であります。其の楽人は森の小鳥であります。其の高壇は山の高根でありまして、其の説教師は神様御自身であります。是が私共無教会信者の教会であります」。(雑誌「無教会」明治34年【1901】3月14日付)
◇
明治維新以降、キリスト教なかでもプロテスタント系(新教徒系)のそれほど青年知識層に大きな影響を与えた宗教はない。これは昭和期のマルクス主義思想の影響に匹敵すると言っても過言ではない。文明開化・欧化主義の高揚のなかで、キリスト教の世界に接近し、そこで「神」や宣教師と教会の雰囲気に触れることにより、西洋に直接行ってみることのできない、つまり洋行の出来ない多くの青年男女達も、近代文明や近代市民社会がどんなものであるかを感得した。
信仰よりも西洋文明が青年たちをキリスト教に近づけさせたとも言える。しかし、キリスト教による衝撃が強烈であればあるほど、それだけ混迷も深かった。洋行を体験した知識人の方がその精神的亀裂は深かったのである。
欧化主義の風潮に呼応するように、南北戦争(1861~65)後のアメリカからプロテスタント系の聖職者が日本の主要都市を訪れ布教活動を展開した。その拠点となったのが、アメリカ人の宣教師・医師、ジェームズ・ヘボンをはじめサミュエル・ブラウン、デイビッド・トムソンの影響を受けた植村正久らを中心とする開港間もない横浜(横浜バンド)、ウィリアム・S・クラークやウィリアム・ホィーラーが教頭を務めた札幌農学校(北大前身)の学生を中心とする札幌(札幌バンド)、さらにはアメリカ人教師リロイ・ジェーンズの教えを受けた熊本洋学校の生徒を中心とする熊本(熊本バンド、その後京都同志社に拠点が移る)などである。
高崎藩士の子息・内村鑑三は、札幌農学校(現北海道大学)第二期首席卒業生で、在学中にアメリカ人宣教師メリマン・C・ハリスから洗礼を受けクリスチャンとなった。洗礼名をヨナタンとした。内村の札幌農学校入学は明治10年(1877)9月である。クラークの滞日はわずかに8カ月間で、すでに帰国しており、土木工学者ホィーラーが26歳の若き教頭(英語ではプレジデント)であった。内村の同期11人の中には、新渡戸稲造(旧制第一高校・現東京大学校長、国際連盟事務局次長、著書「武士道」などがある)、廣井勇(いさみ、札幌農学校や東京帝国大学土木工学科の教授)、宮部金吾(北海道帝国大学教授、植物学者)らクリスチャンの国際的学者・教養人が輩出する(内村は常に最優秀の成績だったが、後年「先生はなぜ東京帝大にはいらなかったのですか」との質問に応じて「金がなかったからさ」と大笑いしながら答えた。(鈴木範久「内村鑑三」より。札幌農学校は学費全額が官費である上に夏冬の制服が支給された)。
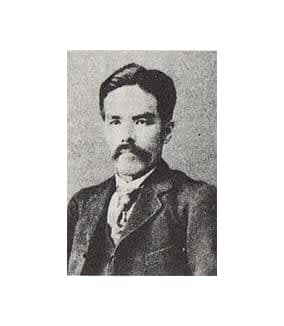
万朝報記者時代の内村(筑波大学附属図書館文献より)
<不敬事件>とそのトラウマ
明治23年(1890)10月30日、教育勅語が発布された。アメリカ留学から帰国した内村鑑三は、この年9月、第一高等中学校(後の第一高校)の嘱託教員として勤めることになったが、時代の荒波にのみ込まれた。月給は65円で、担当は英語と地文(人文地理学・地学)であった。同校では、新年の1月9日授業開始に当たり、天皇自ら親著の教育勅語を受領したばかりであったので奉読式が挙行された。教頭が教育勅語を奉読した後、教員と生徒が勅語に記された明治天皇の署名に対し御真影と同じように「奉拝」することになっていた。鑑三は初めてのことでとっさの判断がつかずためらいがあったようで、わずかしか頭を下げなかった。内村が、自らが信仰するキリスト教の像以外には頭を下げるべきでないと考えていたことは間違いあるまい。
無二のアメリカ人親友ベルに宛てた英文の手紙で「私には恐ろしい瞬間だった。ただちに自分の行動の結果がわかったからだ」と書き送っている。この行為は新聞などを通じて「キリスト教徒による不敬事件」として喧伝された。一連の報道などで心労も重なり鑑三が重い流感にかかり病床に伏している間に、何者かによって辞職願が学校当局に提出され受理された。内村は職を奪われ、友は離れた。教会からは避けられ、暴徒の襲撃を受け、「国事犯人」として旅館にも泊まれなかった。内村はそれ以降20年間ゆっくり眠れなかったと回顧している。この事件は内村の一生を決定づけただけでなく、日本の進路も決めてしまった。
その後、内村は明治30年(1897)以降降、黒岩涙香(くろいわるいこう)発刊の新聞「万朝報」での明治薩長藩閥政府批判などの辛辣(しんらつ)な論説活動によって、マスコミの寵児となり知的青年層(東京帝大、高等師範(現筑波大学)、高等女子師範(現お茶の水女子大学などの学生ら)の心をとらえた。眠れる獅子が立ち上がり咆哮(ほうこう)しだしたのである。内村はジャーナリストとしての才能も豊かだった。
クリスチャンとしての良心と反戦思想
帝国日本は大国ロシアとの無謀な大血戦に突入する。明治36年(1903)夏、ロシアのシベリア鉄道はバイカル湖の迂回線を除く全線が開通した。同国の東清鉄道とその南部支線もつながった。ロシアは清に約束した撤兵期限を過ぎても満州に駐留し、兵力を増強する動きも見せた。東京帝大教授・戸水寛人(とみずひろんど)ら7人の博士は桂太郎首相に「対露開戦」を迫る意見書を出した。これにより一気に開戦の世論が高まった。だが戦力、財力、物量全ての面で日本に勝ち目は薄かった。主戦派の軍人たちでも、いざ戦争を指揮するとなると及び腰になった。
日本国内では日露開戦をめぐって新聞は賛否両論の激しい言論戦を展開していた。東京・大阪の「朝日新聞」「時事新報」「大阪毎日」「国民新聞」は対露強硬論・開戦支持に傾き、「万朝報(よろずちょうほう)」、「二六新報」は非戦を主張した。内村鑑三は、東京一の販売部数にのし上がり一流紙の仲間入りした「万朝報」によって絶対非戦論を叫んだ。明治36年6月30日、彼は「万朝報」に「戦争廃止論」を書いた。
「余は日露非開戦論者であるばかりでない。戦争絶対的廃止論者である。戦争は人を殺すことである。そうして人を殺すことは大罪悪である。そうして大罪悪を犯して個人も国家も永久に利益を収め得ようはずがない。(中略)。世には戦争の利益を説く者がある。然り、余も一時はかかる愚を唱えた者である。しかしながら今に至ってその愚の極なりしを表白する。戦争の利益はその害毒を贖(ルビあがな)うに足りない。戦争の利益は強盗の利益である。これは盗みし者の一時の利益であって(もしこれをしも利益と称するを得ば)、彼と盗まれし者との永久の不利益である。盗みし者の道徳はこれが為に堕落し、その結果として彼はついに彼が剣を抜いて盗み得しものよりも数層倍のものを以て彼の罪悪を償わざるを得ざるに至る。もし世に大愚の極と称すべきものがあれば、それは剣を以て国運の進歩を計らんとすることである」(以下略)。
9月1日付の記事で、内村は再び訴えた。
「余はキリスト教の信者である。しかもその伝道師である。そうしてキリスト教は、殺すなかれ、汝の敵を愛せよと教うるものである。しかるに、もしかかる教えを信ずる余にして開戦論を主張するがごときことあれば、これは余が自己を欺くことである」
陸軍は児玉源太郎に最後の望みを託した。内務大臣である児玉は、国政のかじ取りを担い、戦地に赴く立場ではない。それを戦地に引き戻す人事的な降格を求めねばならない。桂は申し訳ない人事になるが戦争の指揮をとってくれないか、と児玉に申し入れた。児玉は内務大臣を辞し、陸軍史上最初にして最後の降格人事を受け入れた。参謀次長として陣頭に立つ決心をした。参謀総長には薩摩閥の元老大山巌が就いた。
明治36年10月9日、内村は「日露戦争絶対反対」を主張し、幸徳秋水、堺利彦らの論客とともに「万朝報」を去る。内村は社長黒岩に宛てた辞表で言う。
「小生は日露開戦に同意することを以て日本国の滅亡に同意することと確信致し候」
明治37年(1904)2月4日、天皇の御前会議に伊藤、山県、大山、松方、井上の5元老と、桂首相、小村外相、曾彌蔵相、山本海相、寺内陸相ら閣僚が集められ開戦の断が下された。原敬は「少数の論者を除くほかは、内心戦争を好まずして、しかして実際には戦争の日々に近寄るもののごとし」と2月5日の日記に記した。さらに「一般国民、なかんずく実業者は最も戦争を厭うも、表面これを唱うる勇気なし。かくのごとき次第にて国民心ならずも戦争に馴致(じゅんち、慣らされること)せしものなり」(「日記」2月11日付)と書いた。日露戦争は総兵力109万人、戦費19億8000万円を費やし、8万7000人の戦死者を出した。未曾有(みぞう)の犠牲を強いた消耗戦であった。

内村晩年の写真(筑波大学附属図書館文献より)
後世への最大遺物
私の長い読書遍歴の中から内村鑑三の「後世への最大遺物、デンマルク国の話」(岩波文庫)を取り上げて私見を述べてみたい。学生時代から愛読し影響を受けた日本人の著作に「夏目漱石全集」と「内村鑑三全集」がある。宗教哲学者・文明批評家内村鑑三の著作中でも特に愛読しているもののひとつが「後世への最大遺物、デンマルク国の話」である。文庫本で100ページに過ぎないこの小品を私が愛読するのは、苦難のときの心の支えにして来たことにもよるが、内村の土木技術(または土木技術者)にかける期待がいかに厚かったかも知ることができる。
内村の生涯の知友の中で注目したい土木技師が少なくとも2人いる。東京帝大土木工学科教授・廣井勇(いさみ)と内務省技師・青山士(あきら)である。2人については本連載でも既に取り上げているが、広井は札幌農学校2期の同期生で内村と同時期に洗礼を受けたクリスチャンであり、また青山は内村の唱える無教会主義キリスト教の敬虔(けいけん)な信者で同時に廣井の大学門下生である。
「廣井君ありて明治・大正の日本は清きエンジニアを持ちました」と追悼の辞で称(たた)えた内村が、廣井やその愛弟子(まなでし)青山から土木技術に関する高度な最新知識を教授されていたことは想像に難(かた)くない。
さて「後世への最大遺物」である。1世紀余りも前の講演である。(本書を読むと、厳格そのもののような内村が洗練されたユーモアのセンスを持っていたことがほほえましく思える)。内村は、人生は限られているが、何を後世に残せばいいのか、と問いかける。そしてイギリスの代表的な天文学者ジョン・ハーシェルの20歳代の頃の著名なことばを引用する。「我が愛する友よ、我々が死ぬときには、我々が生まれたときより世の中を少しなりとも良くして往こうではないか」。内村は祖国日本を少しでも良くして、そのための遺物を残して、この世を去ろうではないかと聴講者に呼びかける。
「後世に良きものとして残せるもの」として、内村はまず金銭を上げる。「金を残す者をいやしめる人はやはり金のことにいやしいのだ」として、財産を残してその大半を慈善事業に寄付したアメリカ人富豪の例を挙げている。「金を貯めそれを清きことに用いることは、アメリカを盛大にした大原因」とまで言い切る。プロテスタント的価値観といえよう。では金を貯められない者はどうするか。事業を残して逝くべきと言う。氏は土木事業について語っている。「どういう事業が一番誰にでも分かるかというと土木的の事業です。私は土木学者ではありませんけれども、土木事業を見ることが非常に好きでございます。ひとつの土木事業を残すことは、実に我々にとっても快楽であるし、また永遠の喜びと富とを後世に残すことではないかと思います」とまで言い切っている。
では事業が残せない者はどうするか。思想を残せ、と言う。著述をするか学生を指導するか、即ち広義の文学者になるか、教師の道を選ぶか。氏は思想を深めるには、としてイギリス近代の文学者トマス・カーライルの名句を引用する。「何でもよいから深いところに入れ、深いところにはことごとく音楽がある」。内村は教師像について述べる。「先生になるには学問ができるよりも―学問もなくてはなりませんけれども―学問を青年に伝えることのできる人でなければならない」。
金も残せず、事業もできず、思想家・文学者・教師にもなれない者はどうするか。後世への最大遺物は「勇ましい高尚な生涯」であると結論づける。「もし我々が正義はついに勝つものにして不義はついに負けるものであるということを世間に発表するものであるならば、その通りに我々は実行しなければならない。(中略)。我々に後世に残すものは何もなくとも、我々に後世の人にこれぞというて覚えられるべきものは何もなくとも、あの人はこの世の中に活きている間は真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを後世に残したいと思います」。「デンマルク国の話」も土木技術とキリスト教精神の勝利を高らかにうたった敗戦国デンマークの復興物語である。
参考文献:「内村鑑三全集」、拙書「評伝 技師青山士」、同「評伝 技師廣井勇」、筑波大学附属図書館文献など。
(つづく)
