
加藤楸邨(青年教師、筑波大学附属図書館文献)
<人間探求派>俳人の人生
加藤楸邨(しゅうそん、1905~93、本名・健雄)は、近現代の日本俳句界を代表する俳人のひとりである。その作風は中村草田男や石田波郷らとともに「人間探求派」と呼ばれる。私は、楸邨の自然諷詠的な表現を排除し厳格に人生を探求する作風に強く魅かれるものがあり、楸邨について以下自己流に語ってみたい。粕壁(現埼玉県春日部市)の教師時代の作品を中心とする。
私は埼玉県内の河川を現地調査したことがあった。埼玉県は北に利根川、東に江戸川、西に荒川と大河に3方を囲まれ、県内を多数の中小河川や用排水路が網の目のように走っている。古利根川や中川は江戸期以前の利根川本川であり、元荒川はその名の通り江戸期以前の荒川本川である。同県は県内に河川面積の占める割合が全国一で、その昔は今日では考えられないほど水害多発地域でもあった。
同県内の河川調査の際、私は楸邨が古利根川や元荒川などの川べりを歩き、四季の風景を俳句に詠(よ)んでいることを知った。その作品群は彼が埼玉県立粕壁中学(現春日部高校)の国語教員時代のものであった。
◇
ここで彼の人生をスケッチする。「俳句遠近」(加藤楸邨、読売新聞社)などを参考にする。彼は東京市北千束(現東京都大田区北千束)に生まれる。父は内村鑑三の唱導する無教会主義クリスチャンで鉄道官吏であった。転勤が多く、駅長であった父の転勤に伴い若い楸邨は関東、東北、北陸の各地方を転居した。漂泊性の強い習性が身についてしまった、と回顧する。金沢中学(旧制)を卒業すると、定年退職した父に代わって家計を支えるため、進学を断念して小学校の代用教員となる。(代用教員に採用されたことは一面彼が秀才であったことをうかがわせる)。人生苦難の始まりである。この頃、アララギ派や石川啄木の短歌を好んで読んだ。父の病死を期に一家はそろって上京した。
勉学への情熱が捨てきれない青年は、大正15年(1926)東京高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)に併設された第一臨時教員養成所国語漢文科に入学した。苦学生は22歳で同学年中の年長者であった。「ほとんどの期間を家庭教師として過ごしたが、むさぼるように本をよく読んだ」(「俳句遠近」)。万葉集に強く魅かれた。哲学書も読み漁り、フランスの哲学者ベルグソンの「エラン・ヴィタール」(生命の躍動)や「純粋経験」に新たな人生観を見出した。
昭和4年(1929)、東京高等師範学校を卒業し、埼玉県立粕壁中学に赴任した。この年矢野知世子(俳人)と結婚した。24歳。高等師範卒の先輩教師に「いろいろ面倒を見てやるから、その代わりに俳句会のメンバーになれ」(同上)と誘われ俳句を始めた。俳人・村上鬼城の雄渾な作風に惹かれた。「残雪やごうごうと吹く松の風」の句などに「抵抗しがたい奇妙な力を感じた」という。決定的な出会いがあった。俳人で医師の水原秋桜子との邂逅(かいこう)である。楸邨は秋桜子に従って古利根川から関宿、野田あたりへかけて作句行に歩いた。「先生も思いつめたような沈黙の時間が多くなったが『あの頃の夕闇の中に光る古利根川の水を今もさむざむと思い浮かべることができる』という先生の文は、私の中にもそのまま生きていることなのだ」(同上)。
粕壁中学教師時代の作品
楸邨が粕壁中学に勤務したのは昭和12年(1937)までの8年間で、その間の作品は「寒雷」(処女作)に収められている。「古利根抄」(昭和6~9年作)などの中から私の好きな句を抜き出してみよう。
<元荒川>と題された句・洲の鴨のふたたび鳴かぬ夜の雨・摘みわけてゐる綿の実に夕日影・降る雪にさめて羽ばたく鴨のあり・行く鴨にまことさびしき昼の雨
<古利根>や<船戸>と題された句・山茶花(さざんか)のこぼれつぐなり夜も見ゆ・行きゆきて深雪の利根の船に逢ふ・老いし水夫(かこ)吹雪の面を手に拭う・あわれなる寄生木(やどりぎ)さへや芽をかざす
<川間駅>と題された句・末枯に鶏をはしらせ電車来ぬ
<晩秋>と題された句暴風雨くる夜の人ごゑは晩稲刈(おくてがり)稲妻のきらめく畦(あぜ)に稲負へり稲妻のちから衰へしぐれきぬ
昭和12年、楸邨は中学教師を辞めて東京に移り住む。その時<古利根を去りて東京に出づ>と題された句・菜が咲いて鳰(にお)も去りにき我も去る
秋桜子の勧めで「馬酔木(あしび)」発行所に勤務しながら、東京師範学校(現筑波大学)の上にできた国立大学で今日の大学院に相当する東京文理大学国文科に進学する。31歳の大学生(実質的には研究生)である。
<文理科大学占春園>と題された句(占春園はキャンパス内に残された江戸期の庭園)・身のほとり木の芽の光ふるごとし
◇
昭和26年(1951)秋、楸邨が46歳の時、高齢の彫刻家・詩人高村光太郎を岩手県の山間地山口村(当時)の自己離謫(るたく)の地に訪ね初面会をした。印象記を「俳句遠近」に載せている。「人間探求派」らしい文章の一部を引用したい。
「光太郎翁はこんなことをいわれた。『僕はバッハのブランデンブルグ協奏曲がどうしても聞きたくなることがある。それは今花巻の知人の家にしかない。思いたつと僕はすぐ花巻まで歩いてゆく。そしてとにかく何よりも先にブランデンブルグ協奏曲に耳を傾ける。するとだね、僕の中に睡っていたものがさっと目を覚まして、僕の中で生きて動き出すんだ。これが消えない中に薄(すすき)の原の中の夜道を山口村に帰って来るのだよ。君、その道道、薄の上の空をだね。ブランデンブルグ協奏曲が波濤のように走り奏でられるんだ。僕ももちろんその曲の中で歩いている。月も星も薄も何もかも曲の中にあるわけだ』。私は残念ながらそれまで音楽には縁が遠くて親しむことがなかった。両手をタクトのように振りながら話してくれる翁の水っ洟(ルビぱな)がときどき飛び散ったことを忘れることができない」。
傑出した芸術家の精神性をこれほど見事に描いた訪問記にはなかなか巡り会えない。
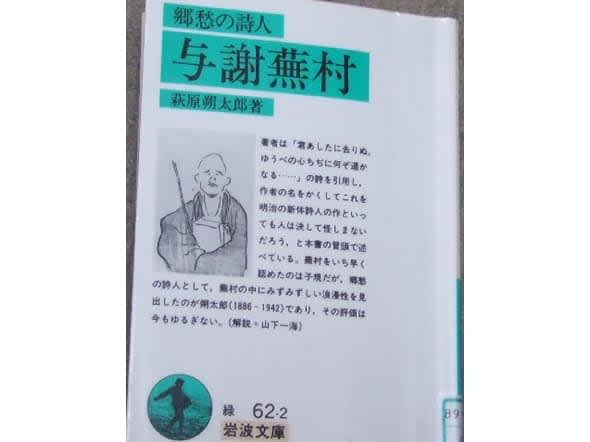
「郷愁の詩人 与謝蕪村」(萩原朔太郎著)
朔太郎しか書けない「蕪村論」
春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな 菜の花や月は東に日は西に 愁(うれ)ひつつ丘に登れば花茨 木枯や何に世渡る家五軒
与謝蕪村ならではの秀句である。私は本格的な句作や俳句研究をしたことはないが、それでも時に駄句をひねり古今の名句を鑑賞することを好んできた。近現代の俳句はもとより、江戸初期の松尾芭蕉、同中期の蕪村、後期の小林一茶の3俳聖の作品を愛読して来た。とりわけ蕪村には強く魅かれるものがある(蕪村は生前俳人よりも画家として著名であった)。蕪村俳句の魅力をみごとに喝破した作品論が、詩人・萩原朔太郎(1886~1942)の「郷愁の詩人 与謝蕪村」(昭和11年刊行)である。名だたる詩人が論じた稀有な「詩人論」として、氏の蕪村論に勝るものはない。私も共感するところが少なくない。朔太郎の「蕪村論」を論じてみたい(引用は岩波文庫版。同書「解説」から引用する)。
朔太郎は自著の冒頭で言う。「俳句嫌いであった自分にとって、蕪村だけが唯一の理解し得る俳人であった」。「彼の俳句だけを愛したという事実は、思うにおそらく蕪村における特異なものが、僕の趣味性や気質における特殊な情操と密に符合し、理解の感流するものがあったためであろう」。蕪村に同じ資質の詩人の魂を見出したのである。朔太郎は蕪村の句作の特徴として(1)万葉歌境に通じる春怨思慕の若々しいセンチメントがあること(2)画家らしく色彩の調子(トーン)が明るく、絵具が生々(なまなま)しており、強烈であること、即ち<若々しい明るさがあること>を挙げている。蕪村が心酔してやまない芭蕉と比較して、芭蕉が老の静的な美を慕い反青春的風貌を持っているのに対し、蕪村は色鮮やかな青春の情緒を描いていると指摘する。
朔太郎は蕪村評価の歴史を回顧して、江戸時代には影の薄かった蕪村が、近代になって再評価されたのは、正岡子規以来のことだとした上で、そこで作られた<定評>―即ち蕪村は客観的であり、芭蕉が主観的であることに対比して考えられるという<定評>が、無批判に受け継がれていると批判する。蕪村の客観的と見える背後に実は強い主観があることを指摘し、そこにこそ蕪村のポエジイ(詩情)があると強調する。いまこそ蕪村の詩境を考えなければならないとして、そのポエジイの本質を<郷愁>であると結論づける。同書では「春の部」「夏の部」「秋の部」「冬の部」と四季に分けて秀句を論じている。
朔太郎の蕪村読解
朔太郎の優れた作品解釈を思いつくままに列記してみよう。
遅き日のつもりて遠き昔かな(「春の部」)「蕪村の情緒。蕪村の詩境を単的に詠嘆していることで、特に彼の代表作と見るべきだろう。この句の詠嘆しているものは、時間の遠い彼岸における、心の故郷に対する追懐であり、春の長閑(のどか)な日和の中で、夢見心地に聴く子守歌の思い出である」。
陽炎や名も知らぬ虫の白き飛ぶ(「春の部」)「この句の情操には、或る何かの渇情に似たところの、ロマンチックな詩情がある。『名も知らぬ虫』という言葉、『白き』という言葉の中に、それが現れているのである」。
白梅に明ける夜ばかりとなりにけり(「春の部」)「天明3年(1783)、蕪村臨終の直前に詠じた句で、彼の最後の絶筆となったものである。白々とした黎明の空気の中で、夢のように漂っている梅の気あいが感じられる。全体に縹渺(ひょうびょう)とした詩境であって、英国の詩人イエーツが狙ったいわゆる「象徴」の詩境とも、どこか共通したものが感じられる」。
愁ひつつ丘に登れば花茨(「夏の部」)「『愁ひつつ』という言葉に、無限の詩情がふくまれている。無論現実的の憂愁ではなく、青空に漂う雲のような、または何かの旅愁のような、遠い眺望への視野を持った、心の茫漠とした愁えである。そして野道の丘に咲いた、花茨の白く可憐な野生の姿が、主観の情愁に対象されている。西洋詩に見るような詩境である」。
月天心貧しき町を通りけり(「秋の部」)「月が天心にかかっているのは、夜が既に更けたのである。人気のない深夜の町を、ひとり足音高く通って行く。町の両側には、家並の低い貧しい家が、暗く戸を閉ざして眠っている。空には中秋の月が冴えて、氷のような月光が独り地上を照らしている。ここに考えることは人生への或る涙ぐましい思慕の情と、或るやるせない寂寥とである。月光の下、ひとり深夜の裏町を通る人は、だれしも皆こうした詩情に浸るであろう。しかも人々はいまだかつてこの情景を捉え表現しえなかった。蕪村の俳句は、最も短い詩形において、よくこの深遠な詩情を捉え、簡単にして複雑に成功している。実に名句と言うべきである」。
凧(いかのぼり)きのふの空の有りどころ(「冬の部」)「北風の吹く冬の空に、凧(たこ)が一つ揚っている。その同じ冬の空に、昨日もまた凧が揚っていた。蕭条とした冬の季節。凍った鈍い日差しの中を、悲しく叫んで吹きまくる風。ガラスのように冷たい青空。その青空の上に浮かんで、昨日も今日も、さびしい一つの凧が揚っている。飄々(ひょうひょう)と唸りながら、無限に高く、穹窿(きゅうりゅう)の上で悲しみながら、いつも一つの遠い追憶が漂っている!この句の持つ詩情の中には、蕪村の最も蕪村らしい郷愁とロマネスクが現れている」。
木枯や何に世渡る家五軒(「冬の部」)「木枯らしの吹く冬の山麓に、孤独に寄り合っている五軒の家。『何に世渡る』という言葉の中に、句の主題している情感がよく現れている。荒涼とした寂しさの中に、或る人恋しさの郷愁を感じさせる俳句である」。
優れた詩人のみが優れた詩人を見出すの感を深くする。
参考文献:「加藤楸邨句集」(岩波文庫)、「郷愁の詩人 与謝蕪村」(萩原朔太郎)、筑波大学附属図書館文献。
(つづく)

