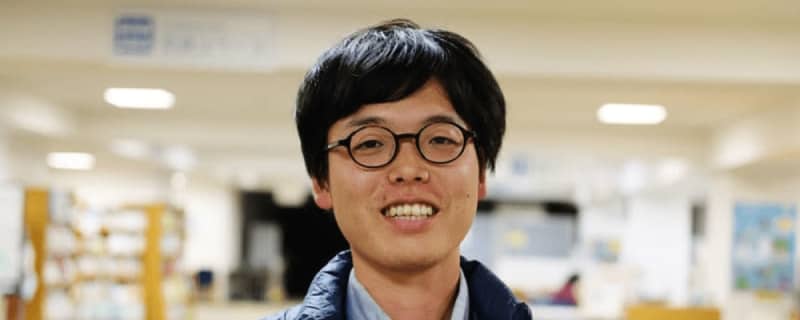
7月に発災した平成30年7月豪雨から4ヶ月が過ぎる頃、特に大きな被害があった岡山県倉敷市真備町に改めて足を運んだ。
車で町を走ると、まるで水害なんてなかったかのように元気に営業を再開している商店があると思えば、あの日から時が止まったかのように土砂に飲み込まれたままの家屋も見受けられる。

復旧から復興へ移行するフェーズと耳にすることもあるが、その状況は一人ひとり異なり、進捗度合いに大きな開きが出てくるフェーズのように感じられた。
きっと、地域の復興ではなく、一人ひとりの生活再建という解像度で向き合わなければならないはず。そのために何が必要なのだろうか。
そんなことを思いながら、真備町から岡山市へと向かった。

訪れたのは岡山県社会福祉協議会。
発災直後から寄り添いながらも俯瞰して被災地の支援を続けている社協、そして社協が運営するボランティアセンターの活動と現在の状況を伺った。
お話をしてくださったのは地域福祉部 主任の西村洋己さんだ。

自分の町で災害が起こったら、と何度も考えられてきたはずだが、実際に起きてみると「まさか」という気持ちはゼロではなかったようだ。
「発災直後から約2ヶ月は10市町で立ち上がったボラセンを巡回して、総合的に支援していました。9月以降は倉敷市のボラセンに常駐し、外部の専門家によるサポートの連携や県内の社協スタッフの調整やボラセンの引っ越しの段取りなど、中間支援と後方支援を担っています。」やわらかな表情の西村さんだが、今でも倉敷を中心に、被災地域の状況把握に奔走する毎日だ。

「これまでも様々な災害現場を見てきましたが、東日本大震災以来の大きな災害ではないかと感じますし、過去に類を見ない大水害でしょう。一見誰も住んでいないように見える窓のない住宅にもたくさんの方が暮らしている状況で、復興はまだまだこれからです。」と真備町エリアの状況を話す。
復興の進み具合における個人差に開きが出てきていることは、社協としても把握した上でどう対応するかを考えられていた。「被災された家と一言で言っても、被害の大きさだけでなく、先祖代々続く家から新築の家まで状況は様々です。災害から4ヶ月経って、ようやく踏ん切りがついて、再建するか取り壊すかの覚悟が決まった人もいらっしゃいますね。私たちも急かさずに、悩まれている時間を大切にしたいなと考えています。」
西村さんは当サイト「いまできること」を運営する助けあいジャパンの代表石川と面識があったこともあり、「みんな元気になるトイレ」を真備町のボラセンに招致された。

「災害用のトイレトレーラーがあることはお聞きしていたので興味はあったのですが、地理的に最適な設置場所を決めかねていました。その後真備町の被災地域にボラセンを移転することになったタイミングで設置することができました。」まだ導入したばかりだが、トイレ利用以外の成果もあるようだ。
「お化粧をしたり着替えたり、いろんな用途に使っていただければいいなと考えています。今後の防災という観点でも、ここを訪れる人に災害用トイレトレーラーというものがあるということを認識していただくだけでも価値があることかなと思います。」
約10年の間、日頃から多方面の人と交流を持ち、情報交換を行ってきたことが、今回の災害でとても活きていると西村さんは強調する。「災害が起こってから緊急時にできることはどうしても限られてしまいます。平時にいかに備えておくか、そして色んな人とのつながりを築いておくかが、有事の選択の幅を大きく広げてくれると感じました。トイレトレーラーだって、つながりがきっかけですしね。災害に直接関係ない方々でも町への関心さえ高ければ、有事の際は必ず力を合わせることができると思います。」

そして、今回の災害の教訓として、意識変革への限界も感じたという。
「防災キャンペーンもとても大切ですが、それだけでは足りない。様々な理由で防災を行動に移せないという人は少なからずいるでしょう。自然と日常の中で防災を気にかける環境をどうデザインするかという科学的なアプローチが求められているように感じています。」
平成も残すところ約半年。
数々の自然災害に見舞われた時代であったが、それらを無駄にすることなく、日本の防災と復興の技術が培われた時代でもある。
平成30年7月豪雨の経験をどのように次に活かすか、自分の町にどう活かすか。
一人ひとりがそれを考え行動することが、結果として被災地を想うことにつながるのかもしれない。
文・写真:柳瀬武彦

