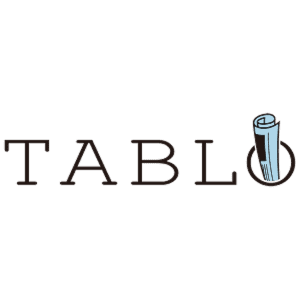《鳥屋野潟の漁師が真っ暗い夜、舟をこいで行くと向こうからも舟がこちらへ向かってくるのがうすぼんやりと見える。その舟はだんだん近づいてこっちの舟に寄って来る。よけようと舟を動かしてもその舟は同じ方向に向かってくる。ぶつかると思った瞬間、舟は影も形も見えなくなっていた。その舟は亡者舟と呼ばれ、鳥屋野潟では遭難して成仏できない霊が亡者舟となって出てくるのだと言われていた。そして亡者舟にあった人間は間もなく死ぬといわれた。》
~新潟市潟環境研究所「新潟市潟のデジタル博物館/くらし・文化」より「鳥屋野潟の亡者舟」(初出:『新潟市史(平成3年度版)』)~
初めて鳥屋野潟を前にしたときは素直に「湖だ」と思った。南北から引っ張られて出来た大地の裂け目は水面を広々と延べており、「潟」という字からイメージする沼地とは異なって開放的で明るかった。
「良いところに官舎があるのねぇ。春んなるのが待ち遠しいて思わん?」
周囲9キロ余りもあるという水際を埋める並木を眺めながら母は幸せそうなため息をついた。並木は桜で、鳥屋野は花見の名所として有名だ。佐藤茂男さんは勤め先が分割民営化されたのは何十年前だろうと思いながら、「今は社宅だよ、官舎じゃなくて」と誤りを訂正した。
母は笑顔で「そうだった、そうだった」といい加減に応えた。
「まだ夏だってのに、秋冬飛ばして春て。雪になったら白鳥が見られる」
「ほんね、ええとこら。ずっと居ってもええぐらい。思うたったより部屋数もあるし、横の公園が庭がわりで、早う散歩してみたい」
「母さん、楽しそうだなぁ」
「ちっとばか、はじけとる?」
「うん。子どもみたい」
「......あんたにそんなん言われる日が来るとはね」
「俺が幾つになったと思ってんの」
茂男さんが父を亡くしたのは中学生のときだ。家計を助けるため高校を卒業するとすぐ電鉄会社に就職した。新潟支社で貨物列車の運転士になり、父が遺してくれた家で母とつましく暮らしてきた。
三十路も半ばに差し掛かり、少し貯えが出来てきたちょうどそのタイミングで、ある女性と恋に堕ちた。結婚を決めたのは昨年――2007年――の暮れで、今は8月の盆の入り。婚姻届けの提出と挙式は11月、新居が完成するのは3月の予定だ。
父が遺した古い家を取り壊して更地にし、あらためて土台から家を造るのだ。何ヶ月もかかるのは、地盤改良からやり直すためだ。二世帯住宅にして母と同居する計画に、未来の妻は賛成してくれた。
「しばらく、楽しいわ。旅行みてだ」
母は、家の建て替え工事の間、社宅で息子と暮らすことを心待ちにしていたようだった。社宅は昭和の団地ふうの四角い4階建てで、新しくもなければ洒落てもいないコンクリートの塊なのだが。3棟同じ形の建物が並んでいるところが、無機質な味気なさに加速をかけていた。
「本当に今夜はホテルに泊まらなくてよかったの? すぐ近くに小綺麗な旅館もあるよ? 今から母さんだけでも部屋を取ったら......」
「そんげなもったいね! 茂男の社宅で充分」
「じゃあ、せっかくだから新潟駅の方まで行って、寿司か何か食おう」
「もったいねえて言うたろう? お嫁さんが来るまで節約しんば! お母さんがご飯炊いてあげるすけ帰ろう」
「今日ぐらい、いいでねっか!」
――その日は結局、新潟駅近くで母にご馳走を奢り、タクシーで帰宅した。母は盛んに遠慮しつつも嬉しそうで、茂男さんにとっても慌ただしくも楽しい一日となった。