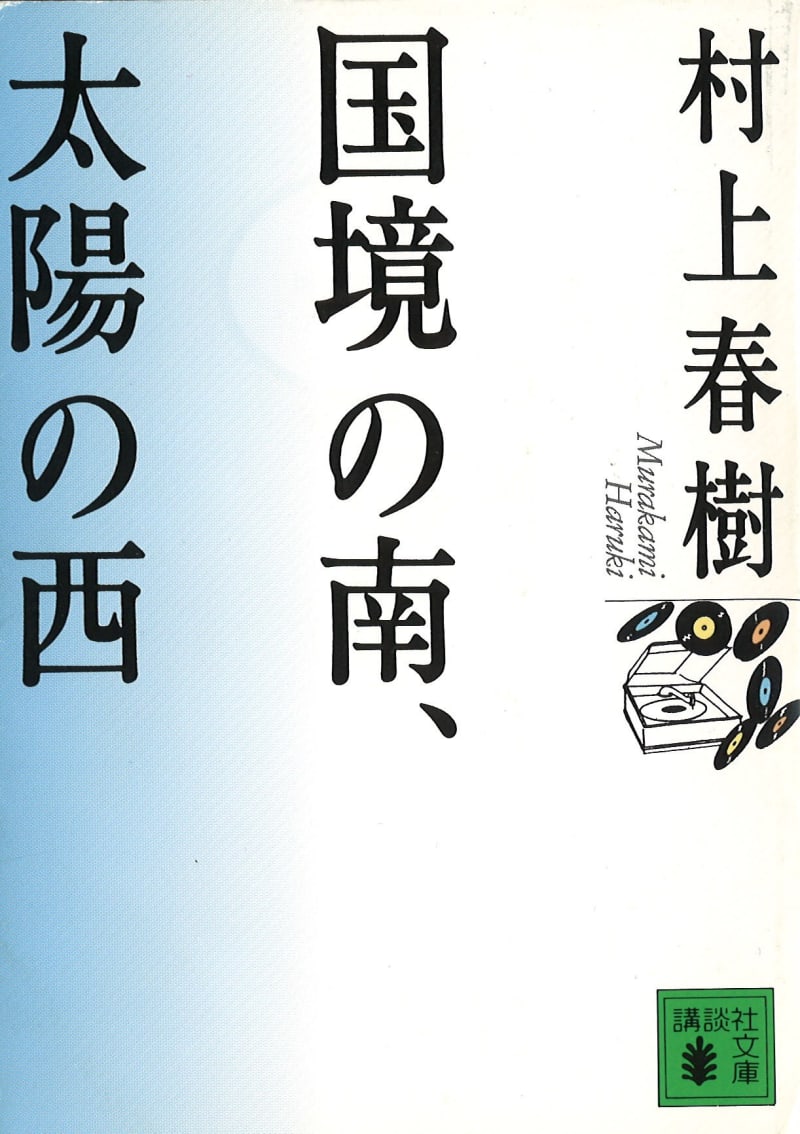
4月には新しい元号が発表され、5月1日には皇太子が新天皇となって、改元されます。このため、「平成」という元号についての話題が多いです。
村上春樹作品のうちで、作中には元号のことは出てこないのですが、「戦後の昭和」という時代を強く意識して、書かれた重要な作品に『国境の南、太陽の西』(1992年)があります。今回の「村上春樹を読む」では、そのことを紹介したいと思います。
☆
「僕が生まれたのは一九五一年の一月四日だ。二十世紀の後半の最初の年の最初の月の最初の週ということになる。記念的といえば記念的と言えなくもない。そのおかげで、僕は『始(はじめ)』という名前を与えられることになった」
『国境の南、太陽の西』は、そのように書き出されています。主人公に対するこういう命名法は村上春樹では非常に珍しいです。
でも、それに続いて「父親は大手の証券会社に勤める会社員であり、母親は普通の主婦だった。父親は学徒出陣でシンガポールに送られ、終戦のあとしばらくそこの収容所に入れられていた。母親の家は戦争の最後の年にB29の爆撃を受けて全焼していた。彼らは長い戦争によって傷つけられた世代だった」とあります。
村上春樹自身は1949年、昭和24年の1月12日生まれですが、始は1951年1月4日生まれ。2年年下の主人公ですが、同作は「長い戦争によって傷つけられた世代」の子どもとして、戦後に生まれてきた世代の物語で、戦争を書き続けてきた村上春樹らしい物語の開幕だとも言えます。
☆
最初に、この作品を読んだ時、感じた感覚が忘れられません。ものすごく直線的で<村上春樹がこんな直線的な作品を書いたことがあるかなぁ……>と感じました。村上春樹作品には2つの物語が並行して進んでいく形の小説がたくさんありますが、そういう形の小説ではなかったのです。そして、読み終わると、何か、とても<怖い>のです。
「直線的」というのは、途中で主人公が立ち止まって、じっくり考えて、また進んでいくという物語展開ではなく、大切なものが、どんどん捨てられていきながら物語が進んでいくという感覚です。
☆
同作では、主人公の「始」が通う小学校に「島本さん」という女の子が転校してきて、「僕」(始)は同級生の彼女と親しくなります。「僕」が「島本さん」の家に遊びに行って、ナット・キング・コールの『プリテンド』などを、レコードで聴いたりします。そして「始」と「島本さん」は小学生時代、12歳の時に「島本さん」の家でレコードを聴きながら、じっと手を握りあったことがあります。
「島本さん」が、「僕」の手を握ったのです。手を取りあっていたのは全部で十秒程度でしたが、「僕にはそれが三十分くらいにも感じられた。そして彼女がその手を放したとき、僕はそのままもっと手を握っていてほしかったと思った」とあります。「そのときの彼女の手の感触を僕は今でもはっきりと覚えている」ともあります。
でも小学校を出ると、「僕」と「島本さん」は別の中学校に進みます。「僕」は事情があって、違う町に移ります。それから3カ月の間は何度か「島本さん」のところに行っていたのですが、2人は会わなくなってしまいます。
☆
そして、「僕」は高校2年生の時、イズミという女の子と親しくなり、3回目のデートで、キスをします。
さらに「僕」は高校3年生の17歳の時、大学2年生の女性とセックスをするのですが、その女性はイズミの従姉でした。そのことで、「僕」はイズミを深く傷つけ、イズミを損なってしまいます。同時に自分も損なってしまうのです。
大学に入ったときに、「僕」は「もう一度新しい街に移って、もう一度新しい自己を獲得して、もう一度新しい生活を始めようとした」のですが、「でも結局のところ、僕はどこまでいってもやはり僕でしかなかった。僕は同じ間違いを繰り返し、同じように人を傷つけ、そして自分を損なっていくことになった」と記されています。
☆
「僕」は結婚して、子どもも出来ます。妻が妊娠している時、何度か軽い浮気をしたりもしています。
そして最初の子供が生まれて、少ししたころ、実家から転送されてきた一通の葉書を受け取ります。会葬御礼の葉書で、36歳で亡くなった女性でした。その名前には心当たりがなかったのですが、しばらく考えているとイズミの従姉であることに思い当たるのです。「僕は彼女の名前をすっかり忘れてしまっていた」のです。そのように、何でも捨てて、忘れてしまいながら生きてきた「僕」なのです。その葉書を送ってきたのはイズミに違いありませんでした。このあたりも、かなり怖いです。
☆
「僕」は妻の父親が持っていた東京・青山のビルの地下で、ジャズを流す、上品なバーを始めていたのですが、その店が雑誌『ブルータス』の「東京バー・ガイド」という特集に載ったので、高校時代の友人が来店します。その彼は、イズミが愛知県豊橋のマンションで1人で住んでいることを知らせます。
イズミは「誰も彼女と口を利いたことがない。廊下ですれ違って挨拶しても返事がかえってこない。用事があってベルを押しても出てこない。いても出てこない」という人間になっているようです。
「僕」には、イズミをそのように損なってしまったという「悪」の自覚はあるのですが、本当にこのことを繰り返さないという覚悟が形成されるという形になっていません。
バーの開店にしても、結婚時には「僕」は教科書出版社の仕事をしていたのですが、妻の父親から、自分のビルで「よかったらそこで何か商売をやらないか」「もし本当にやる気があるんなら資金は要るだけ貸してやるよ」と言われて、その「悪くない話」に従ったのです。「悪くない話」に、すぐのっていくタイプの人間なのです。本人のその場の都合で、何かがバラバラと捨てられていく感じの「僕」の物語です。
☆
そして「僕」が36歳の11月、「僕」が経営するバーに、あの「島本さん」がやってくるのです。これは怖いですね。年明けて、37歳になった「僕」の店にも「島本さん」がやってきて、「僕」は「島本さん」とほとんど毎週のように会っていきます。ついに2人は「僕」の箱根の別荘に行って、激しく結ばれるのです。でも「島本さん」は「僕」と関係した後、翌朝には、まるで幽霊のように「僕」のところから立ち去ってしまいます。この「島本さん」が、現実の存在なのか、幽霊なのか、どんな存在なのか、作品が発表された時には随分話題となりました。
「島本さん」が消えてしまったので、仕方なく「僕」は家に帰りますが、妻が「しばらく前からあなたに好きな女の人がいることくらいわかっていたわ」と言います。これも「怖い」ですね。
☆
さて、この作品は、何を書いているのでしょうか。話を分かりやすくするために、私の考えをまず述べてしまいましょう。主人公への「始」という命名も村上春樹作品の中で変わっていることを紹介しましたが、「島本さん」という名前も象徴的だと、私は考えています。「島本」とは「島国日本」を縮めた命名なのではないかと、私は考えているのです。その理由を以下、記してみたいと思います。
☆
「僕」のバーで「島本さん」と「僕」が、37歳の時に、こんなふうに話しています。
「若く見えるわよ。三十七にはとても見えないわ」と島本さんが言うと、「君もとても三十七には見えない」と始が言います。「でも十二にも見えない」「十二にも見えない」と言い合うのです。
紹介したように「始」は1951年1月4日生まれです。その「始」と「島本さん」の2人が37歳である時を計算してみれば、1988年です。1988年は「昭和」で言えば、「昭和63年」のことです。そして「昭和64年」は最初の1週間しかないので、まもなく昭和が終わるという年です。
「二十世紀の後半の最初の年の最初の月の最初の週」に生まれたので「始」と名づけられたのですが、その「最初の週」という部分に、「昭和64年」は最初の1週間しかなかったことと対応しているのではないだろうかと、私は感じてます。
☆
そして「でも十二にも見えない」の部分ですが、「始」と「島本さん」は12歳だった時に、「島本さん」の家でレコードを聴きながら、じっと手を握りあったことがあります。それも計算してみると、1963(昭和38)年ということになります。
「1963年」は、デビュー以来、村上春樹がこだわり続けている年です。『風の歌を聴け』(1979年)などを読んでも「ケネディー大統領が頭を撃ち抜かれた年」のことが書かれていました。それは「1963年」のことです。登場人物たちが集う「ジェイズ・バー」が「僕」の「街」にやってきた年です。そのころからヴェトナム戦争が激しくなった年です。『風の歌を聴け』の「僕が寝た三番目の女の子」で、21歳で死んでしまった彼女の写真を1枚だけ、同作の「僕」は持っていて、その写真の裏には「1963年8月」という日付けがメモしてあります。それは彼女が「人生の中で一番美しい瞬間」の年でもあります。
☆
ですから「1963年」のことを簡単に「こういう年」と断定することはできないのですが、でもあえて、私の考えを記せば、「1963年」は、前の東京オリンピックが開かれた「1964年」の前年という意味が含まれているのではないかと思います。
東京オリンピックが開かれた「1964年」を目指して、日本人は日本の山を崩し、海を埋め立て、高層ビル群を建てるというような計画を進め始めました。そのように日本の美しい自然が失われていくことの象徴である東京オリンピックの前年、つまりまだ日本の自然に美しさが残っていた最後の年という意味が含まれているのではないかと思うのです。
ですから「若く見えるわよ。三十七にはとても見えないわ」「でも十二にも見えない」という言葉の中に、日本の戦後(20世紀後半)の「昭和」という時代が語られていると思うのです。
☆
例えば、「僕」は30歳になって5歳年下の有紀子と出会い、結婚をするのですが、それが書かれる章の直前には、たいした理由もないのに、見知らぬ男から10万円の現金がはいった封筒を貰ったことが記されています。
「僕」は、その封筒に封をしたまま机の引き出しにしまいこんでいます。その金を貰った理由について、「僕」はいろいろ仮説を立てて考えてみますが、「うまく腹の底から納得することができなかった」し、「どれだけ考えても、それは深い謎として」残りました。
そして、「島本さん」と箱根で関係した後、「島本さん」が消えてしまい、しかたなく自宅に帰った「僕」が「ふと思いついて十万円が入った例の封筒を探してみた」のですが、「でも引き出しの中には封筒は見当たらなかった。それは非常に奇妙で不自然なことだった」と書かれています。
これは、何を表しているのでしょう。でも、ここに戦後の昭和の終わりまでの時代を置いて考えてみれば、大した理由もなく、お金を得て、そのお金が謎のうちに消えてしまうという、バブル経済の姿が描かれていることがよくわかります。
☆
紹介したように『国境の南、太陽の西』には、「僕」と「島本さん」が箱根に2人だけで行って結ばれる場面が大きな山場ですが、その前に、もう一つ、たいへん印象的な場面があります。
「ねえ、ハジメくん」「あなたどこか川を知らない? 綺麗な谷川みたいな川で、そんなに大きくなくて、川原があって、あまり淀んだりせずに、すぐに海に流れ込む川。流れは早い方がいいんだけれど」と「島本さん」に言われて、「僕」と「島本さん」が石川県の川に行く場面です。
その川に「島本さん」は白い灰を流します。「あれは私の赤ん坊の灰なのよ。私が生んだ、ただ一人の赤ん坊の灰」と「島本さん」は話します。その後、「島本さん」の顔は紙のように真っ白になってしまいます。そして「僕」は閉鎖されたボウリング場の駐車場に車をとめて休みます。
「僕」は「島本さん」の「瞳の中をじっと覗き込んでみた。でもそこにはまったく何も見えなかった。瞳の奥は死そのもののように暗く冷たかった」とあります。その後、薬を飲んで、「島本さん」は回復するのですが。
☆
そして、この「島本さん」の瞳を覗く場面がもう一度、『国境の南、太陽の西』に出てきます。それは、まさに「僕」と「島本さん」が箱根に行って交わる時です。
その時も、「僕」は記憶に残る、石川県のボウリング場の駐車場で見た「島本さん」の瞳のことを考えています。彼女の「瞳の奥にあったものは、地底の氷河のように硬く凍りついた暗黒の空間だった」こと、そして「それは僕が生まれて初めて目にした死の光景だった」と「僕」は思い出しているのです。
そして、箱根で「僕」が「島本さん」の体を抱いた時の「島本さん」の瞳は次のように書かれています。長い引用ですが、大切な場面です。
「彼女の頬にはたしかな温かみが感じられた。僕は髪を上にあげて、その耳に口づけした。それから僕は彼女の目を覗き込んでみた。僕は彼女の瞳に映った僕の顔を見ることができた。そしてその奥にはいつもの底の見えないほどの深い泉があった。そしてそこには仄かな光が輝いていた。それは生命の灯火のように僕には感じられた。いつか消えてしまうかもしれないけれど、今はたしかにそこにある灯火だった。彼女は僕に微笑んだ。彼女が微笑むといつものように小さな皺が目の脇に寄った。僕はその小さな皺にキスをした」
☆
この「島本さん」の瞳の奥にあったものが、石川県のボウリング場の駐車場と、箱根とでは少し違っていますね。石川県のボウリング場の駐車場では「瞳の奥にあったものは、地底の氷河のように硬く凍りついた暗黒の空間だった」「それは僕が生まれて初めて目にした死の光景だった」とありました。
それが箱根では「その奥にはいつもの底の見えないほどの深い泉があった。そしてそこには仄かな光が輝いていた。それは生命の灯火のように僕には感じられた」となっています。
この変化の意味について、考えて、今回の「村上春樹を読む」を閉じたいと思います。
☆
村上春樹の小説はいくつもの謎に満ちていますが、この物語も例外ではありません。その謎の中で、『国境の南、太陽の西』最大の謎は<普通とは逆のセックス>というものではないかと思います。
「ハジメくん」「服を脱いで体を見せてくれる?」と「島本さん」が言うのです。「まずあなたが服を全部脱ぐの。そしてまず私があなたの裸を見るの。いや?」
そして裸になった「僕」の体をじっと「島本さん」は見ています。「島本さん」はまだジャケットも脱いでいません。
そして「ねえハジメくん、私のすることがもし何か変な風に見えたとしても、それはあまり気にしないでね。私はそうすることが必要だからそうしているだけなのよ。何も言わないで、私にそうさせておいてね」と言います。
さらに「こうするのが長いあいだの私の夢だったんだから」とも「島本さん」は加えています。「島本さん」は「僕」の性器に触り、自分の性器を撫でています。
「恥ずかしいけど、一度こうしないことには、どうしても気持ちが落ちつかなかったの。これは私たちにとっての儀式みたいなものなの。わかる?」と「島本さん」が「僕」に語ります。
それに続いて、紹介した「その奥にはいつもの底の見えないほどの深い泉があった。そしてそこには仄かな光が輝いていた。それは生命の灯火のように僕には感じられた」という「島本さん」の瞳の奥の話の文章が続いているのです。
☆
この<普通とは逆のセックス>は、何を意味しているのでしょう。奇妙な形のセックスは何を意味しているか……。「島本さん」は「僕」に「これは私たちにとっての儀式みたいなものなの。わかる?」と語っていますが、正直、難しいですね。
でも、私なりの受け取り方を書いて置きたいと思います。
「島本さん」の「島本」は「島国日本」の短縮形で、日本のことではないだろうかと、このコラムで、私は述べました。その「島本さん」=「日本」が、20世紀後半の昭和の始まりを名前に持つ「始」に「これは私たちにとっての儀式みたいなものなの」と語っているわけですから、ここまで来てしまったやり方、つまり過去を振り返ることもなく、大切なものをどんどん捨てて、自然の山や海を破壊し、何も考えずに進んできて、バブル経済を推進し、そしてそのバブル経済が壊れるまでを生きてきた「私たちにとって」、そのような、これまで通りのやり方ではなくて、そのやり方と異なる生き方で結ばれなくてはいけないのではないかと、「島本さん」=「日本」が「僕」(戦後の昭和)に語っているということではないでしょうか。
「始」と「島本さん」が結ばれるには、2人が12歳だった時、「島本さん」の家でレコードを聴きながら、じっと手を握りあった時、まだ日本(島国日本=島本さん)に美しい自然が残っていた最後の年(1963年・昭和38年)に戻らなくてはいけないのです。
その時に、戻らなくては結ばれない、その時の「僕」(戦後の昭和)と「島本さん」(島国日本)に戻るための「私たちにとっての儀式みたいな」<普通とは逆のセックス>なのではないでしょうか。
あるいは、ここまで(昭和の終わりまで)来てしまった日本人の「私たち」が、このような20世紀後半の(戦後の)昭和の時代にしてしまったことへのお祓いの儀式としての<普通とは逆のセックス>なのだと思います。
☆
「僕は彼女の目を覗き込んでみた。僕は彼女の瞳に映った僕の顔を見ることができた」と村上春樹は書いています。「島本さん」=「島国日本」の瞳に「僕」(戦後の昭和)の顔が映っています。「僕」は、このような20世紀後半の(戦後の)昭和にしてしまった自分の姿をそこに見ているわけです。
これが儀式として<普通とは逆のセックス>を経た後、「島本さん」の瞳の奥に「仄かな光が輝いていた。それは生命の灯火のように僕には感じられた」と変化する理由だろうと、私は考えています。
そして、<普通とは逆のセックス>を経た後、「僕」と「島本さん」は<普通のセックス>で夜明け前まで何度か、優しく、激しく交わったのです。
☆
でも、「島本さん」は「僕の前から消えて」しまいます。そして『国境の南、太陽の西』は「僕」と「島本さん」が結ばれて終わりの物語ではありません。「島本さん」が「僕の前から消えて」しまって、終わりではありません。
仕方なく、「僕」が箱根から、妻・有紀子のもとに帰った後も、かなり長く、物語が記されています。この物語は次のような言葉で終わっています。
「僕はその暗闇の中で、海に降る雨のことを思った。広大な海に、誰も知られることもなく密やかに降る雨のことを思った。雨は音もなく海面を叩き、それは魚たちにさえ知られることはなかった。
誰かがやってきて、背中にそっと手を置くまで、僕はずっとそんな海のことを考えていた」
この「始」の「背中にそっと手を置く」のは誰でしょうか……。その推測を記すことはいたしませんが、私は、この最後の言葉に、とても「怖い」ものを感じました。
果たして、「始」は「島本さん」の瞳に映った自分の顔を見て、あの豊かな自然がまだ残っていた日本をしっかり記憶して生きていく人間となるでしょうか?
それとも、相変わらず、その場の都合で、大切なものをバラバラと捨てながら生きていくでしょうか?
「始」の背中にそっと手を置いた誰かは、「おい、どうなんだ」と読者に迫ってくるのように読めるのです。ここが最も怖い場面だと、私には感じられました。
☆
『国境の南、太陽の西』は1992年10月の刊行。1989年1月7日に「昭和」が終わって、最初に刊行された村上春樹の長編小説です。その小説は、戦後の(20世紀後半の)昭和の終わりまでを書いた物語なのです。村上春樹の「昭和」への時代認識、歴史認識をよく示している作品だと思います。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓
