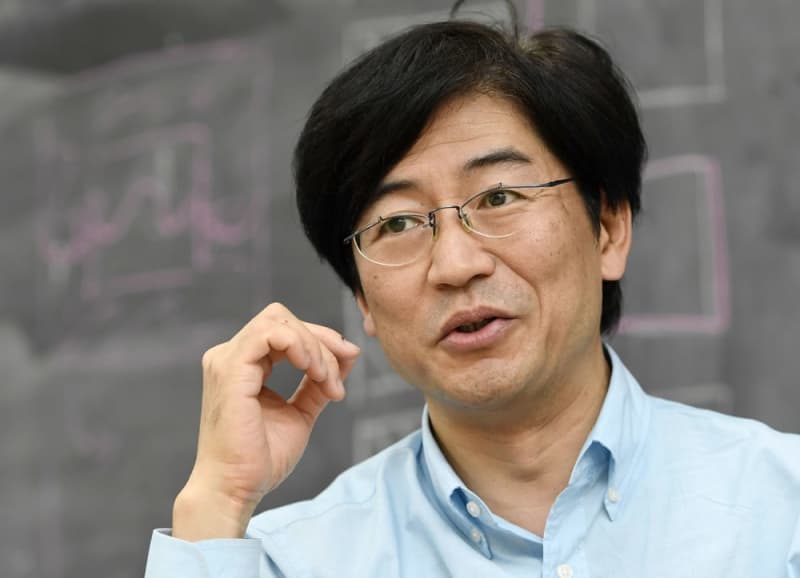
最先端のロボット工学や通信技術を駆使することで、人間が内在的に抱える限界を乗り越え、認識や行動の可能性を広げようという「人間拡張技術」が注目されている。世界の第一線で研究に取り組む東大大学院の暦本純一(れきもと・じゅんいち)教授に、技術の展望や社会に及ぼすインパクトを聞いた。(聞き手・共同通信=角田隆一)
―人間拡張とはどんな概念ですか。
人間は有史以来、眼鏡や車いすなどの技術を使って能力を加えてきました。研究では、人間の能力を技術によって自由に増強、拡張することを目指しています。高齢者や障害者の能力回復、時間や場所の制約をなくすことも対象となります。
―具体的にはどんな拡張技術があるのでしょうか。
大きく四つに分類できます。一つ目はパワースーツを使って重い物を持つといった「身体能力」の拡張です。義手や義足のように機械を使って身体の機能を補うものも含まれます。
二つ目は視覚や聴覚を補強する「知覚」の拡張です。視覚を失った人に他の感覚で視覚情報を伝えることなどを指します。
三つ目は遠隔地での作業を可能にする「存在」の拡張です。最近開発が進む遠隔操作ロボットもその一種です。
四つ目は何かを理解したり習得したりする「認知能力」の拡張です。私たちは泳いだり運動したりする姿を外部カメラで撮影すると同時に映像を本人に送る技術を開発しました。体外離脱という新たな視点で自分のフォームを点検でき、技能習得の助けとなります。いわば室町時代の能役者、世阿弥が示した「離見の見」で、客観的な視点で自らを見る意識を持つことができます。
これらの拡張技術は独立して存在しているわけではなく、複合的に組み合わせることで相乗効果を生み出す場合もあります。
―近年、障害者用のパワースーツや分身ロボットなど、さまざまな拡張技術が進展しています。どのような関連技術がこれを後押しするのでしょうか。
オランダの17世紀の画家フェルメールは、カメラの原型となる光学装置を使って作品を描いていました。この時代は機械やレンズが技術の中心でしたが、今はコンピューターの計算能力が加わりました。2000年代以降の通信の進化も重要です。ネットワークに人がつながることで、可能性が広がりました。
人工知能(AI)によって人間に能力を足せることが増えてきています。人間がサイバー空間と密接につながることで、人間拡張に新たな可能性が生まれています。
―AIが重要なのはなぜですか。
AIが人間に置き換わるという議論が目立ちますが、人間とAIの融合が進むという見方もあります。人間とAIの協調や相乗効果を高めるのも人間拡張における重要な視点です。
例えば、私たちが昨年10月に公表した「無音声インタラクション」という技術は「口パク」で相手に意思を伝えることができます。喉元に超音波エコーのセンサーを付け、口パク時の口内の動きを分析します。AIのディープラーニング(深層学習)を使って発話時の舌や筋肉の動きを数値化し、合成音声で再現する仕組みです。この技術を使ってスマートスピーカーなどと連携させれば、町の中で声を出さずに電話し、口パクでインターネット検索をすることも可能です。超能力のテレパシーと似ています。声帯を失った人も口の動きを覚えていれば、しゃべれるかもしれません。
―人間拡張によって今後どのような世界が訪れるのでしょうか。
将来的には、人の能力そのものがインターネットにつながる時代が来るかもしれません。例えば、すし職人やピアニストの技巧やこつといった属人的な職人技をAIで分析し、デジタル化した情報をネットで共有できるようになります。その技能を試したい人がダウンロードし、能力を補助する機械を使うことで、熟練の技を容易に習得できるようになり、新しい体験も可能になります。
―人間の個性の在り方にも影響しそうですね。
人間の働き方や交流の仕方、社会の構造も変化していきます。ある程度の高みまで技能の習得が容易になり、その先の高いレベルでの個性の発揮を競うようになります。
―海外でも同様の研究は進んでいるのでしょうか。
米国では存在の拡張の派生として、遠隔操作ロボやウエアラブル端末の軍事利用を想定した開発が進んでいます。航空機はドローン(無人小型機)に、兵士はロボやサイボーグに置き換わるでしょう。戦争に肉体を持つ人間が行く必要がなくなるかもしれません。これも人間拡張の一つの側面です。
―今後、突き詰めたい技術は。
取り組みたいのは、人間の深い思考やひらめきを助ける拡張技術の開発です。AIが絵画や文章を「創作」できる時代になりました。人間にしかできない創造性の発揮を促す技術を作りたいと考えています。人生を豊かにする鍵は創造力や「自分でやってできた」という感覚です。哲学的な問いだけでなく、道具やエンジニアリングの視角からも模索していきたいと考えています。(終わり)
関連記事はこちら
https://www.47news.jp/47reporters/3337278.html
