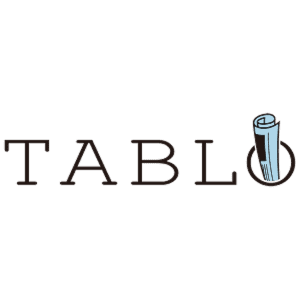一九七四年生まれの中村勇さんは熊本県阿蘇山で少年時代を過ごした。代々、阿蘇山で林業に携わってきた家に生まれ、勇さんの父も林業関連の会社を経営していたが、その職場は山でありつづけた。
阿蘇というと、私のような東京者はどうしても観光客の視点で、活火山である阿蘇山ハイキングや温泉などを思い浮かべがちだが、当然彼の地に根を張って暮らしている人々がいるわけである。
勇さんの生家が営む林業は阿蘇地域の地場産業であり、阿蘇地域林業担い手対策協議会ホームページ《ASOMON》によれば、二〇一九年現在、二つの森林組合と七つの林業事業体がある。
阿蘇山は杣山であり、古くから杣人も多く暮らしてきた次第だ。
さらに、阿蘇山は山岳仏教と修験道の霊場でもあった。私の観光客レベルの前知識には阿蘇で霊場といえば阿蘇神社しか存在しなかったのだが、かつては山上に三十七坊五十一庵を有していたというから驚きだ。
仏教の霊山としての阿蘇山は、一六世紀の島津氏対大友氏の争いが原因で、すべての僧房が撤退して一旦、終焉した。開祖は最栄読師とされ、七二六年に天竺から来朝して阿蘇山上で十一面観世音菩薩を刻んだという説と、最栄読師は比叡山慈恵大使の弟子で一一四四年に開山したとする説があるが、いずれにせよ阿蘇山は数百年間も仏教の霊場としての威容を保ってきたことになる。
その後、一五九九年に加藤清正の尽力で阿蘇山の麓に坊中(坊舎や宿坊の集合)が再興されて山上にも寺の本堂が建てられ、それが現在の天台宗西厳殿寺に繋がっているのだというが、山上の坊中が復活することはなかった。
中村勇さんが子どもの頃、生家の近くに、由来のわからない石の祠があったそうだ。ひょっとして古い坊中の遺跡だったら面白いのだが、今でも存在するかどうかはわからないのだという
勇さんが小学六年生の七月のこと。夏休み直前の土曜日の夜、二人の妹たちと共有している二階の子ども部屋で寝ていたところ、突然、何者かが、
「窓の外を見ろ!」
と、叫んだ。

目を覚ますと、まだ夜の一〇時。妹たちは眠っており、今聞いた声は、自分だけが夢の中で聞いたものに違いないと思った。しかし気になる。
そこで起きあがって、窓から外を眺めた。
勇さんが生まれる前に開通した国道が家の真ん前にあるお陰で、道路沿いの街灯が常夜灯代わりになっている。周囲には人家はなく、子ども部屋の窓から見えるのは、その国道と山ばかり。
――なんだあれは?
彼の家にとっては財産でもある杉林に覆われた山の中に、淡い水色の玉があった。柔らかく光っており、たいへんに美しい色合いをしている。
勇さんは、もっとよく見るために窓を開けてみた。ちなみに勇さんの家は祖父と父がすべて手作りした木造家屋で、窓は木枠で上下に開閉する仕組みで鍵はネジ式だ。ネジをキコキコと回して窓を開けると、夜気が頬を撫でた。標高が高いので、この辺りは夏になってもかなり涼しい。
さて、もう一度、目を凝らして水色の玉を観察してみたところ、国道沿いに生えた杉の梢に引っ掛かっているように見受けられた。地面から五メートルほどの高さにあり、直径三〇センチばかりの球体かと思われる。
室内を振り向くと妹たちはぐっすり寝入っていた。隣室に二歳上の姉がいるが、もう眠ってしまったようだ。両親も早寝早起きの習慣だからすでに熟睡しているのか、耳を澄ましても物音ひとつしない……。
――行ってみよう!
勇さんは好奇心を抑えきれず、パジャマ姿のまま、そっと家から抜け出した。
国道を横切って水色の玉に近づいてみると、思ったよりも大きく、一抱えもありそうで、球体全体が光っていた。ほぼ真下から見てもツルンと丸いばかりで、コードのようなものは付いていない。薄青色をした満月のようで、とても不思議な気がした。
五分ほどうっとりと眺めていたが、ハッと我に返って急いで部屋に戻り、寝直した。この一帯には熊や猪が棲んでいる。夜の山が危険なことは勇さんも知っていた。
翌朝、窓の外を見てみたら、水色の玉は消えていた。
父は仕事に出ていて、きょうだいはまだみんな眠っていたから、台所で働いていた母をつかまえて、昨夜のことを話した。
「夜に表に出たらいけん。ばってん、そりゃ夢なんやなかと? あんたが外に出たら、うちかおとうさんが目ば覚ましそうなもんや」
「夢やなか! 絶対違う! ほんなこつ見たんや」
「……どっちでもよかばい。それよりこん古高菜、食べてみぃ」
勇さんの母は彼の話を聞き流した。山での暮らしには保存食作りが欠かせず、高菜の古漬け以外にも、梅干しや紅生姜、各種の果実酒を作っており、父の会社の経理も担当していたから、いつも忙しかったのだ。
仕方なく、勇さんはひとりでまた外に出てみて、昨夜、玉があったところを見てみたが、変わったものは何も見つからなかった。
それからもしばらくの間、またあの玉が現れることを期待して注意していたものの、ずっと空振りつづきで失望し、夏休みが終わる頃にはどうでもよくなってしまった。
そして中学二年生から個室を与えられると、窓の向きが変わって、夜、部屋の窓から国道や山が目に入らなくなったので、本当に忘れてしまった。
――およそ五年の月日が流れた。勇さんは高校二年生になり、夏休みの間、麓の国道沿いにあるパチンコ屋でアルバイトすることにした。
そこは、高校で仲良くなった友だち・Aの家が経営しているパチンコ屋だった。Aの家に遊びに行った折に、Aの母から「うち人手が足らんけん、アルバイトせん?」と勧誘されたのだ。Aも一緒にやると言うので、学校には内緒で引き受けることにした。勇さんたちの高校は遊興施設や夜間のアルバイトを禁止していたのである。
家から山の麓までは約二キロで、自転車を使えばAのパチンコ屋に通うのはわけがなかった。家に帰宅するのはいつも深夜二時過ぎになったが、明るい国道を真っ直ぐ走ればいいだけなので安全だ。麓の辺りは、商店や人家、段々畑があり、家の辺りとは違い空が広く開けていて、誰もいない道を自転車で飛ばすのは爽快だった。たまにトラックが通ることがあっても、帰り道で人影を見かけたことはなく、世界を独り占めしているような気がした。
その夜は、とりわけ星空が見事だった。
トラックも通らず、人っ子ひとりいない国道をいつものように自転車で走っていると、前方に親子と思しき影が見えてきた。
気づいたときは一〇〇メートル以上離れていたが、自転車を漕ぐうちに徐々に接近していくことになった。最初は大小の人影から親子だろうと見当をつけただけだった。が、近づくにつれて細部が見えてくると、それが女性と五、六歳の男の子で、二人とも防空頭巾を被っていることが明らかになった。
中綿を詰めた布製の防空頭巾で、学校の防災訓練のときと、第二次大戦中を描写した映画や写真でしか目にしないようなものを、夏の盛りに人気のない山麓の道で被っているわけだ。
それだけでも奇妙だが、そのうち勇さんは二人が歩く動作をしていないのに、こちら向きに前進していることに気がついた。
二人とも国道沿いの街灯の光が届くところに立っているから、鮮明に姿が見える。手足を動かさず、手を繋ぎ、うつむいて佇んでいる……が、最初の位置から明らかに前に進んできている。そんな馬鹿な、と、自分の目を疑いながら勇さんはさらに近づいていった。
やはり二人は歩く動作をしていない。しかし接近してくる。
――うひゃあ。
怖くなって、勇さんは車道側に膨らんで二人を避けた。そして擦れ違った瞬間に二人がいた場所が暗くなったように感じ、自転車を止めて振り向いたところ、そこには誰もいなかった。
近くには人家も商店もなく、山があるばかり。夏のこの時期は、山には下生えが繁茂していて容易には足を踏み入れられない。
二の腕に鳥肌がびっしりと立っていた。うなじの辺りがツンと冷たくなって髪が逆立つ。必死でペダルを漕いで家に帰り、布団を被って朝まで震えていた。
それ以降、深夜にひとりで帰るのが恐ろしくてたまらなくなり、幸い怪しいものに遭遇したのはその一回きりだったが、夏休みが終わるとパチンコ屋のアルバイトを辞めてしまった。
勇さんが生まれ育った阿蘇の辺りにある有名な怪異譚は〝赤橋〟という通称で知られる阿蘇大橋――飛び降り自殺が多く、橋のたもとに〝まてまて地蔵〟というお地蔵さんが建てられている――にまつわるものと、西南戦争がらみのものが多く、防空頭巾を被った女性と子どもが登場する話は知らなかった。
勇さんだけに見えた幽霊なのかもしれない。しかし勇さんの家系には第二次大戦で死んだ母子の逸話などもなく、やはりよくわからない。
ただ勇さんは、このことがあってから、小学六年生のときに見た光る水色の玉について思い出したのだという。
どちらも家の前を通る国道沿いで起きた出来事なので、今も実家に帰るたびに記憶に蘇らせないわけにいかないとのことだ。(川奈まり子の奇譚蒐集・連載【二七】)