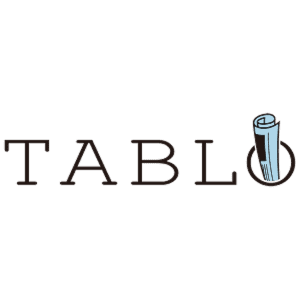スマートフォンが浸透したことで、いまや「アプリ」は私たちに欠かせないツールになっています。世界初のスマホは1992年のIBMの「Simon Personal Communicator」と言われていて、そこからノキアの「Symbian」とかブラックベリー社の「BlackBerry」なんかが黎明期を支えていくのですが、やはり日本人にとってのスマホといえば、2007年リリースのiPhoneと2008年リリースのAndroidでしょう。初めてアプリを利用したのも、iPhoneのAppストアか、AndroidのGoogle Playストアという人がほとんどじゃないでしょうか。
今回は「スマホアプリ」についての考察です。
ちなみにアップルがiPhoneをリリースした2007年にAppストアは存在せず、同社のプリインストールアプリのみ利用できる状態でした。そのなかで「Nightwatch」と名乗るハッカーが「Hello World」というアップル非公認のアプリを開発しています。その機能はただiPhoneの画面に「hello, world」という文字を表示されるものでしたが、これが今では当たり前になっているサードパーティーアプリの走りです。そして、iPhoneのAppストアは2008年7月1日、AndroidのAndroid Market(現Google Playストア)を公開して、さまざまなアプリが登場していくことになりました。
そんなアプリのなかでも、日本に大きな影響を与えたものといえば「SNS」でしょう。とくに“サクッとスマホで”というメリットが大きいアプリといえる「Twitter」と「LINE」は、私たちにSNSの意識を根付かせる原動力となりました。“既読スルー”なんかが社会問題になったのが懐かしいですね。
両方ともに情報の発信と受信を行えるツールですが、リリースされた当初は、Twitterは1対多数で拡散性が高く、LINEは1対1で秘匿性が高いという点で人気を集めることになります。それまでにも「2ちゃんねる」とか「mixi(ミクシィ)」など、ウェブのコミュニケーションツールはたくさんありました。しかし、やはりリリース当時はPCメインということで利用できる人のハードルは高かったように思えます。そのなかで、TwitterやLINEは登場時にスマホという手軽なハードで利用するのがメインだったこともあり、より多くのユーザーに浸透できたのではないでしょうか。
また、「手軽」という意味でいえば、〝映像〟によるコミュニケーションツールの「YouTube」もTwitterやLINEに並ぶSNSアプリです。ただ、こちらは情報の発信よりも受信にウェイトが大きいのが現状。情報を発信する側のユーチューバーが大ヒットしていますが、多くの人たちにとって動画の視聴がメインではないでしょうか。とはいえ、“見ればいいだけ”という手軽さと無料というコスパで、文字から映像に情報の幅を広げたのはYouTubeの功績と言えます。
ちなみに、リアルな数字はどうなっているかというと、SNS系のサービスやアプリの利用率について調べたのが次のグラフ1とグラフ2です。グラフ1は各アプリごとの利用率推移で、LINEは他アプリの追随を許さないほどの浸透ぶりを見せています。グラフ2は年代別の利用率比較ですが、どの年代でもLINEとYouTubeは圧倒的に強いことがわかりました。
これはちょっと先述しましたが、LINEは1対1のトークを土台とする秘匿性に特徴があり、YouTubeも“見るだけ”でメリットが大きいツールです。この“閉じられた”コミュニケーションという部分が奥手な日本人に合っているのかもしれません。
このように社会を変えるようなアプリばかりではありませんが、いまもアプリはどんどんと登場しています。そのなかでも最近話題になっている技術といえば、やはり「AR(拡張現実)」です。具体的には、現実世界の情報をもとにデジタル情報を重ね合わせ、視覚的に現実を拡張すること。良く分からない人も多いと思うので、ものすごく端的に言うと見えないものが見えるようになる技術と考えてください。例えば、大ヒットしたスマホゲームの「ポケモンGO」は本来見えないはずのモンスターが現実から取り込んだ風景の中に見えるようになっているでしょう。それのことです。
ゲームのほかにも、自分の部屋を撮影して取り込み、そこに仮想の家具を配置してサイズやスペースを確認するアプリなんかも人気を集めています。また、ARと教科書を連動させて、タブレットなどのメディアで図形や生物などの構造を立体的に見られる「AR教科書」なんかも登場。まだまだ何ができるのか手探り状態ですが、新しい技術や発想で驚くようなアプリが登場するかもしれませんね。(文◎百園雷太)