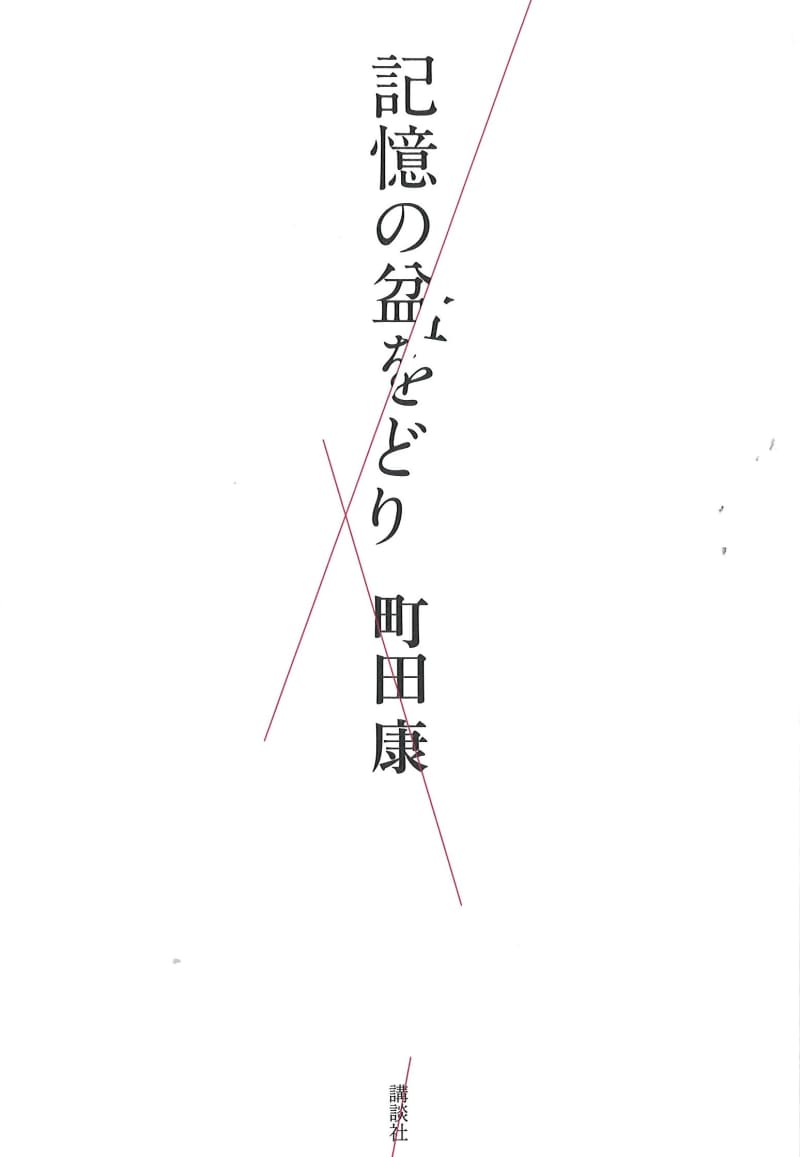
思うに任せぬ状態になることは、誰の日常にもよくある。その一つが本書の表題になっている「記憶」で、必要なことを思い出そうにも像を結ばず、もどかしさが増すばかりということを繰り返す。とうとう思い出すのをあきらめて「ああ、もうっ」といやになる。自分のことながらあきれるが、いくらいやになっても「私」「自分」というやつは決して頭の中から離れない。町田康の小説には、この思うに任せぬ不如意と「私」が描かれていて、吸引力がめっぽう強い。現れる人物は珍妙にも滑稽にも思えるが、はっと気付く。ここに書かれている自意識のうねりは、今、本を読んでいる自分の心と重なっているのではないか。
言葉とリズムが転調、変調を繰り返す町田独自の文体は笑える、でも痛い。痛い、でも笑っている。この短編集の9編も痛点と快いツボが刺激される。
「記憶の盆おどり」の語り手は、記憶があやしくなって断酒をしている作家。突然、自宅に美しい女が訪ねてくる。昔、捨てた女と同姓同名だが、年は若い。記憶にはないが、どうやら原稿を書く約束をしていたらしい。帰ってもらおうと妻に頼むと「頭取に会う」と言って出掛けてしまった。何の話だ、と作家はさっぱり覚えていない。語り手が知らないのだから、作中でも説明されない。そうするうちに作家は女のペースにずるずると陥っていく。不如意の中で、薄もやのような作家の意識がのたうち回る。
ほかの作品でも思いも寄らない珍妙な境遇に放り込まれた人間たちの、やむにやまれぬ言動に引き込まれる。突然、エゲバムヤジという生き物を押しつけられた男(「エゲバムヤジ」)、見知らぬ男に才能を売り渡した売れないギター弾き(「百万円もらった男」)、絶対走らないことを条件に結婚した夫婦(「ずぶ濡れの邦彦」)…。
これら「不如意と私」が頭の中でぐつぐつと煮えるさまを、はらはらしながら読む。2005年の長編「告白」で町田は人が人をあやめる衝動と破滅を実に深く、説得力を持って書き切ったが、今回の短編集でも登場人物(ある1編では人ですらない)をぎりぎりまで追い込んでみせる。そこにあるのは不如意に囲まれた人間の哀しさと笑うしかないカタルシス。だから町田康を読みたくなるのだ。
(講談社・1700円+税)=杉本新

