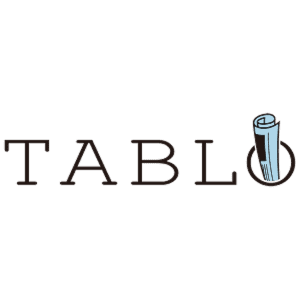写真はイメージです
今、最大の情報収集源がなにかといえば、若年層では圧倒的にネットであろう。しかし、令和になった今でも思い出すのが平成9年(1997年)の「神戸連続児童殺傷事件」加害者の酒鬼薔薇聖斗(後に「少年A」)の顔写真をなんとか見ようとした騒動である。
雑誌メディアが注目されていた
写真は新潮社が発行する写真週刊誌『FOCUS』に掲載されていたものだが、当時は14歳の未成年者の顔写真と実名を出していいのか、という議論が発生。新潮社は公益性があると判断をし、強行。回収をすることもなかった。1981年にFOCUSを立ち上げた斎藤十一氏は創刊にあたり、「君たち、人殺しの顔を見たくはないのか」と部下に言ったとされる。16年後にもそのイズムを引き継いだ形となったが、同誌は2001年に休刊となる。
話は酒鬼薔薇に戻るが、当時私は新入社員として入社2か月ほどの時期だった。学生時代に週刊誌を読む習慣はなかったのだが、先輩社員や同僚の派遣社員らが「『FOCUS』見た?」「まだ見てないの! 誰か持ってないの!?」なんて興奮をしていた。隣の部署に一部あることが分かるとそれを借りてきて皆で「うわーっ! こんな顔してるんだ」「なんか陰があるタイプの顔よね……」なんて話し合っていた。
それだけ雑誌というメディアが注目されていた時代だったし、人々の気持ちを揺さぶる存在だったのだろう。今でも「雑誌が起こした波紋」を考えた場合は、この騒動と2000年の「噂の眞相」編集部への右翼団体襲撃事件を思い出す。
また、私は学生時代から自分が通う大学の職員とよく遊び、彼の家に行っていたが、彼は毎月「GON!」(ミリオン出版)というサブカル誌を読むのを楽しみにしていた。彼がある日興奮しながら見せたのが「胎盤をステーキにして食べた」という企画だ。あとは、タイの新聞から転載した交通事故死体の写真にも興奮していた。
しかし、それからそれ程先ではない2004年、ネットがかなり普及し、グロ画像や無修正画像がネット上には多数存在していた。イラクで人質になった香田証生さんの首が斬られる動画なども当時、会議などでネットについて喋っている時は話題となった。その時も酒鬼薔薇の時と同様に「あれ見た?」「いや、恐ろしくて見られない」などと喋っていた。
そんな私も2001年に会社をやめ、フリーライターになった。雑誌制作にかかわることとなったのだが、ほとんどはライターとしての関与のため、Wordで書いた原稿と撮影した写真とイラスト、エクセルで作った表などを編集者に送るだけで後は編集者がデザイナーと相談のうえで、誌面に展開していった。
「写植」で雑誌を作っていた時代
そんな中、自分も編集をやってみたくなり、雑誌「テレビブロス」の編集部に売り込みの電話をしたところ、運よく編集長が出てくれ、そのまま採用となった。当時の雑誌制作についての記述をWikipediaから引用する。これは「電算写植」という項目の「2000年代以降」という部分だ。
〈大規模出版においては2000年代頃まで電算写植が使われていたが、1999年にQuarkXPressを上回る機能を持つDTPソフトウェアAdobe Indesignが発売され、Adobe Indesignの機能向上が進むにつれて、大規模出版を含むほとんどの出版がAdobe IndesignベースのDTPに置き換えられた。〉
というわけで、当時の主力だった雑誌作りの方法とは、編集者が「ラフ」と呼ばれる誌面の設計図と原稿、イラスト、表、写真(以下「素材」)をデザイナーに渡し、彼らがIndesignを使い、文字を入れた形でPDFを編集者に戻す形で作っていた。これを「データ入稿」という呼び方をしていた。
一方、ブロスの場合は「写植入稿」と呼んでいた。手順は以下のようになる。
【1】原稿以外の素材とラフを持ってデザイン会社へ。配置や強調したい部分等について打ち合わせをする。
【2】翌日ないしは2日後にデザイナーが該当ページの文字以外の「素材」が入ったデザインを送ってくる。ただし、タイトルや見出しなどはこの段階で入っている。ここではあくまでも配置と文字数、フォント、級数が決まる。微修正をしてもらう。
【3】このデザインを基に原稿を書き始める。もしもはみ出てしまった場合は「文字の級数を小さくする」ないしは「平体・長体にする」という技を駆使して強引に文字を増やす。これは後に印刷会社で指定する。
【4】月曜日夜:編集部に集合。編集者が一斉に「入稿」作業を行う。デザイン会社からは修正したデザインが編集部に届いている。自分の担当ページを抜き出す。テキストを印刷した紙に「あ」や「い」「A」「B」などと「相判」を振り、デザイン用紙にも「あ」などと入れて「この原稿はここに入りますよ」を印刷所のオペレーターに対して分かるよう加工をする。夜が遅くなってくるとデザイナー軍団も編集部にやってくる。火曜日朝6時までにビル1階の守衛所にすべての素材とデータの入ったフロッピーディスク、CD-R、指示書(作業したもの)を封筒に入れて渡す。
【5】火曜日夜:大日本印刷の「出張校正室」へ。編集部ごとに部屋を持っており、ここでようやくデザインに文字が入った状態のものを見ることができる。事実関係の修正をしたり、はみ出ていたりした場合は、級数をさらに小さくする、などの指示を印刷所に対してする。この段階で初めて入るテキストや写真もあったりする。ただし、印刷所はあまりそれを喜ばない(当たり前か)。
【6】水曜日夜:「念校」のために再び大日本印刷へ。この日は「青焼き」と呼ばれる、「印刷見本」的なものが渡される。最後の最後、チェックをするのだ。印刷所の人は「まぁ、文字を少し直す、ぐらいでしたらいいですが、大きな変更はナシでお願いします」と言う。
【7】無事終了し、大日本印刷の敷地外にある酒屋で印刷会社の人々が外で立ち飲みをしているのに混ざって一緒に酒を飲む。
【8】翌日テレビブロス発売。それから1週間は抗議電話が来ないかを祈るとともに、早くコンビニから消えてくれ~と願う。さすがに抗議は1週間以上過ぎると来なくなる。
他の編集部はすべて「データ入稿」だったため、大日本印刷に編集者は行く必要がなかった。2週間に2晩、市ヶ谷まで行くのは正直キツかったが、編集長曰く「写植入稿の方が味わい深い」とのこと。さらに「デザインが自由」とも言っていた。
今やネットに原稿を入れる時代になっただけに、あの頃、細かいデザインにこだわりまくり、いかにアホなレイアウトができるかに血眼になっていた時代を思い出す。(文◎中川淳一郎 連載『俺の平成史』)