
樺美智子の死因については、圧死説と扼死説があり、60年を経た今も謎のままである。圧死であれば、国会構内でのデモ隊と警官隊の衝突の中で、デモの隊列が崩れ、下敷きになったことになる。首を絞められた扼死であれば、加害者は故意の殺人罪に問われよう。
死後約3時間半後、6月15日午後10時42分から検視した監察医の渡辺富雄は「圧死の疑い」とした。ただし、父親に渡す死亡届の用紙には死因を「不詳」と書いている。当時の週刊誌への寄稿で、父親に「圧死の疑い」とするのは「忍びがたく」と説明したが、医師が死因を虚偽記入する理由としては、説得力がない。
司法解剖は翌16日。遺体は慶応大法医学教室に運ばれ、中館久平と中山浄が執刀した。その前半だけ、東大医学部教授上野正吉も同席した。
中館の鑑定書は、扼殺されたとも、そうでないともいえるというあいまいな表現だった。傷害致死の疑いで捜査していた東京地検は、上野に再鑑定を依頼する。再鑑定の結論は、警察官との接触はなく、デモ隊の人なだれの下敷きになった窒息死、つまり圧死だった。
これに対し、解剖に立ち会った社会党の参院議員で医師の坂本昭の見解は扼死。現場の写真や証言を集め、樺のいたデモの先頭近くでは「人なだれはなかった」と断定する。さらに、膵臓と頸部に出血があったことから、警棒で腹部を強く突かれて気を失い、首に手をかけられて窒息死したと結論付けた。
坂本は参院法務委員会で法務省を追及、死体検案書と中館・上野の鑑定書の公開を求めるが、法務省は拒否した。
近年まで扼死を主張し続けた人もいる。医師で詩人の御庄博実(みしょうひろみ、本名・丸屋博)は、執刀した中館のプロトコール(口述筆記)を伝染病研究所(現・東大医科研)の草野信男に届け、草野の所見をまとめた。「扼死の可能性が強い」という内容だった(「樺美智子さんの死、五十年目の真実―医師として目撃したこと」(『現代詩手帖』2010年7月号など)。御庄は2015年に亡くなっている。
わたしは関係資料を調べ、国会構内に入った樺の学友たちに会い、坂本の遺族や御庄にも取材した。その結果、扼死の心証を得たが、決定的な証拠がない。真相を明らかにするため、死体検案書と2つの鑑定書の公開が望まれる。

扼死か圧死か。決定的な証拠がないのに、圧死と思っている人が少なくない。ネット上の百科事典『ウィキペディア』の「安保闘争」の項も、圧死と断定して記述する。これには当時の新聞報道も影響しているのではないか。
樺が死亡した翌朝、6月16日の朝日と毎日がそろって、樺の隣でスクラムを組んでいたという明治大学生の証言を載せた。警官隊とぶつかり、うしろから押してくる学生集団に圧迫されて人なだれが起きた。樺は学生のドロ靴に踏まれて死んだというリアルな証言である。週刊誌などもこの学生の話を載せた。
しかし、住所氏名まで出ているこの学生は実在しないことが判明している。捏造(ねつぞう)された証言である可能性が高い。誰がどのような意図で証言したのか。
父親の俊雄は、60年1月の羽田ロビー闘争で娘が検挙されたときは、彼女が学生運動に深入りしていることを知らずに『全学連に娘を奪われて』(『文藝春秋』3月号)を書き、全学連を批判したが、このころには娘の行動に理解を示し、新聞報道に厳しい目を向けている。

『中央公論』60年8月号には「体験的新聞批判」を寄稿し、娘の死を伝える6月16日の朝日新聞朝刊を例に検証した。
11版社会面の見出し「学生デモに放水」が、12版では「デモ隊警察の車に放火」にかわる。11版の「まるで野戦病院」は学生の負傷者の惨状を報じるが、12版でこの記事が消え、13版では「暴力は断固排す」という政府声明が加わる。
早版と遅版の違いは、第一線の取材記者のなまなましい現地報道が、上級幹部の意図に反するからだと分析している。
幹部の意図の浸透を示すように、各新聞の論調が政府の主張と軌を一にして暴力追放を強調するようになり、6月17日朝刊では東京に拠点を置く主要7紙が「七社共同宣言」を掲載。「理由のいかんを問わず、暴力を排し、議会主義を守れ」と呼びかけた。
中央公論で俊雄は、この宣言文の「その依ってきたる所以は別として」を挙げ、混乱の根本の原因である政府・与党の非民主的な行動(国会に警官隊を導入した強行採決など)を不問に付していると指摘した。
また「暴力ということについていうならば、単にデモ隊の暴力だけをとり上げるべきではない」。武装警官が「非武装の国民大衆のデモ隊にむかって行使した暴力」こそ糾弾されるべきだと述べている。説得力のある議論を展開した。
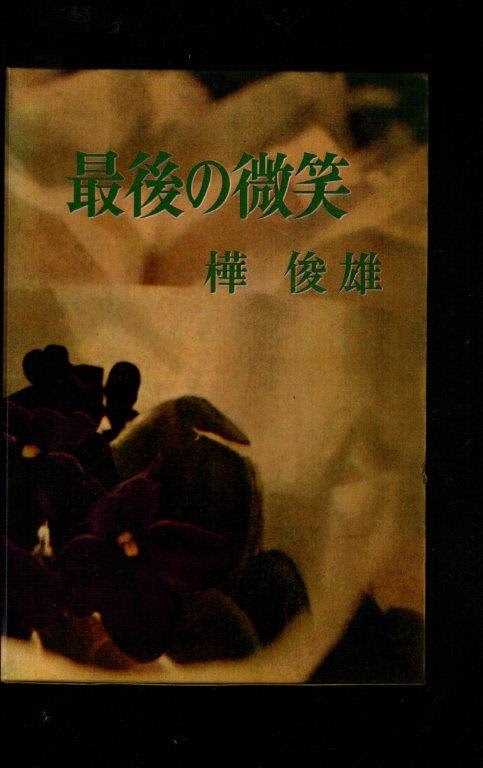
同年9月刊行の『最後の微笑』では、官の責任について次のように述べる。
「娘の死という事実について、自分にその責任があると申し出られた人が一人も現われないのはおかしいという気持ちです。虐殺にしろ、事故死にしろ、ああいう公けの事件で、公けの場所で死んだのでありますから、その公けの立場にある誰かが、娘の死について哀悼の意志を表明してもいいのではないでしょうか」
「娘のとった行動が法の秩序を破るものであったとしても、娘が死んだという事件はまた別の事実であります。かりにその死が事故死であったとしても、そこに出動していた多数の警官にはその死を阻止する義務があったのではないでしょうか」
父の視点は、直接の関係者・関係当局の責任だけでなくもっと深い所まで届く。「それらの関係当局をこえた岸内閣の政治的意向が表れていると思われてなりません」
俊雄は1980年に亡くなるが、最晩年まで一貫して、娘は警官に扼殺されたと主張している。(敬称略、肩書は当時、女性史研究者=江刺昭子)

