東京2020大会で悲願のメダルを! パラ陸上・走り高跳び 鈴木徹選手
6度目の正直。勝利のカギは“笑顔”
’00年、初の日本人走り高跳び選手としてパラリンピックに出場した鈴木徹。その時から6大会連続となる東京大会で悲願のメダルを目指す。4年に1度の大舞台を控えた今、あらためてこれまでの経緯と現在の心境を語ってもらった。

鈴木徹は事故に遭う以前の幼いころ、ある障害を抱えていた。
「幼少期に心臓病と吃音症があったんです。脈拍数は一般の人の半分ほどしかなく、スポーツをやりたくてもできなかった。吃音症は、妹が溺れてしまって母親に助けを求めたときに、突然言葉が出なくなったんです。今はこんなに話しますが、当時は話すことをやめていました。僕が話すと嫌なことしか起きなかったので。でも、小学校のころ、球技でシュートを決めると、みんなが『すごい』と言ってくれた。だから自分はスポーツ選手にならないといけない、と思いました。“なろう”ではなく、“ならなければいけない”と。心臓は高校生のころにはスポーツ心臓になったので、命に関わることもなくなった。部活でやっていたハンドボールも、どんどんやっても構わないと。僕は、2つの病気を持っていたことで、自分を表現する方法がスポーツだと決められたんです」
事故後に走り高跳びを始めたのも、自然の流れだった。
「中学3年の時に県で2番ぐらいの記録を出していました。事故の後、リハビリの合間に走り高跳びをやってみたら記録が出た。僕は日本代表だったらなんでも良かったので、五輪よりは陸上でパラリンピックの方が日本代表は近いと思った」
その後、順調に走り高跳びで記録を伸ばしていくが、あるとき壁にぶち当たったという。
「始めてすぐ、記録が190㎝ぐらいまで一気に伸びたのですが、その後ですね。大学生になって普通にやっていれば記録は出るだろうと思ったけど伸びない。コーチと出会って基礎を教えてもらうことで2mにたどりつきましたが、競技を始めて6年後のことでした。その間に一番苦労したのは足の切断面に傷ができること。義足はカーボンの硬い素材でできているので摩擦などで傷ができてしまう。そうなると義足もつけられず、歩くこともできないんです。当時は練習をしては傷を作り、治ってはまた傷を作りの繰り返し。だから練習メニューも決められず、その日にできることをできるだけやるという練習でした。今は慣れましたが、当時は精神的にキツかったです。メニューを作ってもその通りにできず、葛藤もありました」
リオでのパラリンピックはメダルを確実視されながら4位。敗因はメンタル面だという。
「集中することで自分を苦しめてしまいました。メダルを取りに来たのに、早く終わらないかなと思って、競技を楽しめなかったんです。それまでは普通にやれば結果を出せていたので気楽だった。それがメダルを取って当たり前、という雰囲気が自分にもあって、普段とは違うことをしてしまったんですね」
メンタルトレーナーで精神面を強化、今年から新たな義足に変えてパラリンピックに挑む。
「調子がいい時は試合中も笑顔なんです。それを意識したり、他の選手とコミュニケーションをとるようにしたり。また、義足を日本製にして、硬さなど細かいところをオーダーできるようにしました。義足は野球で言うバットと同じ。つけた時の感覚が重要なんです。まだ微調整をしていますが、春には義足を決めてトレーニングに集中し、東京でピークに持っていきます」

【TVガイドからQuestion】
Q 好きなテレビ番組は?
「ガイアの夜明け」とかテレビ東京の番組をよく見ます。ドキュメンタリーのようなリアルな番組が好きなんです。「アナザースカイⅡ」(日本テレビ系)も見ます。自分も出たいと思って場所も決めています(笑)。ドラマはほとんど見ないのですが、木村拓哉さんの作品だけは見ています。「グランメゾン東京」も全部見ました。僕は木村さんの作品を見て育った世代。カッコいいなと憧れているので(笑)。スポーツはテレビではあまり見ないですね。経営者向けの番組とか、紀行ものなどをよく見ています。
【プロフィール】
鈴木徹(すずき とおる)
1980年5月4日山梨県生まれ。牡牛座。AB型。高校までハンドボール部に所属。国体で3位入賞。高校卒業直前の交通事故で、右足膝下11cmを残して切断。リハビリをきっかけに始めた走り高跳びで記録を伸ばす。’00年シドニーからパラリンピック5大会に連続出場。’12年ロンドン、’16年リオで4位入賞。
【プレゼント】
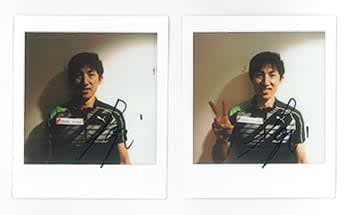
サイン入り生写真を2名様にプレゼント!
ハガキでの応募方法は「TVガイド」3/27号(P110)をご覧ください。
「TVガイド」の購入はコチラ→https://zasshi.tv/category/TVG
取材・文/田村友二 撮影/為広麻里
