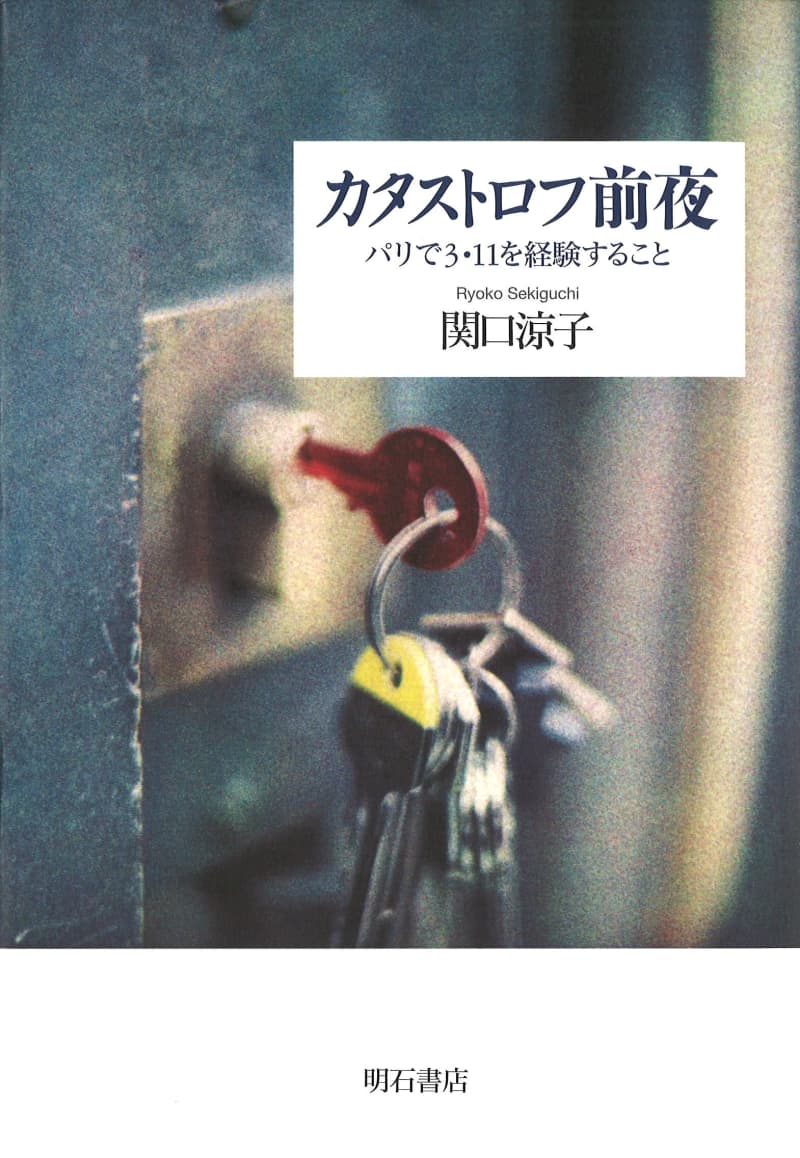
息苦しい春の中にいる。言うまでもなく新型コロナウイルスの感染拡大のせいだ。閑散とした街を歩きながら、自然と9年前の春を思い出している。東日本大震災による揺れと津波、それに続く原発事故。2011年春に感じていた不安はどんな色で、どんな形をしていたか。
そんな中で本書に出会った。のめり込んで読んだ。あの春に感じた息苦しさが、その深さがよみがえった。あれは絶望に近い感覚だった。世界の終わりの始まりだと感じていた。
著者の関口涼子はフランスに住む著述家で翻訳家、詩人でもある。本書には東日本大震災に関する作品が3編収められている。どの作品も最初はフランス語で書き、それぞれ出版したものを、関口本人が翻訳した。
冒頭の一編「これは偶然ではない」は、クロニクル形式で書かれており、11年3月10日から始まる。この日の記述は短く、日常がさらりとつづられる。11日午前零時頃もまだ平穏の中にいる。迂闊にも、日常が続くのだと信じていた、あの時。カタストロフ前夜である。
11日午前8時頃以降の記述は長い。日本で大きな地震があったとフェイスブックで知る。神奈川県の実家に電話するが誰も出ない。父母の携帯電話にかけるが通じない。弟の携帯もつながらない。回線がパンクしているのかもしれない。
津波の映像を見る。原発が気がかりだという情報も得る。フランスにいる日本人の知人が集まってくる。みんなでウェブサイトのNHKをかじりつくように見る。テレビでニュースが流れるたびに不安にかられ、みな家族に電話をするがつながらない。
「この光景をすでに見たことがある」という既視感に襲われる。地震や台風などの数えきれないイメージが重なってゆく。
3月14日の記述。「テレビに釘付けになっている時にわたしたちが相対しているのは、波や風、炎の映像だけではない。それは、生きている人がその中に存在する、生の瞬間なのだ」「このたびばかりは、この本がハッピーエンドで終わりますようにと願わずにはいられない」
この災害がフランスでどう見られているか。日本人の礼儀正しさへの称賛もあれば、原発事故を招いたことへの非難もある。この状況下で日本人が相変わらず職場に通うことに呆れ返っている人たちもいる。そうしたまなざしが、日本人である関口を襲う。マイノリティーとしての日本人が、大量の、容赦のない言説の客体になる。
3月25日。「ハッピーエンドは不可能だ」「いまだ終わりを知らないこのカタストロフの真っ只中にいながら、何かがすでに損なわれたと知っている」
このような筆致が変わるのが4月上旬だ。筆者は帰国するため、飛行機に乗る。日本に着き、街を歩くことで、どのように心境が変化するのか。4月27日には「安らいだ心持ち」にすらなるが、それはなぜか―。
本書のタイトルを「カタストロフ前夜」としたのは、「わたしたちは常に二つのカタストロフの間に身を置いて」いるからだという。カタストロフに終わりは存在せず、いま、この瞬間は次のカタストロフに対する前夜だとすれば、本書は「警告の書」でもある。
3.11のとき、海外にいた人の中には、永久に日本に帰れず、故郷を失ってしまうと恐れた人もいたと聞いたことがある。遠い場所に身を置いた者であるがゆえに見えるものがあるだろう。
この大震災の被災者とは、当事者とは誰だったのかという問いが浮かんでくる。私は9年前の春、大阪にいた。被災地から離れていたし、親族が亡くなったわけでもない。だから自分が被災者だと思ったことはないが、日常が大きく揺さぶられ、精神的なダメージは大きかった。もっと離れた場所にいた関口もまた、この災害を身近に感じ、地震とは別の大きな揺れに、魂を揺さぶられている。
被災の程度は“グラウンド・ゼロ”から同心円状に広がっているわけではない。カタストロフを自分の身に引き寄せる手立てを、本書の中に見る。
(明石書店 2400円+税)=田村文
