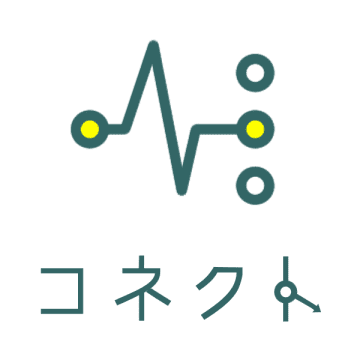天才打者が明かす名投手の記憶、「力の入れ方が違った」宿命のライバル掛布との対決
読売巨人軍史上屈指の好打者で通算1696安打をマークし、守備でも名二塁手として鳴らした篠塚和典氏(1992年途中までの登録名は篠塚利夫)。Full-Countでは、天才打者が現役当時を振り返る連載「篠塚和典、あの時」を掲載中。今回は、巨人のエースで“昭和の怪物”の異名を取った江川卓氏の記憶を語る後編だ。
江川氏は1979年から87年まで9年間、巨人一筋でプレー。まさに“太く短い”野球人生だった。2度の最多勝を含め、9年中8年で2桁勝利を挙げ、通算135勝。年平均15勝は驚異的だ。1年目の79年だけは9勝(10敗)で10勝ラインに届かなかったが、この年は、入団を巡る“空白の1日”騒動の責任を取る形で、公式戦開幕から約2か月間も出場を自粛したハンデがあった。右肩の故障を理由に現役引退を表明した87年でさえ、13勝5敗、防御率3.51の好成績を挙げている。
76年から94年まで19年間も巨人でプレーした篠塚氏は、江川氏の現役時代の投球の大部分を、二塁の定位置から見ていた。特に印象的だったのは、江川氏の極端な“ギアチェンジ”である。
「立ち上がりは様子見というか、守っている側からすると、手を抜いているように見えました。ただ、抑え気味に投げても、簡単には打たれませんでした」と笑う。そして走者を得点圏に背負うと、ガラリと豹変したという。「走者なしとか走者一塁の時とは、体の張りが違うと感じました。江川さんはスコアリングポジションに走者が行くと、背中に張りが出る。守っていて『これは強い球を放りそうだ』と感じましたよ」
絶妙のペース配分、メリハリで“勝てる投手”として君臨した江川氏。篠塚氏は「当時は、『完投するのがエースの役目』と思われていた時代ですから、打者9人全員に全力でいくわけにはいかない。時には手を抜き、クリーンアップに対しては全力で、という組み立てだったと思います」と説明する。
もし江川氏と対戦していたら…「そりゃ、真っ直ぐしか狙いません」
だが、そんな江川氏が、序盤だろうと大差がついていようと、全球全力で立ち向かった打者がいた。「阪神の掛布(雅之)さんですね。確かに掛布さんの時だけは、最初からトップギアに入れている雰囲気を感じました。1球で、力の入れ方が違うのがわかりました」と篠塚氏も証言。巨人のエースと阪神の4番は1955年生まれの同い年でもあり、2人のライバル対決はファンを魅了した。
圧倒的な力量を示した江川氏だが、球種はストレートとカーブの2種類しかなかった。「バッターにとっては読みやすいですよ。江川さんは、相手がストレートにタイミングを合わせて待っているとわかっていても、“打てるものなら打ってみろ”という感じで真っ直ぐを投げ込むことがありました」と篠塚氏。それでも江川氏のストレートは、たとえ完全にヤマを張られていたとしても、篠塚氏が前編で語ったように、「打者からは、まるでホップしているように見える」球質ゆえ、簡単には打たれなかった。
もし、篠塚氏が敵として江川氏と対戦したら、どう攻略したのだろうか。「そりゃ、真っ直ぐしか狙いません。でも実際のところ、同じチームでよかった、という感じですよ」と脱帽するのだった。
「江川さんが投げる球は、キャッチボールからして違っていました。短い距離から段々伸ばしていって、いちばん遠くから投げてもまだ回転がいい。遠くから見ても、回転の良さがわかりました。そういう回転があったからこそ、打者にホップする印象を与えたのだろうと思います」と篠塚氏は振り返る。“昭和の怪物”は強者ぞろいのプロの世界にあっても突出した、唯一無二の投手だった。(宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki)