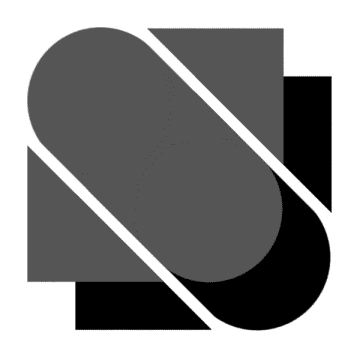大物選手の移籍やリーグの盛況ぶりが近年たびたび話題となるアメリカのMLS(メジャーリーグサッカー)。
新型コロナウイルスの流行により彼らもサッカーどころではない日々が続いていたが、先日、2020シーズンの再開日程が発表された。
しかもそのやり方は日本のJリーグなどとは異なり、全26チームが一ヶ所に集まっての集中開催!
各国が検討しながら最終的に採用しなかった(できなかった?)大会方式をMLSは選択した。
そこにはどんな狙いや背景があるのか。
アメリカのスポーツビジネス事情に詳しい、Blue United Corporationの中村武彦代表に、MLSを含むメジャースポーツの現在の状況、さらには一大ビジネスであるアメリカのスポーツ産業の今後などを聞いた。

サッカーが先陣、7月8日再開
――MLSの再開日が決まりました。フロリダ州オーランドでの集中開催とのことですが、具体的にどのような形で行われるのでしょうか?
MLS全チームがフロリダ州オーランドのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある「ESPN Wide World of Sports Complex」を利用して一ヶ所集中開催をします。
形式はワールドカップをイメージしていただければと思います。全26チームが6つのグループに分けられ、7月8日より16日間にわたり予選ラウンドを開催。7月25日にベスト16、8月1日にベスト8、8月6日に準決勝、そして8月11日に決勝戦が開催予定です。
優勝チームは北中米カリブ海地域チャンピオンズリーグへの出場権を得ると同時に優勝賞金約1.1億円を獲得します。また、この後9月よりコロナの状況を見つつ、レギュラーシーズンも再開予定で、この一ヶ所集中開催で戦った試合数はリーグ戦に換算されます。
なお、この一ヶ所集中開催期間は選手・スタッフともにディズニーを特別な理由がない限り離れることは禁止されています。
――MLSは2節を終えた3月上旬にリーグを中断しました。今回、こういった形での再開を決断した背景などがあれば教えてください。
コロナの状況がまだ予断を許さない中で、通常のリーグ戦再開にはまだリスクが高く、州ごとに法律によっては屋外活動への制限もまちまちです。
アウェー戦への移動などの安全面を考慮、それらのリスクを最小限にしつつ、選手・スタッフ・ファンの健康状態を鑑みて、最大限に感染しないようにコントロールできる方策としてこの大会が考案されました。
――なぜ、オーランドが集中開催の地に選ばれたのですか?
全26チームの選手・スタッフを一ヶ所に集めるための宿泊施設、そしてこれだけ多くの試合を開催できるフィールド・施設を備えているためです。
もちろん、広大な敷地を保有するアメリカですので、ここ以外にも類似した施設は幾つか存在しますが、MLSの放映権を保有しているESPN社の意向も影響しているとは思います。
※数年前にMLSバンクーバー・ホワイトキャップスが配信した施設の紹介動画。こちらを見るだけでもハード面の充実がうかがえる。
――アメリカの他のメジャースポーツはどのような状況でしょう?シーズン終盤だったNBAとNHL、開幕前のMLB、9月に開幕するNFLなど状況は様々ですが。
NBAもMLSと同じオーランドにて、7月31日より変則型の22チームで一ヶ所集中開催を発表しています。
NFLは開幕まで時間があるためかまだ具体的な施策は公式には発表しておらず、他のリーグの動きなどを静観しているような状況です。
MLBは6月16日時点ではまだリーグと選手協会の間での選手の労働条件への折り合いがついておらず、最悪、リーグ戦が開催できないのではないかという危機感は高まってきております。
MLSもギリギリまで、減らされた試合数に伴う選手の減俸に関して交渉を継続した末、再開に漕ぎ着けることができましたので、ここはアメリカスポーツにおける労使協定特有の問題だと思います。
※今年完成したMLBテキサス・レンジャーズの新スタジアム「グローブ・ライフ・フィールド」だが、いまだチームやファンを迎え入れることはできず…。
――それぞれ再開に向けて問題となっていることや、共通の課題などがあれば教えてください。
共通の課題は、やはり選手・スタッフの衛生や安全面が第一に来ます。続いては、試合数が減るので、それに伴い選手の年俸をどのように減らすのか、という交渉がリーグと選手協会間で激しく続けられております。
また一ヶ所集中開催に際してはその期間中、家族とも断絶な状態となるので、果たして現実的なのかどうかの問題もあります。MLSは短い期間ですが、MLBなど長期間に渡ってそれを実施することはなかなか難しいものがあります。
そして当然ながらスポンサーや、放映権の問題もあります。
スポーツビジネスは“変化”とともにある
――なるほど。新型コロナウイルスによって、一大ビジネスであるアメリカのスポーツ産業にはどんな変化が生まれそうでしょうか?
これはまだ正直わからないです。
ざっくりと言うと今までは人を集めてナンボの集客重視であったのが(=密を作る)、人を集めてはいけないモデル(=密を作らない)に一気に移行したので、3ヶ月程度で答えは出ないと思います。
ただスポーツビジネスの4大収益源であるチケット、スポンサー、放映権、スタジアムのうち、チケットとスタジアムを一気に失いましたので、ショックは大きいです。

コロナ問題が勃発した直後からここまではいかにファンとのエンゲージメントを高めることが重要かと考え、皆がこぞってあらゆるアイディアや企画をSNSを中心に創出してきました。
しかし収益源になっているものはほぼ皆無ですし、ネタが尽きてきた感もあり、やはりスポーツをまた見たい!という気持ちは皆高まってきています。
また、コロナの後は色々と変化することは必須で、例えば9・11のテロの後、空港やスタジアムへの入場のセキュリティが一気に強化されたことで、早めに行かないといけなくなりましたし、持ち込めるアイテムも制限ができたり、入場時のセキュリティに時間がかかるような不便がかかるようになりました。
それと同様に、コロナ後も色々な不便は生じると思います。
現時点で既に聞こえてくるものとしては、今後搭乗に際しては、飛行機の搭乗時間の4時間前には空港に行き、現存のセキュリティチェックに加えて衛生面でのチェックも増えるのではないかと言われています。
スタジアムで言えば、まずは収容人数への制限がかかるようになるでしょう。
入場に際しては人が密にならないように割り当てられたゲートからの時差入場や、コンコースの一方通行、トイレへの入場制限、ドアのタッチレス化、飲食のプレパッキングされたものをスマホで座席から購入する、退場時も座席区分ごとに時差退場などの予想が聞こえてきたりします。
業界への異変としては、衛生面の専門家の仕事が増えたりするとも言われていますし、アメリカのプロスポーツでは既にそのような公募も散見します。同時にホテルなどが使用する衛生管理の認証などをスタジアムも申請し始めました。
もしかしたらスタジアムに観戦に行くことは高い娯楽になってしまうのかもしれませんし、入場制限がかかるのであれば元々区分けされていて客単価の高いスカイボックスなどを増設しないといけなかったり、スタジアムの構造まで変えてしまうかもしれません。
観客席に余裕が生まれるということはカメラの設置位置も変わってくる可能性はあります。そもそも満員の観客席にて観客の視界を遮らないところに今はカメラが設置されていますが、その制限も変わります。

またホームアドバンテージも無観客試合ですと薄れますし、選手の視点からも変化は当然あると思います。
例えば、大観衆がいるとプレッシャーで全く本来の力が出せなかった選手が無観客試合で活躍をしたり、観客の声援に後押しされてやる気が出た選手にとっては逆効果となり、今まで聞いたことのない無名の選手が台頭してきたりすることも考えられます。
スタジアムにおける変化はこのように既に色々と予想が出てきていますが、やはり今後の新しいマネタイズ方策は急務となってきます。
無観客試合ゆえにCGでテレビ放映にスポンサーのロゴの露出を今までにはできなかった方法で拡大したりする案も見受けられますが、果たしてロゴ掲出にどれほどの効果があるのか?という命題はコロナ以前から議論されてきたことです。
eSportsや、SNS、デジタル施策がその答えを導き出す主役であることは間違いないですが、ここから世界中のリーグが無観客試合で再開していく中でどのような創意工夫をしていくのか非常に注目しています。
例えばスタジアムももちろんですがテレビやインターネットで観戦をして盛り上がるファンというのは今までにもいたわけで、そちらにもっと注力することになるのかもしれません。
NFLのスーパーボウルを代表例とすると、スタジアムが満員なのは当然ですが、それを遥かに上回る数の人がテレビで観戦し、そこから派生して生まれるビジネスは巨大です。

スポーツビジネスの産業が変化を求められてきたのは今に始まったことではなく今までも様々な変化がありました。
今回のコロナは特にいきなり予想を超えるインパクトであったので、そのショック状態が大きいですが、その時々の社会の変遷に合わせて消費者の価値観も変わってきており、それにアジャストするのがスポーツマーケティングでした。
わかりやすい例は「安全性の担保」。アメフトの器具は最たる例ではないでしょうか。
現在は昔と違い、様々なテクノロジーが駆使されスポーツそのものの安全性が向上してきました。アメフトに限らず、一昔前のスポーツを見ますと今の常識では考えられない危険な器具もあります。それはスポーツを子供にさせる親の価値観の変遷も影響しています。
一方で、言い換えるとこれからも色々と変化をしていくのが当たり前ですので、変わるものを追いかけてばかりいくのは不可能ですし、これを機にスポーツビジネスにおける原理原則をきちんと理解することが肝要になっていくものと考えます。
変わるものと、変わらない不変な原理原則。このバランスを理解しつつ、今後もスポーツビジネス業界に参画していくことが大切だと思います。
≪続く≫
【関連記事】久保裕也、MLS初ゴール!GK棒立ちの「圧巻ミドル」がこれ(動画あり)
中村武彦/青山学院大学卒業。マサチューセッツ州立大学アマースト校スポーツマネジメント修士課程、及びマドリーISDE法科大学院修了。現・東京大学工学部社会戦略工学共同研究員。NEC海外事業本部を経て、2005年に日本人として初めてMLS国際部入社。2009年にFCバルセロナ国際部ディレクターなどを歴任後、独立し2015年にBlue Unitedを創設。鹿島アントラーズ・グローバルストラテジーオフィサー、MLSコンサルタントなども務める。2012年にはFIFAマッチエージェントライセンスも取得し、2018年にパシフィックリムカップを創設。同年プロeスポーツチームの「Blue United eFC」も立ち上げ。2017年より青山学院大学地球社会共生学部の非常勤講師を務める。著書:「MLSから学ぶスポーツマネジメント(東洋館出版)」