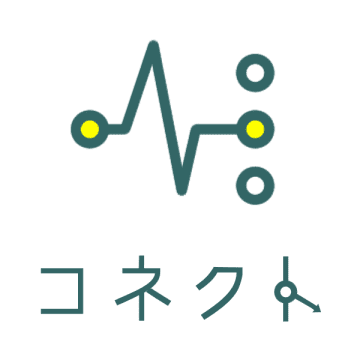スーパーGTを戦うJAF-GT見たさに来日してしまうほどのレース好きで数多くのレースを取材しているイギリス人モータースポーツジャーナリストのサム・コリンズが、その取材活動のなかで記憶に残ったレースを当時の思い出とともに振り返ります。
今回は2008年のNASCARスプリントカップシリーズ第4戦としてアトランタ・モーター・スピードウェイで開催された“コバルトツールズ500”の後編。このレースはコリンズのNASCAR魂に火を点けたようです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
アトランタのホテルでNASCARエンジニア陣とネイションワイドシリーズを観戦した翌日、私はNASCARスプリントカップシリーズ(現在のNASCARカップシリーズ)の“コバルトツールズ500”決勝レースを見届けるべく、アトランタ・モーター・スピードウェイに向かった。今回はメディアセンターに私専用のデスクが用意されていた。
そのデスクの隣にはテレビ放送の実況を務めるアナウンサーたちが座っていたので1時間ほどおしゃべりした。互いの仕事についてなど、さまざまな話題について言葉を交わしていると、彼らは私がどこの出身かと尋ねてきた。
私はロンドン北部のある村に住んでいることを説明すると、一瞬の間を置いてから、アナウンサーのひとりが「じゃあ、君のアクセントは“偽物”じゃないんだね!」と叫んだ。
どうやらアメリカには、なぜか偽のイギリスアクセントを使って話そうとする人がいるらしい。彼らは私もそういった人間のひとりだと思っていたのだ。イギリス人ジャーナリストがNASCARの取材に来るのは、それくらい珍しいことだったのだ。
前日はNASCAR独自の取材法に驚かされたが、この日はプレスルームの奇妙な点に驚かされた。なんとメディアセンターのスタッフが食事を席まで持ってきてくれるのだ。
私も取材したことのある鈴鹿サーキットや富士スピードウェイなどでは、昼食にお弁当が提供されるのだが、アトランタの週末はフルコース料理が提供された。ポテトが添えられた巨大なステーキに続いて、デザートとして大きなボウルに入ったアイスクリームも提供された。
正直、私には量が多すぎたのだが、残念ながらアメリカには“少なめ”という選択肢はない(そしてアメリカ人ジャーナリストの多くは痩せてもいない)。私が必死の思いでアイスクリームを食べ終わると、プレスルームで働く女性が次はなにを食べたいかと聞いてきた。
必死の思いでデザートまで食べきったばかりだったので、この質問にはさすがに混乱した。すると彼女は「次の食事のことですよ」と答えてきた。このような感じで1日中、食べ物が際限なく出てきた。
私には食べ切れないほどの量だったが、メディアセンターにいるほかのジャーナリストたちは、私がほとんど食べないことを奇妙に思っていたようだ。私のお腹は限界を超えていたが、アメリカ人たちは際限なく食べ続けていた。
“コバルトツールズ500”決勝レースが始まっても食事の提供が続いたことにも驚かされたのだが、それよりもレースがスタート早々に奇妙な展開になっていたことに驚かされた。
このときの私はレースレポートを執筆する仕事を受けていなかったので、終わりのない食事サービスから逃れるべくピットレーン(アメリカ人はピットロードと呼ぶ)まで歩いていくことにした。
そのピットレーンではNASCARのピットクルーたちがどれだけ訓練を積んでいるかを目の当たりにした。彼らの多くは出番を迎えるまで座っている。そしてイエローコーションが出されると走行全車が激しいエンジンサウンドを奏でて一斉にピットへ戻ってくる。するとピットクルーは慌ただしく仕事を始めるのだ。
彼らの仕事は目にも留まらぬ速さだった。NASCARではほかのモータースポーツのような最新鋭のピット機材は使われない。かわりにスチールのホイールにナット、そして一般家庭のガレージにあるようなジャッキが使われている。給油機も“水差し”のような原始的なものが使われていた。
ピット作業の光景は、私がF1や他のスポーツカーレースで見慣れてたものとはまったく違うものだった。本当に昔ながらの手法が採られていて、1960年代からそれほど変わっていないように見えた。

ピットクルーの仕事を見届けたあと、私はピットレーンの端でマシンがターン4から立ち上がって来る様子を見ることにした。アトランタ・モーター・スピードウェイのターン4は超高速コーナーで、40台のマシンが目の前数メートルのところを約時速200マイル(約時速321.86キロ)で通り過ぎていく様子は圧巻の一言だった。
圧倒される光景だったが、私がそこに立つことを許されていたことにも少し驚かされた。走っているマシンの台数とドライバーが全開で駆け抜けていくセクションであることを考えると、私が立っていた場所はかなり危険な場所に思えた。正直に言えば、少し恐怖さえ感じるスポットだったので、長居することなくメディアセンターに戻った。
レースが進むと、ドライバーの多くがマシンのハンドリングに手こずっていることが明らかになってきた。雪が降った前日に続いて気温が低かったこと、そしてグッドイヤーが新しく投入したタイヤを使っていることが原因に見えた。
ドライバーたちがハンドリングに苦しんでいることは、ピットレーン端で走行を見ていたときに気付いていた。メディアセンターに帰ると、モニターで走りを見ていたジャーナリストたちも「マシンはアスファルトというよりもダート(未舗装路)を走っているかのようだ」と表現していた。
この状況を見兼ねたチームは、頻繁にタイヤを変えて状況を改善しようと試みていたが、そううまくはいかなかった。
■ジャーナリストも騒然としたトニー・スチュワートの発言
ただNASCARに参戦しているドライバーの多くがダートオーバルでレースキャリアを始めるので、大半のドライバーはなんとかマシンを乗りこなしていた。
一方、この大会に参戦していたロードレース出身者、つまりダッジ・チャージャーをドライブしていたファン・パブロ・モントーヤやダリオ・フランキッティ、パトリック・カーペンティアなどは苦戦しているように見えた。
レースは当時NASCARでもっとも人気のあるドライバーだったデイル・アーンハートJr.(シボレー・インパラSS)を先頭にスタート。一時はクリント・ボウヤー(シボレー・インパラSS)とトップ争いを繰り広げた。
しかし、このレース全体を支配していたのはカイル・ブッシュ(トヨタ・カムリ)で、終始彼を追い続けたのがジョー・ギブス・レーシングのチームメイト、トニー・スチュワート(トヨタ・カムリ)だった。
結局、このふたりはワン・ツーフィニッシュを飾り、カイル・ブッシュは当時NASCARカップシリーズ参戦2年目だったトヨタに初勝利をもたらした。アメリカのマニュファクチャラー以外がNASCAR最高峰シリーズで優勝を飾ったのはジャガーが優勝した1954年シーズン以来のことだった。


本来であれば快挙として注目を浴びるはずだった功績は、レース後にスチュワートが発したコメントによって、かすんでしまった。2位でフィニッシュしたスチュワートはチームやトヨタに対して祝福の言葉を残すと誰もが予想していたのだが、彼の発言はショッキングなものだった。
「今日のタイヤは、僕がプロドライバーとしてのキャリアで使ってきたもののなかで、一番ひどいレーシングタイヤだった。グッドイヤーはF1から撤退し、IRLから撤退し、CARTから撤退し、ワールド・オブ・アウトローズからも撤退した。そして、それには理由があった。ろくでもないタイヤしか作ることができないからだ」
こう言い放ったスチュワートはひどく荒れていた。この発言を聞いたメディアセンターのジャーナリストたちは大いに驚いた。NASCARに参戦しているドライバーたちは歯に衣着せぬ物言いをすることが多いが、シリーズの主要パートナーでもある企業に、これほど直接的な“口撃”を仕掛けたという話は聞いたことがない。
ドライバーによるグッドイヤー批判はレース後の記者会見でも続いた。3位でフィニッシュしたアーンハートJr.を始めとするドライバーたちも次々と不満を口にした。
確かに、あの週末グッドイヤータイヤが十分な働きをしなかった。しかし、その原因はタイヤではなく、あまりにも低かった気温にあると私は睨んでいた。事実、アトランタで起きたトラブルが再発することはなかったのだ。
2008年の“コバルトツールズ500”は見ていて特にエキサイティングなレースではなかったが、レースの裏で起きていたことは興味深かったし、NASCAR初心者だった私には最適なレースだった。
このあと、私はさらにNASCARを学ぶべく、旧式のNASCARマシンで争われるヨーロピアン・レイト・モデルシリーズにドライバーとして出場し始めた。ちなみに、このシリーズは後にNASCARユーロシリーズへと変化していく。
また私はNASCARへの情熱を持ち続けていたので、その後数年はノースカロライナに足しげく通っていた。
今もNASCARはチェックしているが、最後に現地で観戦してからは数年が経過している。私が見たり取材したNASCAR戦の多くは記憶から消えてしまっているが、アトランタで過ごした最初の週末は、いまでもはっきりと心のなかに残っている。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
サム・コリンズ(Sam Collins)
F1のほかWEC世界耐久選手権、GTカーレース、学生フォーミュラなど、幅広いジャンルをカバーするイギリス出身のモータースポーツジャーナリスト。スーパーGTや全日本スーパーフォーミュラ選手権の情報にも精通しており、英語圏向け放送の解説を務めることも。近年はジャーナリストを務めるかたわら、政界にも進出している。