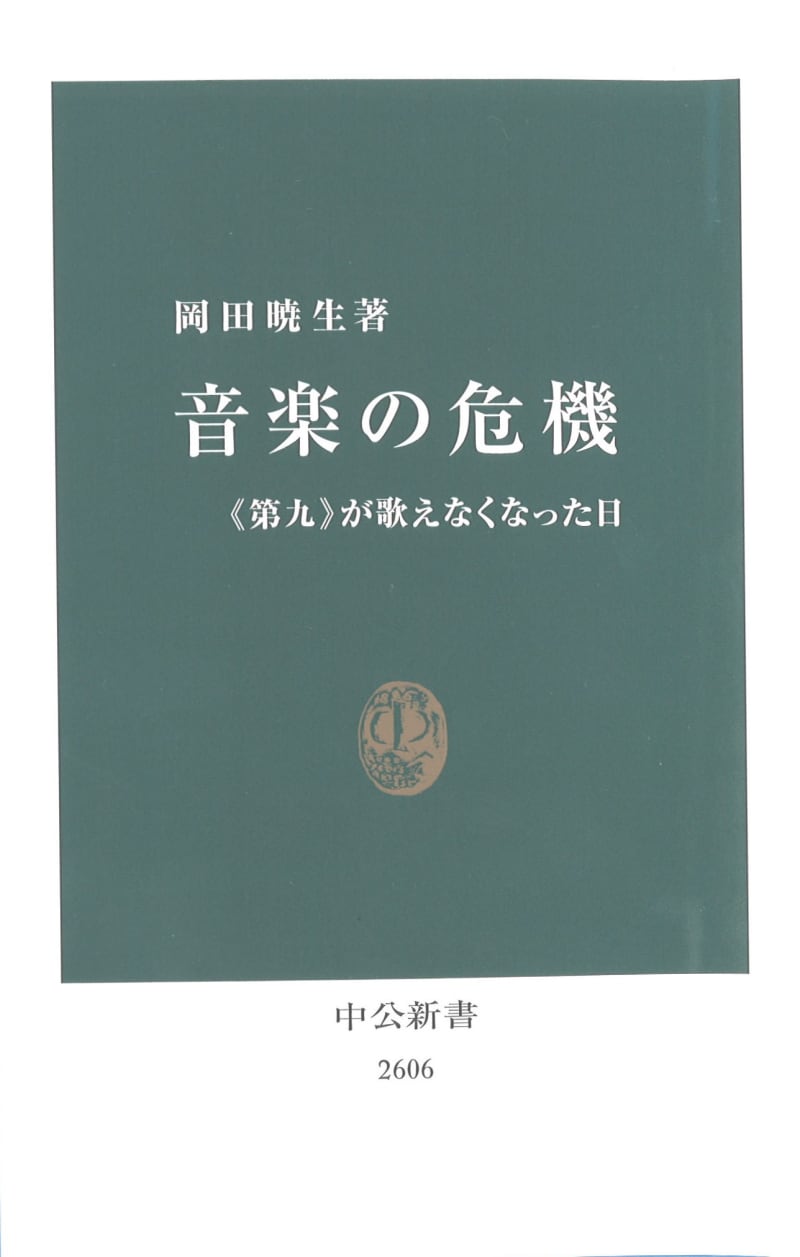
新型コロナウイルス感染拡大に伴って、演奏会やライブ、演劇、美術館、スポーツ会場など密集する場所がなくなった。感染防止の努力は必要で、日本では次第に観客が入る形で催されているが、コロナ以前とはほど遠い。「音楽とは、人々が集まって一緒にやる、一緒に聴くものだ」と著者は記す。本書は音楽から照射する現代社会批評として、私たちが現下の困難をどう捉え、この先にどんな社会があり得るのかを考える道しるべになるだろう。
芸術とは「常識からするとにわかに信じがたい『ヴィジョン』を突きつけてくる」ものであり、平時の常識が崩れる世界を察知することが芸術の有効性だと著者は指摘する。元気、癒やし、感動を得て人々の絆を確認し、快適になる音楽とは立場を異にする。「何の役に立つのかわからない」とされたとしても、次に来る世界の気配をまとう鋭敏なセンサーであるというのだ。
この夏にやむを得ず広がった「オンライン帰省」は「実際に故郷に足を運ばないことで決定的に失われる何かを見逃してしまう」という著者の例示は的を射ており、音楽の場合も複製では伝わらない気配の中に大切なものが含まれている。配信や録音は第三者の技術的な関与、システム管理者の一元的な統合を経ていることを、オンラインに頼る場面が一気に増えたコロナ時代にこそ自覚する必要があると感じた。
人と共有する空気と振動、気配を察知することは重要であり、本書ではマイルス・ディヴィスをはじめとするジャズ奏者の細やかさにその典型を見る。いつとは分からないがこの感染症を克服した社会をつくるヒントが音楽に埋蔵されていると思う。
著者は「音楽の聴き方」(中公新書)の中で音楽について「特定の歴史/社会から生み出され、そして特定の歴史/社会の中で聴かれる」と述べている。そうであるなら音楽を通して社会を考える意味は今こそ明らかだろう。危機に直面する時でも、文化は決して不要不急ではない。その確信を新たにした。
(中公新書 820円+税)=杉本新
