
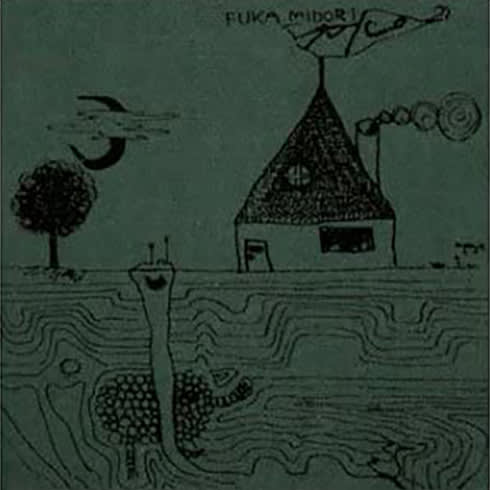
今年9月半ば。浅井健一&THE; INTERCHANGE KILLSの「TOO BLUE」がリリースされたあとくらいに、編集担当氏から“BLANKEY JET CITY の名盤は随分以前に紹介したので、今度は浅井さんつながりでSHERBETSやAJICOはどうですか?”と推されていたのだが、ここまでいろいろと新作リリースが続いて、大分先送りしてしまって申し訳ない。大変遅くなりました。今週はAJICOの『深緑』を紹介します。
画期的だったバンド結成
まずは、有名アーティスト同士による豪華コラボレーション、それも男女のコラボから語ってみたい。男女コラボというのは演歌や歌謡曲の世界ではことさら珍しいのものではなく、フランク永井/松尾和子「東京ナイトクラブ」(1959年)、橋幸夫/吉永小百合「いつでも夢を」(1962年)辺りから始まって、木の実ナナ/五木ひろし「居酒屋」(1982年)、小林幸子/美樹克彦「もしかしてPART II」(1984年)等々、いくらでも実例を挙げられるし、何ならほぼ歌えるほどでもある。であるからして…と思い、J-POP、J-ROCKに話を絞らせてもらおうと考えたのだが、これもまた殊更に少ないとも言えない。鈴木聖美 WITH RATS☆「ロンリー・チャップリン」(1987年)や中山美穂&WANDS;「世界中の誰よりきっと」(1993年)辺りを例に上げようとするのは古い人間の悪癖だろうから、もう少し最近のもの(と言っても、ここ15年間くらいだが)に話を絞っても、記憶にも記録にも残る名曲はわりとある。順にザっと上げてみる。EXILE&倖田來未「WON'T BE LONG」(2006年)。絢香×コブクロ「WINDING ROAD」(2007年)。青山テルマ feat.SoulJa「そばにいるね」(2008年)。加藤ミリヤ×清水翔太「Love Forever」(2009年)。T.M.Revolution×水樹奈々「Preserved Roses」(2013年)。ちなみに「Love Forever」はのちに清水翔太×加藤ミリヤ「FOREVER LOVE」(2010年)というアンサーソングを生みだし、「Preserved Roses」は水樹奈々×T.M.Revolution「革命デュアリズム」(2013年)と連動していた。ここ数年で言えば、DAOKO×米津玄師「打上花火」(2017年)、椎名林檎とトータス松本「目抜き通り」(2017年)、椎名林檎と宮本浩次「獣ゆく細道」(2018年)などが鮮烈な印象を与えたし、アルバム収録曲ではあるがRADWIMPS「泣き出しそうだよ feat.あいみょん」(2018年、アルバム『ANTI ANTI GENERATION』収録)も記憶に新しいところだ。
こうして見てみると、一年に一作はヒット作、話題作が生み出されているような印象すらある男女コラボ曲。どうして毎年のように生まれて来るのか。それは、ニュースバリューを与えるためか、カラオケでの使用を増やそうという意図か、はたまた純粋にアーティスト同士の共感、共鳴によって創作されるのか分からないし、それぞれに事情は異なるのだろうが、それが我々、聴き手にとって刺激的な邂逅であることは間違いない。それぞれのヴォーカルのキーの違い、表現方法の違いが合わさることで、各々の楽曲とはまた別の味わい、聴き応えが出てくるのは確実…というか、絶対にそれが出てくるので、面白くないわけがないのである。男女の機微をそれぞれが歌唱する歌詞に乗せるケースも少なくない。その場合は世界観が一方向ではなくなるようではあって、その事の良し悪しはともかくとして、それによって、聴き手を分けないというか、男女いずれのリスナーにもシンパシーを抱かせることができることで、ヒットにつながっているのかもしれない。
事程左様に、音楽シーンにおける定番のようにも思う男女コラボであるが、ダブルネームないしは“feat.”がほとんどであるからして、それを一概に企画もの…と呼んでしまうのはやや乱暴ではあろうけれども、そのコラボでパーマネントな活動を模索したり、フルアルバムを制作したりすることは稀ではあるようだ。そのコラボでライヴをやることはわりとあるようだが、全国ツアーを回った…なんて話は、あったのかも知れないけれど、記憶に残っているものがない。アルバムはパッと思いついたところで言うと、安室奈美恵の『Checkmate!』(2012年)辺りはコラボレーションアルバムではあるものの、あれは彼女がゲスト参加した楽曲をコンパイルした作品。面子が固定されているものではない。前述のアーティストにしても同様で、例に上げたコラボ曲は収録されていても、それ一曲だけとかがほとんどだ。
その意味でも、UA(Vo)と浅井健一(Vo&Gu)とが2000年に結成したバンド、AJICOは邦楽史において稀有な存在ではあろう。1995年にデビューして、シングル「情熱」(1996年)「甘い運命」「悲しみジョニー」(ともに1997年)、アルバム『11』(1996年)『アメトラ』(1998年)が相次いでヒットし、その時点でシンガーソングライターとしての存在感をあまねく認知させていたUA。一方、1990年代において3ピースバンド、BLANKEY JET CITYを強烈なインパクトを放ち、1996年にはSHERBETを結成(※それを前身として1999年にバンドスタイルのSHERBETSとして結成)していた浅井。そんな彼が2000年にBLANKEY JET CITYの解散を発表後、UAとともに始動したAJICOは、その話題性はもちろんのこと、今となってみても、バンドというスタイルをとったことも実は画期的であったと言える。
全編に溢れるアンサンブルの妙味
なぜバンドであったのか。AJICO結成の首謀者は浅井で、彼がUAを誘い、UAが彼女自身のソロでもサポートをしていた椎野恭一(Dr)をメンバーに推挙。ふたりの間で“ベースはアップライトが弾ける女性”と決めていたそうで、あるイベントでTOKIE(Ba)を観た浅井が直接声をかけて、後日4人でセッションしたことから始まった。AJICOがよくある1、2曲だけの企画ものではなく、バンド結成に至ったのは、首謀者である浅井がバンドを組みたいと思い、UAもそれに共感したからに他ならないわけだが(※馬鹿みたいな文章ですみません…)、1stアルバム『深緑』を聴いてみると、“本当にバンドがやりたかったんだろうな”と思えてくるし、もっと言えば、その音像からはこのメンバーで音を出してみたかったことがよく分かる気がする。[ほとんどバンドとヴォーカルが一緒の一発録りで録音している]ことにも由来するのかもしれないが(※[]由来Wikipediaからの引用)、どの楽曲でも各パートの音が実に生々しい。そして、それらの音がどのように折り重なってアンサンブルを作り上げているのかが分かるように録音されているように感じられる。
全曲そうなので例を挙げるまでもないけれど、ここはM6「GARAGE DRIVE」を見てみよう。イントロはギターの音だろうが、弦を弾いてる感じではなく、弦をこすって鳴らしているような、ノイジーで不思議な音から始まる。そこからリズム隊が加わり、もう一本、別のギターも鳴っていく。メインヴォーカルは浅井で、彼のハイトーンの歌声に呼応してか、ギターの音も甲高い。ベースラインは独特のうねりを持ちながら楽曲を支え、タンバリンが独特のダンサブルさを醸し出す。スネアの音も鋭角的で、この「GARAGE DRIVE」は『深緑』収録曲中、最もR&R;なナンバーと言えるだろうが、幻想的なUAのコーラスが決してアグレッシブなだけではない、特有の空気感を生み出しており、ひと工夫どころか、ひと癖もふた癖もあるナンバーに仕上がっている。最後はドラムのシンバルの残響音の、文字通り残った響きが去っていく感じもとてもいい。
また、AJICOのアンサンブルを語るうえで外してはならないのは、1stシングルにもなったM11「波動」、そのアウトロではあろう。いや、終盤の歌のない部分なので便宜上、アウトロとは言ったものの、3分にも及ぶ演奏なのでそう呼ぶには忍びないというか、ここもまた楽曲の中心とも言えるセクションである。エレキのアルペジオから始まるサビ出しで、2番からリズムが入るという、楽曲が進行するに従って、どんどん3ピースの音が絡まっていくスタイルなので、その後半3分はバンドアンサンブルが楽曲中、最も複雑な箇所ではある。ただ、“複雑”とは言ってみたものの、それは明らかに“密集した”とも“ごちゃごちゃした”とも違う、抑制の効いたひしめき合いと言おうか、ひと筋縄ではいかないバンドアンサンブルであることは間違いない。おそらくアドリブであり、インプロビゼーションに近い演奏ではあろう。だが、こういうところにAJICOがバンドであることが凝縮されているとは思うし、このバンドの象徴でもあると言えると思う。
浅井の既発曲をUAらと再構築
『深緑』で興味深いのは、それをセルフカバーと呼んでいいのかどうか分からないけれども、すでに発表されていたナンバーを原曲とした楽曲が収録されている点もある。M4「Lake」、M8「メリーゴーランド」、M10「毛布もいらない」がそれ。それぞれ順にSHERBETS「麦」、BLANKEY JET CITY「ハイヒール」、BLANKEY JET CITY「黒い宇宙」が原曲だ。いずれも歌やギターの主旋律はほぼ変わっていないのだが、それぞれにアレンジが変わっていることに加えて、タイトルはおろか、歌詞も全て変わっている。“セルフカバーと呼んでいいのか”と言ったのはその辺で、カバーと言うよりもその手順だけ見たらリメイクと言いたくなるような代物だが(そう言うとSHERBETSにもBLANKEY JET CITYにも若干失礼な気もするので、ここでは先にセルフカバーという言葉を使ったが)、いずれにしても、このことはアルバム内では触れられていない。その理由は分からないけれども(※どこかのインタビューで語っていたのかもしれないけれど、今回それを見つけることができなかったので、もし語っていたらご容赦を…)、そこに触れる必要がなかったということだろう。
“人が変わるとバンドは変わる”とはよく言われることで、同じ曲を同じ楽譜で弾いたとしても、演奏者が異なれば楽曲の仕上がりはまったく別のものとなる。アドリブやインプロビゼーションのような即興演奏であればなおのこと、演者によってフレーズも随分と違ったものになるだろうし、バンドでそれが絡み合えば、そこでしか生まれ得ないアンサンブル、サウンドとなることは必然だろう。つまり、こういうセルフカバー的なことをすることでAJICOがバンドであることがよりはっきりとするようなところがあるのではないかと思う。SHERBETSやBLANKEY JET CITYと比較して云々ではなく、単純に異なるサウンドを鳴らせるというだけで、AJICOというバンドの実存を際立たせることができる。仮に比較されるにせよ、どちらの演奏にもそれぞれの特徴があるのだから、優劣を付けられるものではない。これは筆者の邪推だと思ってもらって構わないが、もしかすると、浅井にはそんな意図もあったのではないかとも、少しばかり想像する。
歌詞ははっきりとその意味合いが分かるものではないので、その解説は完全に手に余るのだが、やはりセルフカバー的ナンバーが興味深いので最後に記しておく。
《刺激的な夜へ行こうぜ/ポケットにいっぱい詰め込んだアメリカ生まれのキャンディ/満月に冷たくウィンクして/マシンガンを撃ちたい/理由はこの空が好きだから/ピンクの火花は真実/いつかこの街に奇跡が舞い降りて僕は目覚める/優しい口笛が聞こえて/かわいい黒猫が夜をみてる》《コメディアンが涙を流している/TVの中でみんな笑い声をあげる/刺激的な夜へ行こうぜ/ポケットにいっぱい詰め込んだアメリカ生まれのキャンディ/満月に冷たくウィンクして》(BLANKEY JET CITY「ハイヒール」)
《夕べの口づけが暴れてた/ママの手に はぐれた十字星/割れた地面から 這い出したクモ/得意げに唄った/美しい記憶 揺れる花びら/次のドアが たたかれる前に/目を覚まそう/風に嘘ついた ロクデナシが/目覚めたら あることに気がついた/ずっと居なかった 探してたよ/ありふれて 離れた言葉のかたち》《馬車の赤目石を子供達が/また盗んでく/ラララ愛してた風の日も》《雷に 打たれても愛してる/そんなありふれた/神様みたいな/夢のドア開く前に聴いた/ママのメロディ》(M8「メリーゴーランド」)。
同じような言葉もほぼないし、まったく性格の異なるような歌詞に見えるし、その見立てで概ね間違いないとは思う。だが、鋭角的であったり攻撃的であったり、あるいは少し奇異であるワードがありながらも、そこに柔らかさや優しさが内包されているのは、どこか似ているように思う。だから、浅井はUAをバンドに誘ってAJICOを結成したのだろうか。少しだけそんなことを思った。
TEXT:帆苅智之
アルバム『深緑』
2001年発表作品
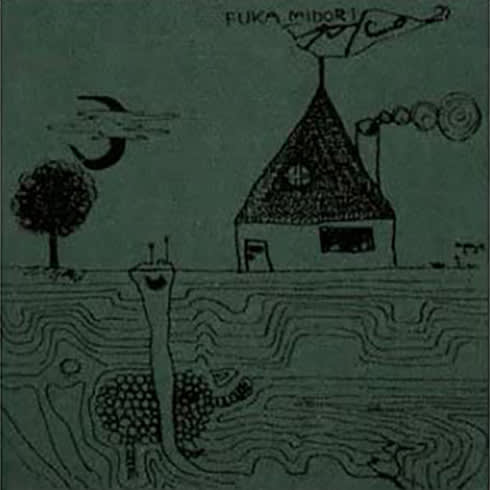
<収録曲>
1.「深緑」
2.「すてきなあたしの夢」
3.「美しいこと」
4.「Lake」
5.「青い鳥はいつも不満気」
6.「GARAGE DRIVE」
7.「メロディ」
8.「メリーゴーランド」
9.「フリーダム」
10.「毛布もいらない」
11.「波動」
12.「カゲロウソング」

