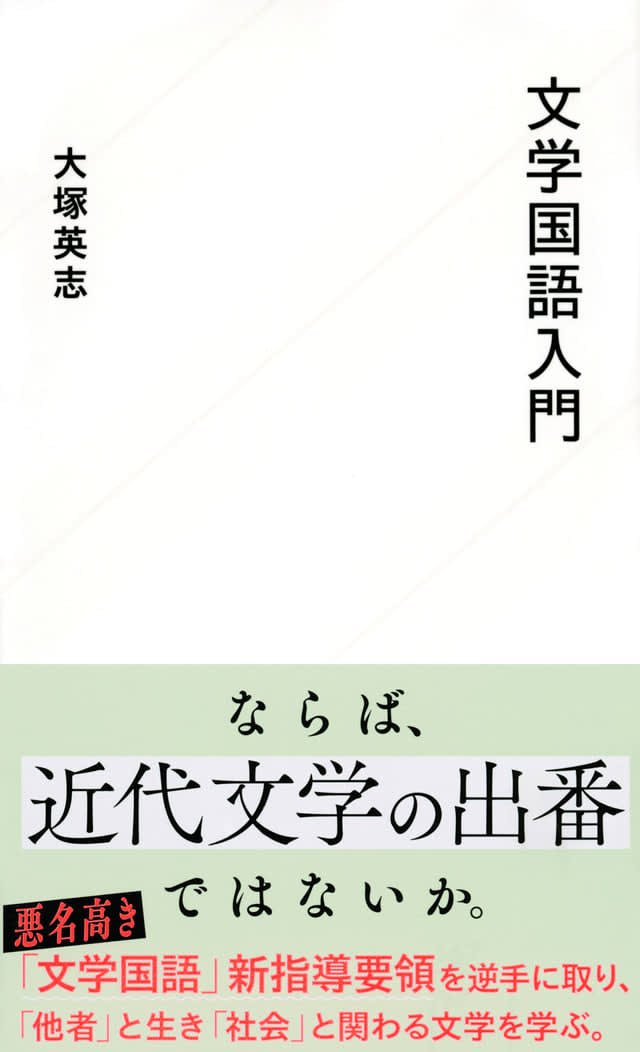
アイロニーに満ちたタイトルだ。日本の近現代文学史の鮮やかな見取り図を提示した本書に、著者は一つの仕掛けを施した。2022年実施予定の高校の新学習指導要領で新設された科目「文学国語」に向けて本書を著したという。まえがきとあとがきで著者は次のように強調する。
新指導要領は従来の「現代文」を、実用的文章を学ぶ「論理国語」と文学を題材にする「文学国語」に分け、国語の目的に「言葉を通して他者や社会と関わる」ことを挙げる。それはまさに明治以降の近代文学が一貫して問い続けてきたテーマだ。ならば他者と関わる手立てを学ぶテキストとして今こそ近代文学を読もうではないか――。
読み方としては「疑い」の歴史として文学史を編み直すこと。疑う対象は小説の周辺にある「私」「他者」「物語」「世界」「作者」「読者」だ。
明治期に始まった一人称言文一致体は、フィクションとしての「私」を生んだ。近代的自我を持つ「私」は誰かにとって正体不明の「他者」であり、「他者」同士が相手の心を疑い合うことが文学の手法になる。近代文学は「私」を根拠付ける「物語」や「世界」を疑い、2次創作の普及はオリジナルの作り手たる「作者」の不在を宣告した。すなわち近代文学は「私」や「作者」や「読者」が「他者」や「社会」との対決を避けて「物語」や「世界」に逃げ込むことに常に疑いのまなざしを向けてきたという。
その曲折は複雑だが、同時にスリリングでもある。例えば村上春樹の初期3部作が「私」から「作者」に至るすべてを疑うよう「読者」に求めていることを解き明かし、村上文学が「正当な『戦後文学』の歴史の延長」にあることを示す手さばきは実に刺激的だ。
さて著者の分析は近代文学を超えてライトノベル、ゲーム、SNSにまで及ぶ。「入門」どころか本格的な論考である。タイトルを付けるなら「疑いの日本文学史」だろう。新指導要領を逆手に取った著者のたくらみを私たち読者は疑わなければいけない。
(星海社新書 1050円+税)=片岡義博
