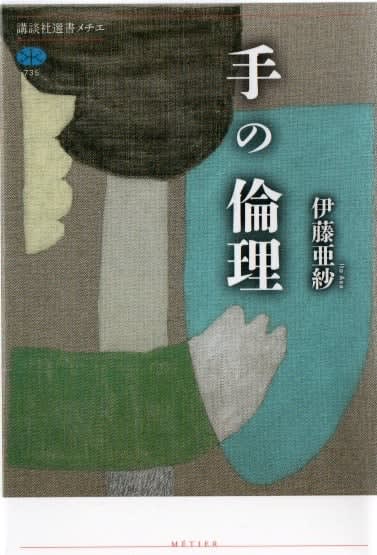
セクハラアンケートの被害例に「いやらしい目つきで見られた」という回答を見つけてドキリとしたことがある。それが「まなざしの倫理」を問うものならば、一方で「手の倫理」がある。他人へのふれ方、さわり方によってそれは親密さの表現にも暴力にもなる。触覚が開く関わりの可能性。これが本書のテーマである。
冒頭、著者は目隠しをして目の見える人に伴走してもらう「ブラインドラン」体験の衝撃を語る。2人は握ったロープでつながり、腕が触れそうな状態で並走する。最初は恐怖で足がすくむ。だが伴走者に身を預ける覚悟をして走ると、何とも言えない深い快感に包まれたという。この体験をめぐる考察が、障害者介助やスポーツ、子育てなどの現場証言を手がかりに議論を展開していく本書の触覚論を集約するものになっている。
並走する2人が腕を振るリズムや歩幅、体の向きといった動作を長時間シンクロさせるうちに「共鳴」の感覚が生じ、伴走者の走行ペースやコーナリングが自然に相手に伝わる。ベテランになると、伴走者の意図や判断が言葉を介さず分かるばかりか、伴走者が伝えようとしていない感情や感覚までも伝わってくるという。
そこに生じているのは一方的な「伝達」ではない。その場の互いのやりとりで生まれる双方向のコミュニケーションであり、互いの体に入り込み合うような関わりだ。こうした状態に至るには相手への深い信頼が前提となる。相手に自らを預けたぶんだけ相手を知ることができる関係が、視覚や聴覚とは異なる触覚特有の関わりの可能性を開く。それによるリスクも伴いながら――。
ウィズコロナの時代、人間同士の接触が大幅に制限される一方、社会の高齢化によって接触を伴う介護や看護の機会は急増している。今まで十分に語られてこなかった「手の倫理」が今後さまざまな現場で問われるだろう。相手を信頼して自らを預けることの価値、触覚が開く関係の豊かさを示した本書の役割は大きい。
(講談社選書メチエ 1600円+税)=片岡義博

