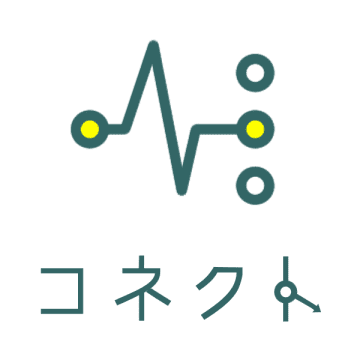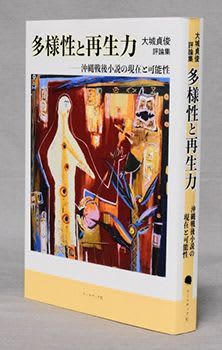
本書の著者は詩人、小説家であり、評論家、教育者である。氏の沖縄戦後詩論に「抗(あらが)いと創造」(2019年)があり、沖縄の戦後が抱えこまざるを得なかった外部勢力への「抗い」を通した言葉による詩の「創造」性を評価している。対して本書は、沖縄の戦後の小説に焦点を当てた評論集である。
ところで、日本の文学史をたどるとき「ローカル・カラー」という問題が浮上する。「ロオカルを出すことを考へずに、到底真に迫る小説を書くことが出来ない」と田山花袋が述べたのは1907年、『小説作法』においてであった。日本へ編入された沖縄は地方色を豊富に持ちながらも確固とした「ローカル・カラー」を小説に刻印できなかったと嘆いたのは、沖縄学の父・伊波普猷の弟、月城であった。もちろん、明治・大正期、沖縄の散文小説にも素晴らしい作品はあるのだが。
戦後沖縄における小説の画期をなしたのは、やはり大城立裕「カクテル・パーティー」の芥川賞受賞(1967年)であろう。「基本的人権を守る重厚な問いが開示」された本作は、沖縄の文学が対峙(たいじ)する問題の大きさを問うた。戦後沖縄の小説は「ローカル・カラー」を踏まえつつ豊かに展開するのである。
本書の著者は、沖縄の文学が抱える特徴に、時代との対峙、状況への抗いを見いだす。またそのテーマとして、日本への同化と異化、差別と偏見との戦い、表現と言語の問題、郷里・沖縄への郷愁を挙げている。本書では、これらの視点を用いながら、本県の芥川賞作家大城立裕、東峰夫、又吉栄喜、目取真俊の作品が考察される。また「沖縄文学の多様性と可能性」を問うために、池上永一、長堂英吉、吉田スエ子、崎山多美らの作品を取り上げ、神話や歴史、言葉の問題から評価していく。他に、文学賞や若い作家についての言及もあり読み応えがある。
著者は、小説作品の的確で簡潔、明瞭な分析を展開している。本書は戦後における沖縄文学の軌跡をたどるうえで欠かせない良書である。
(柳井貴士・愛知淑徳大学創造表現学部講師)
おおしろ・さだとし 1949年大宜味村生まれ。那覇看護専門学校非常勤講師。元琉大教育学部教授。主な著書に小説「沖縄の祈り」「記憶は罪ではない」「海の太陽」など。