
◆「食」という人々の日々の営みから大きな視点で政治を見る
作家の辺見庸氏が、共同通信時代に手掛けたルポルタージュの名著。この「もの食う人びと」は1994年、講談社ノンフィクション賞を受賞した。飽食の日本を旅立ち、紛争地帯や飢餓がまん延する地域で、現地の人たちと「食」を通して交わる。ときには、バングラデシュの首都ダッカで残飯をくらい、原発事故が起きたウクライナのチェルノブイリでは、放射性物質で汚染されたスープさえすする。
「食」という人々の日々の営みから、大きな政治を見る視点が示唆深い。
「食とネオナチ」の一節によると、1990年の東西ドイツ統一後、ケバプ(トルコ料理の一つ)の店が急増した。ベルリンでは統一後、3年もたたないうちに4千軒に倍増。統一後にドイツ企業を解雇されたトルコ人が、ケバプ店を新規開店していた。
背景にあるのは、旧東ドイツ市民の優先雇用とネオナチ勢力による外国人排斥。ある地元大学生はこうコメントしている。
ネオナチの青年たちは、主として旧東側の貧困家庭出身であり、失業者も多く、失業トルコ人とともに、ベルリンの壁の崩壊と政府の無策であらわになったドイツ社会の非受益者層だ。
有名ロックバンドの歌詞「弱い者がさらに弱いものをたたく」構図が古今東西、共通のように思えてくる。
著者は序文にこう記している。
私はある予兆を感じるともなく感じている。未来永劫(えいごう)不変とも思われた日本の飽食状況に浮かんでは消える、灰色の、まだ曖昧(あいまい)で小さな影。それが、いつか遠い先に、ひょっとしたら『飢渇』という、不吉な輪郭を取って黒ずみ広がっていくかもしれない予兆だ。
今や、日本全国に約5千カ所の子ども食堂が乱立している(2020年)。著者の洞察力に驚嘆するほかない。
◆「取材という言葉が一方的で嫌いだ。見るということは見られることだ」
「もの食う人びと」は大ベストセラーになっているため、中身の紹介はここまでとし、筆者(高宗亮輔)の個人的な体験も交えて取材、調査報道との関係を考えたい。
6年前、辺見氏にインタビューをした。当時は集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法が成立した時期。戦後70年を問う著書「1★9★3★7(イクミナ)」の執筆意図も合わせて話を聞いていたとき、辺見氏はこう言った。
「取材という言葉が、一方的で嫌いだ。見るということは、見られるということだと思うんだよ、俺は」
その瞬間、飢渇に陥る日本の将来を見通していた辺見氏の視線の焦点が、ピタリと私の目玉と重なった。と同時に、背中から油汗が噴き出した。意味は分からなかったが、自分の浅はかさが、なぜか全て暴露された心地だった。今でもこう書いているだけで、心拍数が上がる。
確かに、取材の「取」は一方的なイメージがつきまとう。略取、奪取…。漢字学の大家、故・白川静氏の字源辞典「字統」によると、「取」は討ち取った敵の左耳を切り落とす意味にさかのぼり、転じて、他国への侵攻や獲物の捕獲も意味するようになったそうだ。
過熱取材が批判される「メディアスクラム」は、この一方的なイメージと重なる。想定したコメントで「言わせる」、自然災害被害者の顔写真を「泣き落としてでも取ってくる」なども同類ではないか。取材行為は常に、書く材料をかっさらう暴力性や、それを恥じない傲慢(ごうまん)に陥る危険性がある。実際にその落とし穴に落ちれば、「マスゴミ」と批判される。辺見氏は一方的な取材を戒めたとのだと、今は理解している。
◆取材はそもそも暴力性や恥と背中合わせだ 「あなたにその自覚はあるか?」
辺見氏は「もの食う人びと」に、ソウルの日本大使館前で割腹自殺を図った元従軍慰安婦の女性とのやりとりを、取材過程とともに記している。(太字斜体は高宗。ネンミョンは冷麺のこと)
「使ったサック(コンドーム)をね、将校が来る前に洗うのよ」
金さんは両の親指と人さし指でゴムを摘(つま)む動作をしてみせた。
「小川でね。みんなしてね、しゃがんでね。辛かったですよ、情けなかったですよ、これがいちばん」
私のネンミョンはゴムひものように硬く喉(のど)をふさいでいる。
あの、そのサック洗いの時、月がですね、その、満月とかが出てなかったですか。かすれ声で問う。私の描いた情景に、月はあった。川面に映り、揺れていた。*ぶん、あとでそう書きたかっただけなのだ。*
金さんは答える。
「なかったです。いつも曇っていたですよ。一度に四十個も洗ったりしたですよ」
あんた、あれがね、サック洗いね、忘れられないよ。いまでもね、思い出がやってくるのよ。いつか日本に行って、私死ぬところを、日本人に見せつけてやりたくなるのよ……。
私は金さんを半世紀前の記憶の古井戸に突き落としていた。
取材する側としては、どんなに辛い経験でも従軍慰安婦としての経験に触れざるをえない。記者という職についている人の多くは、この点に納得すると思う。一方、満月について聞いた過程を記す記者がどれだけいるだろうか。あえて記さなくても、原稿は成り立つだろう。原稿の流れからすれば余分なものと考え、私なら割愛すると思う。少なくとも、書き手の想定通り「満月があった」と女性に言わせようとしたことを、気まずく思い、そのやりとり自体をなかったことにしようという心理的な防衛機制が、間違いなく働く。
女性のエピソードをメインととらえたときに、背景に退いているこの余計な部分にこそ、辺見氏は取材者の特権的な立ち位置を暴露させているのではないか。「書く側だけ無傷ではいられない」とでも言うように。女性を半世紀前の記憶の古井戸に突き落としてでも旧日本軍の蛮行を暴く行為を、厚顔無恥に転落することから踏みとどまらせているのは、この自己批判だと思う。
所属しているマスコミの大小によらず、記者クラブに所属しているかどうかによらず、取材という行為がそもそも暴力性や恥と背中合わせだ。背中から噴き出した油汗に、私はこう確信している。取材や調査報道の力は、もちろん権力者と対峙(たいじ)したり、社会的な問題を暴露したりすることに使わなければいけない。しかし、さらに言えば、「もの食う人びと」が教えてくれているのは、取材者がその暴力性への自覚を失い、きれい事で塗り固めた途端、報道が総崩れするということだ。
辺見氏の視線が問い掛けてくる。「あなたは自覚があるか」と。
取材者は見る側ではない。見られる側だ。
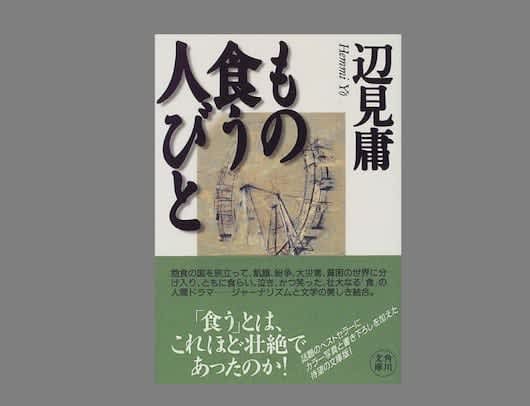
(フロントラインプレス・高宗亮輔)
■参考URL
「もの食うの人びと」(辺見庸著)=角川文庫版・初版1997年
「1★9★3★7(イクミナ)」(辺見庸著)
辺見庸ブログ
