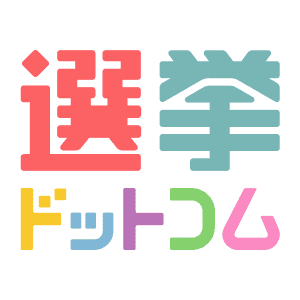決して珍しい存在ではない、さまざまな政治家たちの「失言」。直近では、当時東京五輪・パラリンピック組織委員会会長であった森喜朗氏の「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」という昨年の発言が記憶に新しいところ。この発言がもとで、森氏が会長職を辞任したことは周知の通りですが、『政治家失言クロニクル』は1947年における吉田茂首相の「かかる不逞の輩が国民中に多数あるものとは信じませぬ」から森氏の理事会発言にいたるまで、70年以上にわたる失言の歴史を、テキストユニット「TVOD」のコメカ氏、およびパンス氏の縦横無尽な対談を通して振り返っていく一冊です。
https://www.amazon.co.jp/-/en/TVOD/dp/4910511059
岸信介氏と安倍晋三氏の「失言のつながり」
さて、のっけから少し話が飛びますが、失言のなかには、文字面を見ただけで「ああ、これはヤバいな」と思うものもあれば、それがどのような文脈で口に出されたのかを示さなければ、「?」となるものもあります。
たとえば、岸信介首相(1960年)の「神宮球場は今日も満員」という発言。これだけでは単に球場が活気に満ちていることについて、自然な感想を口にしただけにも思われますが、この発言をより広げると、「デモは騒がしいようだが、神宮球場は今日も満員だ」となります。
しかし、これでもまだ、よくわからないですね。さらに広げてみると、岸氏はこの発言とセットで、「私は『声なき声』に耳を傾ける。いまは『声ある声』だけだ」とも語っています。そして当時は、60年安保闘争の真っただ中で、日米安全保障条約に反対する運動家や労働者、また学生たちが政府に対して抗議の声を上げていました。
つまり、岸氏はデモの参加者たちが決して多数派というわけではなく、球場に足を運ぶようにごく普通に生活を送っている人々も多いことを重視し、また自身はデモの参加者の声を、意識するに足らないものと見なしている、ということがうかがえます。
時代は一気にくだりますが、岸氏の孫にあたる安倍晋三首相(2017年)は、東京都議選の応援演説において「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と発言しています。
「こんな人たち」とは誰か。街頭で安倍氏へと抗議の声をあげる、決して少なくはない聴衆のことを指しています。両氏の言葉に理があるかどうかはさておき、自身に反対する声を軽視するニュアンスが感じられる点で、これらの発言は一致を見せ、それを血のつながりに由来するもの、もしくは祖父から孫への影響と読むことも可能でしょう。
(ちなみに、安倍氏が2018年の年頭記者会見で「声なき声」というフレーズを使用したことも本書では紹介されています)
もちろん、こうした解釈を単なるこじつけと切り捨てることもできますが、失言には先ほども言及したように「文脈」があります。『政治家失言クロニクル』は、戦後間もない時期から現在までに至る政治家たちのさまざまな失言を、その背景となる社会史、また音楽や漫画などのサブカルチャーと結びつけて解説し、いわば失言から「戦後史」を逆照射することにその特色があります。
時代を象徴するさまざまな失言
社会史に絡めて、時代を象徴する失言を見てみましょう。たとえば佐藤栄作首相(1965年)の「ベトナム北爆には理由があり、爆撃される方にも責任がある」という発言。ベトナム戦争当時は、世情の反映もあってか軍事関係の失言が多く見られますが、佐藤氏のこの発言はその代表格で、本書では「親米保守の面目躍如って感じ」と評されています。
あるいは、灘尾弘吉文相(1968年)の「大学紛争で大学の一つや二つはつぶれても仕方がない」という発言。東大安田講堂事件をはじめ、当時さまざまな大学で全共闘、および新左翼の学生たちによる紛争が巻き起こり、大学の機能不全があちこちで見られたことを受けての発言でした。本書では佐藤首相が日大闘争に対して「政治問題として対処する」と発言したことも紹介され、その影響力の大きさが伝わってきますね。
また、本書はただ時系列で失言を追うだけではなく、「大日本帝国」時代の日本の行動に関連した歴史認識のずれや、難病患者や黒人への差別意識など、テーマに大別しての失言の紹介も行っています。
たとえば、差別発言の多さで80年代に印象だったのは、中曾根康弘首相と渡辺美智雄衆院議員です。「(アメリカは)黒人やプエルトリコ人がいるから、知的水準が低い」「おまじりみたいな国籍のよくわからんという人は尊敬されない」(ともに1986年)と述べる中曾根氏に対し、「アメリカの連中は黒人だとかいっぱいいて、『うちはもう破産だ』(中略)ケロケロケロ、アッケラカンのカーだよ」「中国の山西省あたりにはまだ穴を掘って人が住んでいる。政治が悪いからだ」(ともに1988年)と述べる渡辺氏。その露骨さにおいては、ともに負けず劣らずの存在感を示す両氏ですが、文中では当時の日本の、一般的な人種差別に関する意識・認識はこのレベルと大きな差はなく、「ベタベタなキャラクターも半ばパロディックに消費されるという時代だった」と解説されています。
「キャラだから仕方がない」で済ませてはならない
上記はわずかな例ですが、「キャラクターの消費」という側面は、近年の失言においてもまた地続きなものでしょう。たとえば麻生太郎氏の、「7万8000円と1万6000円はどっちが高いか。アルツハイマーの人でもわかる」(2007年)や、ネットの画像でも見る機会が多い、ハローワークでの求職者に浴びせた「今まで何してたんだ」(2008年)などの発言。本書では氏の「『悪童』的なキャラクターに親しみを感じる」、決して少なくはないファンの存在に触れられ、それがいまだに麻生氏を、第一線の政治家たらしめている側面もあることが示唆されます。
また麻生氏以外にも、本書では「現代の失言王」という称号を得る森喜朗氏、「三国人発言」などで知られる元東京都知事の石原慎太郎氏なども含め、著名な政治家の失言が「誤解を恐れずに言い切る豪胆さ」などのようにプラスの方向に解釈されたり、またはお茶の間の娯楽として消費されるような一面があることは、今でも否定できません。そうしたことを考慮すると、「その都度きちんと抗議していくしかない(中略)ずっと継続的に怒り続けていかないといけない」という差別的な失言を受けてのコメカ氏の指摘が、訴求力をともなって伝わってきます。
政治をより身近にするための処方箋
とはいえ、本書の魅力は、「失言から政治史、また政治への心構えを真剣に学ぶ」というよりは、むしろ気楽にページをめくることができる、その「軽さ」にあります。冒頭でも言及されるように、本書でのふたりの対話はきっちりとした対談というよりは、「雑談」に近い語り口のもので、失言以外の話も少なくはありません。また、文芸やサブカルチャーへの造詣が深い両者の資質もあってか、思想・評論では江藤淳や吉見俊哉、漫画では手塚治虫や岡崎京子、小説では松本清張や村上春樹、映画では『団地妻』シリーズ、ドラマでは『ふぞろいの林檎たち』『電車男』など、時代を彩ったさまざまな作家や作品に言及され、この時代にこの作品があったんだ、と知るような楽しみもまた存在します。
そして、こうしたいい意味での(と私は思います)「脱線」は、本としての軸がぶれている、ということではありません。先に述べたことの繰り返しとなりますが、失言には「文脈」があり、その当時の社会情勢や文化とも、どこかの部分で地続きになっています。また、自分にとって身近な「あの作品」や「あの出来事」とさまざまな失言がつながっているのだと知ることは、失言、ひいては政治をより身近なものにする礎にもなりえます。
そう考えると、『政治家失言クロニクル』はさまざまな失言を紹介すると同時に、今でも硬いイメージのある「政治」像をよりやわらかに解きほぐす、一種の処方箋としても意義のある一冊とも言えるのではないでしょうか。
パンス氏は本書のまとめで、「過去を生きた人々についてより深く調べる、歴史のなかに分け入っていくきっかけになれば」とも語っています。『政治家失言クロニクル』が「きっかけ」になるかは読む方次第ですが、少なくとも、「楽しみながら読める」という点で、まずは手に取ってみて損のない一冊です。