子どもの死ほど悲しいものはない。防げるものなら何としても防ぎたい。しかし、子どもの死因では長年、「不慮の事故」が上位に位置し、下位に落ちることはなかった。こうした中、政府は本格的に「チャイルド・デス・レビュー(予防のための子どもの死亡検証、CDR)」の導入に向けて動きだした。
子どもの死に関してはこれまで、医療や教育、警察、福祉といった関係機関がばらばらに原因究明などに当たってきた。CDRはその欠点を補い、各機関が情報共有して死に至った要因を検証し、対策を立てる仕組みだ。では、そのモデル事業の現場はどうなっているのか。日本でも始まろうとしているCDRの課題に迫る連載。最終回の4回目はその現場に迫った。

イメージ(撮影:穐吉洋子)
CDRは欧米発の取り組みで、日本では小児科医らが中心となって導入を訴えてきた。子どもに関わる機関が一堂に集まり、情報と知恵を持ち寄って、死因を究明。そのうえで、予防策まで考えるところに特徴がある。保育園、学校、病院、警察……という多機関の連携こそがCDRの真骨頂だ。
日本で初めての試みは、2020年度からモデル事業として始まり、2年が経過した。主管の厚生労働省は取りまとめを公表していないため、制度化の課題として何が浮かび上がったのかは判然としていない。ただ、2021年夏にフロントラインプレス取材班が独自に行った調査では、「警察」「個人情報」という2つの壁が見えている。
子どもがなぜ死んだのか。それを検証するには、関係者の聴取や現場検証、司法解剖などを手がける警察の捜査情報が欠かせない。
◆刑事訴訟法47条のただし書きが考慮されていない
しかし、刑事訴訟法47条の「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない」という規定などにより、CDRでは捜査情報が共有されにくい。この条文には「但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、その限りではない」というただし書きがあるが、ほとんど考慮されていないのが実情だ。
個人情報保護の壁も厚い。子どもや家族の個人情報は、遺族が同意しなければCDRで使用できない、というのが一般的な見方だ。遺族が虐待の当事者だった場合、拒否される可能性も高くなる。つまり「警察の捜査情報」と「個人情報」がなければ、目的に沿うレベルで検証を行うのは難しい。
こうした中、厚労省はモデル事業2年目を前にした2020年度末、「警察の捜査情報」と「個人情報」を利用しない前提でCDRを進めるとの方針を明示した。1年目には示していなかったことから、それまでの姿勢を後退させたとも受け止められ、「実現はいつになるのか」「結局、実現しないのではないか」と懸念も出ていた。
ところが、モデル事業に取り組む9道府県は、必ずしも、こうした厚労省の姿勢に縛られていたわけではないようだ。実際、警察がCDRに積極的に参加しているところもある。その1つが香川県だ。
香川県子ども家庭課の担当者は「県警に参加をお願いしに行ったところ、すぐにOKが出ました。スムーズに話が通って県警の参加が決まりました。CDRは虐待にも関係がありますから」と言う。香川県警はCDRに複数の部署から担当者を参加させている。他地域では「情報を共有してくれない」と批判の対象になりがちな警察が、なぜCDRに積極参加しているのか。
2021年度まで県警人身安全対策課次長を務め、現在、捜査第一課に所属する岡修司・次長(47)はこう語る。
「警察は、犯人を捕まえたり検挙したりがクローズアップされがちです。でも、もう1つ大きな柱として、『予防』があるんです」
人身安全対策課は児童虐待防止を担当している。岡次長によると、CDRが児童虐待に限らずに多様な問題を扱い、複数の機関が参加していることに警察にとっての利点がある。
「多機関が持っている資料を合わせることで、何か潜在的な問題が見えてくるかもしれません。潜在的な問題が見え、それを解決する術がモデル事業の中で見えてきたら将来の予防につながる。警察が取り組む予防という大きな柱にとっても、すごく意義があると思うんです」
モデル事業に参加して、多機関の担当者と交流を深めることができ、今後の連携面からもプラスだったという。
◆モデル事業が始まる前から関係ができていた
香川県警ではこれとは別に、4~5年ほど前から、さまざまな機関と協力する機会が増えている。検察、児童相談所、けがなどを診る病院などだ。
「警察には事件化したら終わりというイメージが昔はありました。今は、たとえ事件化できなくても、将来の家庭環境の構築が大事だ、ということにシフトしています。だから、それに関わる多機関の方々と話さないと、情報が偏ります。各機関で何ができるのかということも、警察は知りませんでした」
つまり、モデル事業が始まる前から、香川県警には他機関の業務を知り、困ったことについては改善を求めたり、歩み寄ったりする関係ができてきた。そのため、CDRのモデル事業に参加した機関の一部にも、警察に対する理解の蓄積があり、捜査情報を全て出せないことについて反発はあまり見られないという。
「警察が情報を出せないのは当然です。でも、どこまでだったら出せるかを、検事さんと話して(出せるものは出すとの判断もある)。CDRは守秘義務が課せられていますし、そもそも、参加する各機関の皆さんに公判を妨害するつもりなんてない。CDRには、子どもの事故や死をなくすという目的がはっきりしているわけですから。(警察も)いきなりシャッターを下ろさないほうがいいのでは。お互いにできることをやっていく。それを続けていけば、いい方向が見えてくるかもしれない」
警察と個人情報の壁。この2つをまとめて、独自に乗り越えようとする地方公共団体も出てきた。モデル事業に初年度から参加する滋賀県だ。
「われわれとしては、できないことの理由がわからん」。滋賀県のCDRを牽引している滋賀医科大学社会医学講座(法医学部門)の一杉正仁教授(52)は、厚労省の手引きの“後退”に強く反発している。「できないこと」とは、捜査情報と個人情報の利用を前提にしないという厚労省の新たな考え方を指す。一杉教授は、この改訂どおりにやると、CDRは完遂できないという。
「目的が達成できないので、非常に不適切です。滋賀県としては、今後もCDRをやっていきたいと考えています。そのときは(厚労省の手引きどおりにはやらず)個人情報も家族の同意なしで、司法解剖の結果も適切に使っていこうと全員の意見が一致しました。法的にも問題ないと確認しています」
滋賀県のCDRには、県警と地検も参加している。そのメンバーも含め、「全員一致」の見解だという。

CDRで使用する「死亡調査票(基本票)」
◆厚労省の方針変更で別のアプローチに変更
滋賀県でも、香川県と同様にモデル事業に着手する前から、助走のような取り組みが始まっていた。県死因究明等推進協議会の取り組みがそれだ。
この中で、子どもの死亡調査を実施。そうした経験が生き、1年目のCDRモデル事業は、過去3年間の18歳未満の子どもの死亡例131人分を可能な限り追いかけ、死に至る経緯を細かく調べることができた。検証だけでなく、シーンごとの予防策の検討にも力を入れた。提言を知事に提出し、「非常にいい結果が出た」と関係者も手ごたえを実感したという。
ところが、2年目は厚労省の方針変更に伴い、遺族の同意を得ることとし、司法解剖の結果も捜査当局に求めない方式に切り替えた。すると、主治医を通じた協力要請に対し、遺族から返事がないケースが出てきた。そうした場合、遺族の同意がないため個人情報を検証に使えない。
捜査情報を求めない前提となったため、司法解剖の結果も利用できなくなった。それを補うため、滋賀県では、司法解剖に回るまでのカルテや行政への提出書類など、別のアプローチで必要情報を収集する、裏技のような手段で切り抜けるしかなかった。
こうした事態を受けて滋賀県は、CDRにおける個人情報の取り扱いや司法解剖結果の使用などの関係法令について、法律の専門家も交えて詳細に検証した。その結果、いずれについても、法的には「問題なし」との結論になったという。
一杉教授は、2021年8月に滋賀県大津市で起きた小1女児暴行死事件に言及した。「妹がジャングルジムから落ちた」と近所の家に駆け込んだ兄が、実は暴行を加えていて、家庭がネグレクト(育児放棄)状態であったいう事件だ。その事実は、家庭裁判所でも認定された。
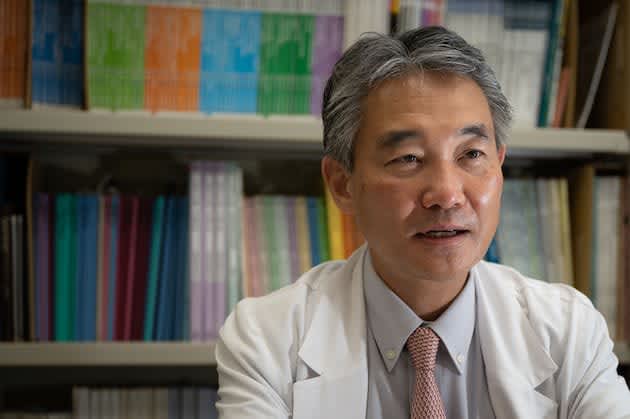
滋賀医科大学の一杉正仁教授(撮影:穐吉洋子)
二度と同じことを繰り返さない、事例検証を通じて子どもの命を守るための対策を講じる――。CDRのその観点から言えば、この事件は検証のテーブルに乗せるべき事案だ。
「そうした家庭の子に何があったのかという原因を調べたり、児童相談所の対応の適否を判断したりするのに、なんで保護者の承諾がいるんですか。どうすれば予防対策を取れるかを検討するのに、保護者の同意を取んなきゃいけないって。バカを言うんじゃないってことですよね」
司法解剖についても、一杉教授には言うべきことがある。
「司法解剖とは、亡くなった原因を明らかにするとともに、その死の背景に犯罪がないかどうかの有無も確認するんです。司法解剖をやって、結果的に犯罪には関係ありませんでしたというケースは、たくさんあります。そういう結果を使っていけないなんて、考えられない」
◆地元の理解も、国民の理解も必要
一杉教授は、矯正医療に携わり、事情を抱えた加害少年たちに接している。だからこそ、CDRについて思うところもある。
「その子たち、ほぼ全員、虐待されていますよ。もしくは、親に捨てられたり、非常に不遇な生活を送っている。そういう子たちがどうして犯罪に手を染めるようになったか、僕は知ってしまった。手をかけて他者を死なせた子。あるいは交通事故を起こして死なせた子……。CDRは『防ぎうる死を予防する』と言うんだけれども、究極は、子どもを取り巻く社会をもう一度、見直さなきゃいけない。そのきっかけになると僕は思っているんです」
そのために、CDRは地元の理解も国民の理解も必要だと一杉教授は言う。CDRの重要性をわかってもらおうと、モデル事業について個人情報の問題に抵触しない範囲で、マスコミにも情報を開示してきた。そのオープンな姿勢が厚労省の気に障ったらしい。
「僕のところに電話がかかって来て、『個別の事案に関してマスコミに言ったんですか』って。言うわけない。(マスコミ報道を見た厚労省が)『個別の事例を連想することになる』とかなんとか、無茶苦茶なことを言っているんです」
フロントラインプレスの取材班が、2021年夏にモデル事業を行う地方公共団体に対して行ったアンケート調査でも、厚労省の指示で情報を出せないとの回答が目立った。個人情報に関係ない情報も出せないというのだ。
その一方で、厚労省自身は、モデル事業の1年目の総括を依然として公表していない。CDRが国民に浸透しない大きな理由の1つは、こうした“中身を外部に知らせない”という厚労省の姿勢だ、と一杉教授も主張する。
「2020年度のモデル事業の報告書として、滋賀県は100ページ近い報告書を厚労省に送っているんです。(1年目には)7つの府県にモデル事業をやらしているのに、総括をしてもらわないとね。滋賀県のやり方はダメですね、とか、〇〇県のやり方がいいですね、とか。困りますね、やるだけやらせておいて」
◆日本小児科学会地方会などに圧縮版を配布
滋賀県では1年目の報告書を、個人情報を抜いた圧縮版にして47都道府県にある日本小児科学会地方会などに配った。子どもの死の予防のために、他の地域でも役立ててもらえたら、という思いからだ。
CDRは厚労省の手引きどおりにやらない場合、モデル事業として採用されない可能性もある。そうなると国からの予算がなくなる。それでも一杉教授は「手弁当になっても、手伝ってくれる有志でやるつもりだ」と話す。

イメージ撮影:穐吉洋子
4月からの2022年度は、厚労省が当初、CDR本格導入の初年度として目標設定していた年度だ。その実現は後年にずれ込んだ。では、2023年4月に創設予定のこども家庭庁は、CDR推進の大きな動輪になれるのか。本当に縦割り行政の弊害を排し、「防ぎうる死を防ぐ」役割を果たせるのか。子どもの不慮の事故、死亡は、今日も明日も起こりうる。大人たちの本気度が問われている。
(初出:東洋経済オンライン)
■連載・こども家庭庁とCDR■
【1】子どもの死を防げるか 試される「ど真ん中政策」(2022年4月13日)
【2】虐待防止にどう生かす「子どもの死亡検証制度」 藤田香織弁護士に聞く(2022年4月15日)
【3】山梨県知事がCDRを「重要政策」に据える理由(2022年4月16日)
