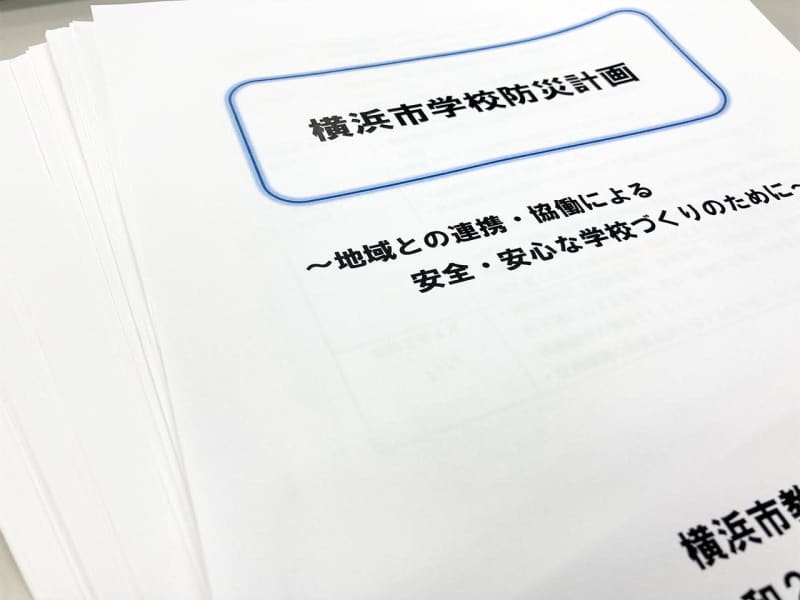
災害時には、教職員がマニュアルを見る時間もないほど、想定外の出来事に追われる学校現場。東日本大震災当時、横浜市内の小学校を指揮した元校長の記憶をたどり、子どもの命を守る現場の対策を見つめる。
「学校現場は、保護者が迎えに来るまで児童を絶対に留め置くとは想定していなかった。基本的には集団下校させて帰すものだと思っていた」。震災当時、横浜市内の小学校校長だった60代男性は振り返る。
震災発生時、校長会の総会に出席するため、市内の小学校ではほとんどの校長が不在だった。元校長は徒歩で何とか学校に戻り、保護者と連絡が取れた児童を帰すように指示した。
「当時の計画には『保護者と連絡を取り、状況に応じて生徒の引き渡しを開始する』とあった。この文面では子どもをとにかく帰すことになってしまっていたのもやむを得ない」
◆保護者迎えまで「留め置き」
横浜市教育委員会は、保護者が帰宅難民となったため、自宅で1人で夜を明かす児童がいたなどの事態を経て、「市学校防災計画」を震災後の7月に大幅改訂した。変更前は「大規模な地震」とあいまいだった想定を、「震度5強以上の地震が観測されたとき」に変更。その上で、「保護者が学校に引き取りに来るまで預かり(留め置き)」を基準とした。
「改訂前も生徒を学校で保護する意識はあったが、『状況に応じた生徒の下校・引き渡し』とあり、対応がぶれてしまったと思う」と市教委の担当者。改訂後は「保護者が留守の家に児童を帰宅させることは、かえって危険」とも記載。保護者情報が書かれた「引き渡しカード」作成も徹底するなど、より児童の安全に配慮した運営が意識されるようになった。
◆共通理解、ほど遠く
3.11の教訓を生かすため、市教委は留め置きなどの重要性を記した「市学校防災計画」を教職員への研修教材として活用するよう呼び掛けるものの、現場では「防災担当の先生は計画と向き合う時間はあるが、それ以外の教員はそこまで意識がまわらない」(男性教諭)との声も聞かれる。
英語、プログラミングなど、教える教科が年々増える現場の負担は大きく、元校長も「防災教育をしっかり行おうとすると、『また新しいことをやるのか』と思ってしまう先生もいて難しい」と指摘する。
11年以降、熊本地震を踏まえた対策や土砂災害などで同計画を9回改訂している市教委は「計画改訂には力を入れてきたが、周知の徹底は考えるべき課題」と認める。改訂の度に校長には通知し、防災担当の教諭らが被災経験者の話を聞く講座などを開くなどしてきたが、全教職員への徹底にはほど遠い。
◆一人一人が日ごろの意識を
元校長は「一人一人の校長の意識や能力によって、防災への取り組みが変わってしまうのは事実で、残念」と声を落とす。
3.11の時、元校長の小学校には周辺の外国籍住民らが集まり、翌朝まで校内を開放した。「困っている人のために」と必死に取り組んだが、区役所などと連絡がついた深夜になって、家屋倒壊が起こった場合のみ学校を開放するルールだったことを知らされた。
「何か起これば、現場はマニュアルを読んでいる暇はない。だからこそ、一人一人の意識を日頃からつくることが大切です」
元校長は震災後、東北を毎年訪れ、宮城県石巻市で児童ら84人が津波の犠牲となった大川小にも足を運んだ。誰もいなくなった校舎の残骸を見たからこそ、思いを一層強くし、被災地で撮影した動画などを使って教員らに訴え続けた。
◆「学校安全神話」は通用せず
元校長も、大型台風の際、児童をいつ帰宅させるか迷ったことがあった。早々に帰す判断もあったが、地域の人から「駅に向かう道は、ひざまで水があふれていて危険だ」と連絡があり、取りやめた。地域の避難訓練などに積極的に参加し、地元とのつながりが強かったことで寄せられた情報だった。小さな取り組みが、子どもの命を守ることにつながると痛感した。
「『学校安全神話』は通用しない。防災教育でなく、命を守る教育に防災を位置づけないと、学校といえども当事者意識を持ち続けることは難しい。子どもの命を守るために、やるべきことはまだある」
【横浜市学校防災計画】市教育委員会が2006年に発行したマニュアルで、各学校防災計画の基本となるほか、教職員の防災研修教材となる。震災対策、風水害対策など4部構成で計163ページ。市立小中高校や特別支援学校などは同計画に基づき、大規模地震発生時の初期対応や年間の防災教育など「学校防災計画」を策定している。
